本日のお悩み
プライベートで辛いことがあったり心が不安定な時、なぜか利用者さんに分かられているんじゃないかなと思うことがあります。
夜勤の前にザワザワした気持ちになったときはお看取りが発生したり、同僚もこういうことが結構あるようです。
みなさんもこういう経験ありますか?
「経験知」がその人の感覚を研ぎ澄ますのかもしれません
いわゆる第六感、というものでしょうか。
あります、あります。
実は私も、以前は「実際に存在するもの」しか信じていなかったのですが、介護の仕事をはじめてから「あるかどうかわからないもの」の存在も信じるようになりました。
介護には科学的な視点が不可欠ですが、科学的な視点「だけ」ではない、ということに気がつきました。
■第六感とプロの関係
ご質問を拝読し、第六感について少し調べてみました。
辞書には「視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚の五感以外の六番目の感覚。理屈では説明が出来ないが、物事の本質を感じ取る心の働き。直感。」とあります。
これを読んで、思い出したことがあります。
以前上司から「プロとは、そうでない人には見えないものが見え、聞こえないものが聞こえる人だ」と教わったことがありました。
また、六車由実さんの「驚きの介護民俗学」という本の中には、「年をとるとは、個人差はあるにせよ、それまでは見えていなかったものが見えたり、聞こえなくなったものが聞こえるようになることであり」と書かれています。
質問者さんが感じていることは、まさにそういったことなのではないでしょうか。
■人間に対する洞察を深める
それをどう感じるかは人それぞれだと思いますが、私は「興味深くておもしろいな」と思います。
きっと私たちが介護の仕事という経験の中で専門性を身につけていったり、ご利用者が歳を重ねて経験知を積んだりすることで、五感以外の感覚が身につく、はたまた敏感になる、のかもしれません。
わからないことはたくさんありますが、人間に対する洞察を、絶えず深めていくことが重要なのかなと思っています。
人間とはなにか、というテーマを考え続けると思うと、つくづく、介護の仕事は奥が深くておもしろいですね。
人体の生理学や心理学にとどまらず、生活を構成するさまざまな事柄のさまざまな知識がその「第六感」なるものをより研ぎ澄ますのかもしれません。
■最後に
第六感が科学的に証明される日が来るかどうかはわかりませんが、世の中、少しくらいわからないことがあるほうが、面白みが増すんじゃないかなと個人的には思っています。
質問者さんが、毎日心配事なく仕事に行けることを祈っています!



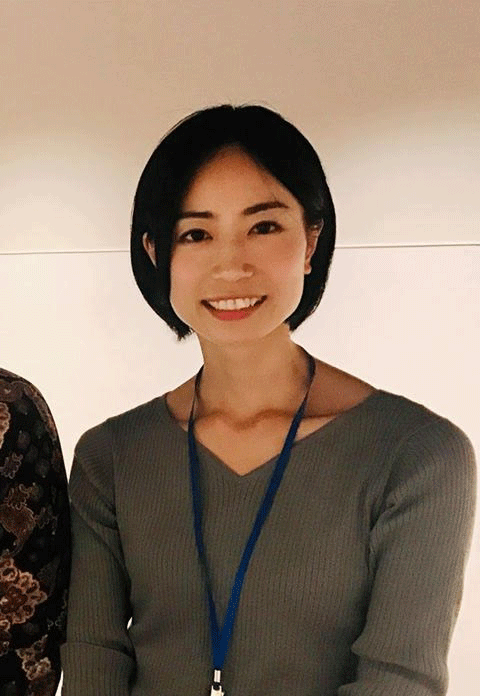


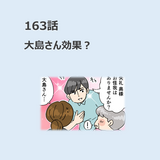
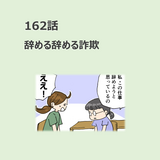
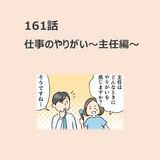
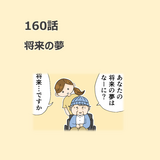
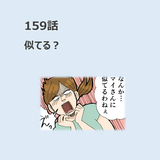





















社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員