介護職が利用者さんに依存されてしまった…そんなときの対応法は?
■執筆者/専門家

ゆりかごホールディングス株式会社 代表取締役 株式会社ゆりかご 代表取締役 茨城県訪問介護協議会 副会長 茨城県難病連絡協議会 委員 水戸在宅ケアネットワーク 世話人 介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・看護師・介護支援専門員・相談支援専門員
■「依存」とはどのような状態か?
私自身も、「あなた以外の人が来ても断るからね!」と強く言われてしまい、対応に困った経験があります。
このような経験を通して、私は改めて「なぜ、強い依存関係になってしまったのか?」を振り返りました。そもそも、「依存」とはどのような状態なのでしょうか。
依存とは、「自分以外の他者を頼りにして、自分の存在を保っている状態」と言えます。
私たちは社会の中で生きています。社会とは、複数の人々が空間に持続的に集まり、関係を築いている状態です。 物理的にも精神的にも、私たちは一人では生きていけません。つまり、誰もが何らかの形で他者に依存しているのです。
依存そのものは、決して悪いことではありません。
しかし、その依存が過度になると、関係性のバランスが崩れ、さまざまな問題が生じる可能性があります。
■依存の強さはどのように決まるのか?
私自身の経験である「あなた以外に訪問されても断るからね」という利用者さんの言葉で考えてみましょう。この言葉の背景には、以下のような認識がある可能性があります。
・私を「他の誰よりも頼れる存在」として見ている
・もしくは「他の誰にも頼ることができない状態」と感じている
このように相手が自分をどう認識しているか、そして他者との関係性がどのようなものなのかによって、依存の強さは異なってきます。
■「誰がサービス提供しても目的が達成されること」は介護の大原則
この仕組みを支えているのが、ケアマネジャーによるケアプランの作成です。
ケアプランに基づいて、各サービス事業所では個別支援計画が作成され、計画的に支援が行われます。つまり、どの職員が関わっても、利用者さんは自分の目標に向かって進めるはずなのです。
しかし、現場では「あなた以外は訪問されても断るからね!」というような発言を受けることがあります。このような言葉からは、利用者さんの目的(目標達成)と手段(介護サービスを受けること)が入れ替わってしまっていることが見えてきます。
また、他職員と自分のサービスに質の差があることも、依存を生む一因です。
もし、どの職員も同じ質でサービスを提供できていれば、特定の職員に強く依存することは少なくなるでしょう。
■利用者さんの特性によって変化する関係性
たとえば、目標に対して「自分で何とかしよう」と積極的に取り組む方もいれば、自分で努力することが苦手で、他者への依存が強くなる方もいます。
このように、他者をどれくらい頼りにするかは人それぞれであり、一律の対応ではなく、個別の理解が必要です。
そのため、利用者さんの支援においては、「アセスメント」が非常に重要になります。
アセスメントを通じて、利用者さんの価値観・行動傾向・支援の受け方などを理解することで、より適切な関係性の構築と支援が可能になります。
なぜ高齢者は介護職に依存するのか?その心理を理解する
2.介護職の「やってあげる」優しさに甘える
3.不本意な施設入居からの反発
■1.身体能力の低下や病気がもたらす心理的負担
たとえば、歩行や排泄、食事など、日常生活の基本的な動作に支援が必要になることで、「自分らしさ」や「自立性」が失われたように感じる方も少なくありません。
このような変化は、本人にとって大きな不安や喪失感をもたらします。
「迷惑をかけている」「もう役に立てない」といった思いが積み重なることで、精神的な負担が増し、誰かに頼らざるを得ないという心理状態に陥りやすくなります。
その結果、身近で支援してくれる介護職に対して、強い依存心を抱くようになるのです。
■2.介護職の「やってあげる」優しさに甘える
しかし、現場では時間的な制約や職員の善意から、「自分がやったほうが早い」「頼まれたら断れない」といった理由で、つい介助をしてしまう場面が多くあります。このような関わり方が続くと、利用者さんは「介護職が何でもしてくれる」と思い込むようになり、自分でやろうとする意欲が低下してしまうことがあります。
結果として、介護職に対する依存が強まり、自立支援の本来の目的が損なわれてしまう可能性もあるのです。
■3.不本意な施設入居からの反発
このような感情は、施設職員に対する態度にも影響を及ぼし、わがままな言動や過度な要求、依存的な振る舞いにつながることがあります。 本人にとっては、環境の変化に対する抵抗や不安の表れであり、自分の居場所を確保しようとする心理的な防衛反応とも言えるでしょう。
強い依存心がある利用者さんへの対応方法3つ
2.均一なサービスを提供する
3.適切な距離を保つ
■1.目的と手段を間違えないようにする
そのためには、誰が支援しても安心してサービスを受けられるよう、チーム全体で信頼関係を築くことが必要です。「この人じゃないとダメ」という状況を避けるためにも、目的と手段の整理を意識しましょう。
■2.均一なサービスを提供する
そのため、職員間での情報共有を徹底し、サービスの内容や質を均一に保つことが重要です。
誰が対応しても同じように安心できる環境をつくることで、依存を防ぎ、利用者さんの自立を促すことができます。
■3.適切な距離を保つ
特に、依存傾向が強い利用者さんに対しては、アセスメントをしっかり行い、専門職として関係性のバランスを意識することが大切です。
最後に:チーム全体で「依存」を見直し、より良い支援を目指しましょう

すでに依存が強まってしまった場合でも、立ち止まって「なぜこの方は私たちのサービスを利用しているのか?」という原点に立ち返ることが大切です。このような振り返りの場では、ケアマネジャーにも同席してもらいながら、ケアプランを再確認し、チーム全員で話し合う機会を持つことが、関係性の見直しと支援の質の向上につながります。
私たちが提供しているサービスが、利用者さんの目標達成に本当に役立っているかどうか。 その視点を常に持ち続けながら、利用者さんと一緒に、より良い未来を築いていくことが大切です。
■あわせて読みたい記事

ナースコールが頻回な利用者さんにどう対応する?対策4選をご紹介 | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/652[2025年2月26日更新]ナースコールが頻回な利用者さんへの対応方法としてコールを抜くのは最適なのか?この記事では、実際の事例を用いながらナースコールが頻回な利用者さんへの対応方法4選をご紹介します!【執筆者/専門家:脇 健仁・古畑 佑奈】
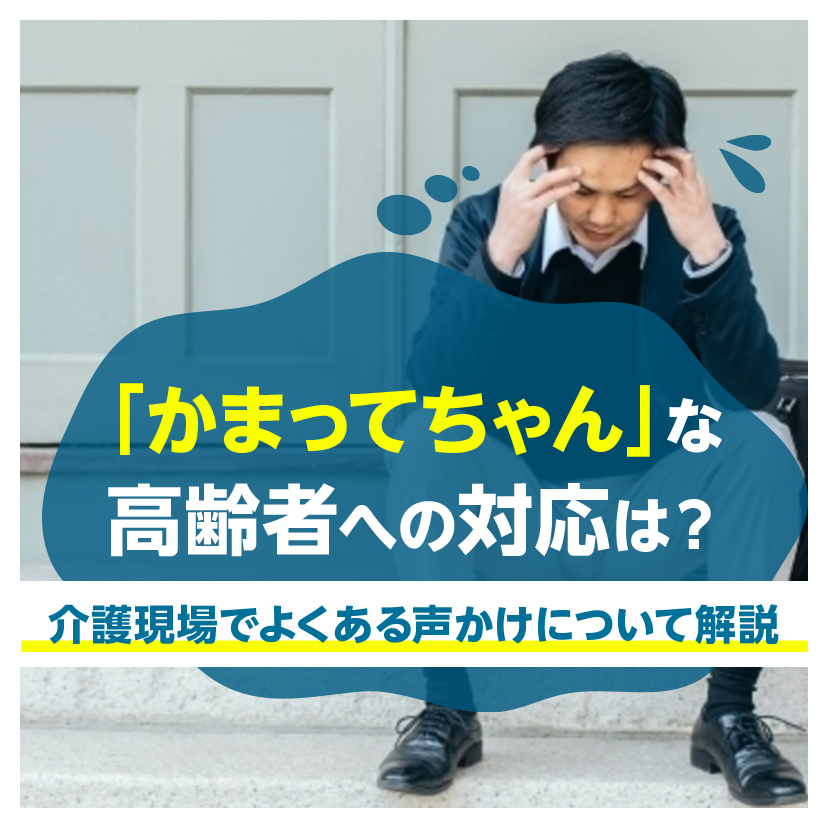
「かまってちゃん」な高齢者への対応は?介護現場でよくある声かけについて解説 | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/740[2025年2月25日更新]介護の現場にいると利用者から用件がないのに呼ばれたり、話しかけられたりしますよね。忙しい中での時間の割き方に悩む方も多いのでは?この記事では、そのような場面に遭遇した場合の対応方法について、ポイントを解説します!【執筆者/専門家:後藤 晴紀先生】







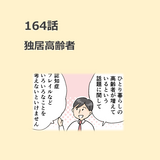
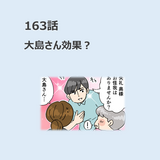







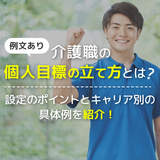












ゆりかごホールディングス株式会社 代表取締役
株式会社ゆりかご 代表取締役
茨城県訪問介護協議会 副会長
茨城県難病連絡協議会 委員
水戸在宅ケアネットワーク 世話人
茨城県介護支援専門員協会 水戸地区会幹事
茨城県訪問看護事業協議会 監事
水戸市地域包括支援センター運営協議会 委員
水戸市地域自立支援協議会全体会 委員
介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント
日本社会事業大学大学院 福祉マネジメント研究科修了(福祉マネジメント修士)
聖路加国際大学看護リカレント課程 認知症看護認定看護師課程 在籍中
介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・看護師・介護支援専門員・相談支援専門員・FP2級