死亡直前にみられる身体の変化として、最も適切なものを1つ選びなさい。
1.関節の強直
2.角膜の混濁
3.皮膚の死斑(しはん)
4.下顎呼吸の出現
5.筋肉の硬直
1.(×)関節の強直は、死後にみられる身体変化です。死後2時間ほどで、顎関節から現れます。
2.(×)角膜の混濁は、死後にみられる身体変化です。死後6時間ほどで出現し、1~2日で最も強くなります。
3.(×)皮膚の死斑は、死後にみられる身体変化です。死後20~30分で発生し、20時間以上経過すると固定されます。
4.(○)死亡直前には、血圧が低下し、胸郭を使った呼吸が下顎を使ったあえぐような呼吸(下顎呼吸)に変化して、呼吸回数も減少していきます。
5.(×)筋肉の硬直は、死後にみられる身体変化です。筋肉内で起こる化学反応により出現します。顎関節から出現して順次全身の筋肉に及び、死後20時間程度で最も強くなります。
高齢者の大腿骨頸部骨折(だいたいこつけいぶこっせつ)(femoral neck fracture)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1.転落によって生じることが最も多い。
2.骨折(fracture)の直後は無症状である。
3.リハビリテーションを早期に開始する。
4.保存的治療を行う。
5.予後は良好である。
1.(×)高齢者の大腿骨頸部骨折は、転落ではなく転倒によるものが最も多くなっています。
2.(×)骨折直後から疼痛が生じ、立位や歩行が困難となります。
3.(○)できるだけ術後早期からリハビリテーションを開始し、長期臥床による筋力低下、褥瘡、肺炎、認知症発症などを予防することが適切です。
4.(×)保存的治療に伴う長期臥床により、ロコモティブシンドローム(運動器障害による移動機能の低下)を引き起こして、寝たきりや要介護状態につながる可能性があります。
5.(×)高齢者の大腿骨頸部骨折では、術後も歩行に対する様々な介助が必要となるケースが多く、概して予後良好とはいえません。
抗ヒスタミン薬の睡眠への影響として、適切なものを1つ選びなさい。
1.就寝後、短時間で覚醒する。
2.夜間に十分睡眠をとっても、日中に強い眠気がある。
3.睡眠中に足が痛がゆくなる。
4.睡眠中に無呼吸が生じる。
5.夢の中の行動が、そのまま現実の行動として現れる。
2.夜間に十分睡眠をとっても、日中に強い眠気がある。
抗ヒスタミン薬は、アレルギー性疾患、感冒、乗り物酔い、睡眠障害などの治療薬として広く用いられています。
1.(×)抗ヒスタミン作用により脳の活動が抑制されるため、日中でも眠気が生じることがあります。ただし、就寝後短時間での覚醒は起こりにくいといえます。
2.(○)特に高齢者が抗ヒスタミン薬を服用する場合に注意が必要な副作用としては、過鎮静、眠気、ふらつきなどが挙げられます。
3.(×)体内のアレルギーを引き起こすヒスタミンの働きを抑制するため、皮膚のかゆみなどの症状を改善します。
4.(×)選択肢の内容は睡眠時無呼吸症候群の説明であり、抗ヒスタミン薬との直接的な関連性はありません。
5.(×)選択肢の内容はレム睡眠行動障害の説明であり、抗ヒスタミン薬との直接的な関連性はありません。
口腔内(こうくうない)・鼻腔内(びくうない)の喀痰吸引(かくたんきゅういん)に必要な物品の管理に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1.吸引チューブの保管方法のうち、乾燥法では、浸漬法(しんしほう)に比べて短時間で細菌が死滅する。
2.浸漬法で用いる消毒液は、72時間を目安に交換する。
3.吸引チューブの洗浄には、アルコール消毒液を用いる。
4.吸引チューブの洗浄水は、24時間を目安に交換する。
5.吸引物は、吸引びんの70~80%になる前に廃棄する。
5.吸引物は、吸引びんの70~80%になる前に廃棄する。
1.(×)乾燥法(乾燥させて保管する方法)よりも、浸漬法(消毒液に漬けて保管する方法)のほうが短時間で細菌が死滅します。
2.(×)浸漬法で用いる消毒液は、24時間を目安に交換することが推奨されています。
3.(×)チューブ外側は、清浄綿などを使って拭きます。内側は、口・鼻腔吸引用は水道水、気管内吸引用は滅菌水で洗浄します。
4.(×)吸引チューブの洗浄水は、8時間を目安に交換することが推奨されています。
5.(○)吸引の停止や故障を引き起こす原因となるため、吸引びんがいっぱいになる前に破棄します。
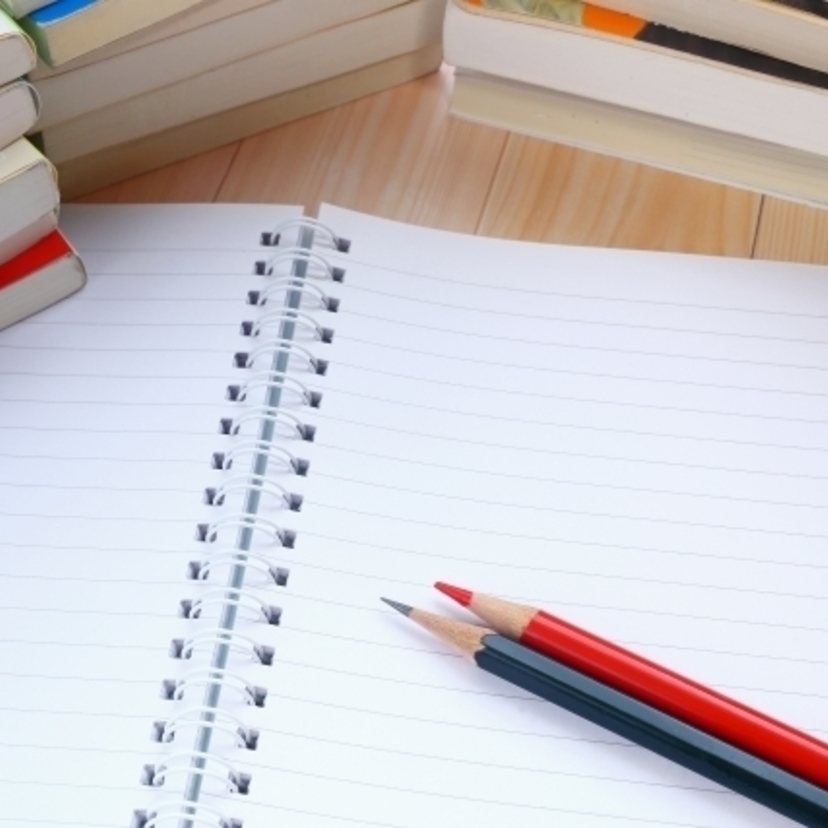



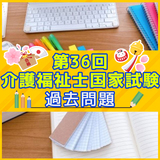
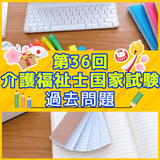
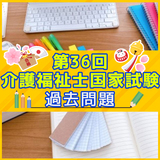







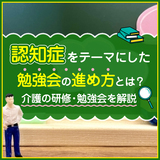













ささえるラボ編集部です。
福祉・介護の仕事にたずさわるみなさまに役立つ情報をお届けします!
「マイナビ福祉・介護のシゴト」が運営しています。