この記事のポイントまとめ♪
2.勉強会に参加する人=認知症に関して理解したいけど知識がないということ
3.認知症について正しい情報を話しましょう
4.何より利用者の気持ちを理解することが大切
認知症のことよりも、「利用者さんを知る」という方向性で勉強会を組み立てよう
■執筆者/専門家

・けあぷろかれっじ 代表 ・NPO法人JINZEM 監事 介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士 『介護福祉は究極のサービス業』 私たちは、障がいや疾患を持ちながらも、その身を委ねてくださっているご利用者やご家族の想いに対し、人生の総仕上げの瞬間に介入するという、責任と覚悟をもって向き合うことが必要だと感じています。 目の前のご利用者に『生ききって』頂く。 私たち介護職と出会ったことで、より良き人生の総仕上げを迎えて頂ける為のサポートをさせていただく事が、私たちに課せられた使命だと思っています。
・認知症ケアの勉強会ではどんなことを話しているのか?
この記事では、認知症ケアの勉強会を効果的に進めるためのポイントを紹介します。
勉強会で使用する事例の探し方
みなさんの施設でも、認知症の方の事例がたくさんあると思います。ぜひ、身近なところから事例を集めてみてください。
それでも事例がなかなか見つからないときは、認知症ケア学会からも「認知症ケア事例集」が発行されているので、それを参考にします。「認知症ケア 事例」等で検索すると、様々な事例が見つかると思いますよ。
6段階で解説!認知症の勉強会の流れ

■1.認知症とは?認知症の定義
※出典:法令検索 共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)
ここでいう政令とは、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令」のことを指しており、その他の疾患にせん妄やうつ病など厚労省が精神疾患として定めているものは、含まれない旨が明記されています。※
※参照:厚生労働省 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令
■2.認知症の診断
A.以下の 2 項目からなる認知障害が認められること
1.記憶障害(新しい情報を学習したり、かつて学習した情報を想起したりする能力の障害)
2.以下のうち 1 つあるいは複数の認知障害が認められること
(a)失語(言語障害)
(b)失行(運動機能は損なわれていないにもかかわらず、動作を遂行することができない)
(c)失認(感覚機能は損なわれていないにもかかわらず、対象を認識あるいは同定することができない)
(d)実行機能(計画を立てる、組織立てる、順序立てる、抽象化する)の障害
B.上記のA1、A2の記憶障害、認知障害により社会生活上あるいは職業上あきらかに支障をきたしており、以前の水準から著しく低下していること
C.上記の記憶障害、認知障害はせん妄の経過中のみに起こるものではないこと
※出典:厚生労働省 認知症と軽度認知機能障害と軽度認知機能障害について
■3.認知症の症状(中核症状・行動心理症状)
認知症の症状は「中核症状」と「行動心理症状(BPSD)」に分けられます。中核症状は脳の障害によって誰にでも現れるもので、記憶障害、見当識障害、判断力や理解力の低下などが含まれます。
一方、BPSDは中核症状に本人の性格や環境が影響して現れるもので、徘徊、妄想、幻覚、暴言、介護拒否、不安、抑うつなど多様です。BPSDは適切なケアや環境調整で軽減が可能です。
また、これらの症状がある場合に気をつけていただきたいことも紹介します。
→認知症だから暴力行為がある・認知症だから拒否があるなどと考えないため
・介護職員の対応が不適切だったかもしれない、関わり方が不十分だったかもしれないという視点で向き合う
・認知症としてではなく、1人の利用者さんという人間として捉える
■4.大脳の機能と働き
まずは、脳の部位ごとに機能を説明し、障害される場所によって様々な症状が出現することを説明します。説明した方がよい部位は以下の通りです。
・頭頂葉
・後頭葉
・側頭葉
・海馬
大脳の働きは、「見て・認識して・記憶から引き出し・再認識し・計画を立てて・行動に移す」ことです。勉強会では、そのプロセスを説明します。
例えば、失認の中核症状は、このプロセスの中で間違った記憶から引き出された情報によって行動してしまうことが原因で、異食等の行動心理症状に繋がります。
ティッシュを見て、キャベツとして記憶から引き出されてしまうことで、口に入れてしまう「異食」に繋がるのです。

■5.認知症の種類と特徴を理解する
勉強会では、その種類と特徴を伝えていきます。
■アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症と診断されると、進行を予防するための薬が処方されます。現在、保険適用されているアルツハイマー薬は4種類あり、その他に漢方薬なども使われています。これらの薬にはそれぞれ特徴があり、患者さんの症状や状態に応じて使い分けることで効果を発揮しています。
しかし、「アルツハイマー薬はどれも同じ」と誤解している方も多くいらっしゃいます。実際には、アルツハイマー薬は進行を抑えるだけでなく、神経細胞の働きを活発にし、症状を改善する効果もあります。そのため、症状に合わせた適切な処方がとても重要です。
適切な薬剤が処方されるようにするためには、利用者さんの様子や状態を看護職員と共有し、医療従事者に正確な情報を伝えることが大切です。これにより、利用者さんが苦しまないような薬剤の選択が可能となり、より良いケアにつながります。
■レビー小体型認知症
また、転びやすくなったり、手が震えたり、動きが緩慢になるといった「パーキンソン病」のような症状が同時に現れるのも特徴です。
■血管性認知症
一般的には、60歳以上の男性に多く見られる傾向があり、糖尿病や高血圧などの生活習慣病があると、発症リスクが高まるとされています。
脳内では、損傷を受けている部位と受けていない部位が混在しているため、能力が部分的に低下することがあります。また、損傷を受けた部位によって現れる症状が異なるため、個人差が大きくなるのも特徴です。
■前頭側頭型認知症
発症は比較的若い世代(40〜60代)に多く、初期には物忘れが少ないため、精神疾患と誤診されることもあります。本人が病気であると認識しない、認めない場合もあり、周囲が気づいても受診を拒むケースもあります。
食習慣の変化や、社会的ルールを無視した行動(万引きなど)が見られることもあり、本人に罪悪感がない場合もあります。症状には個人差があり、進行すると寝たきりになることもあります。
■6.利用者さんの気持ちを考える
自分の異変に気づいている利用者さんは、不安で、怖くて、悲しい気持ちでいっぱいです。行動の一つひとつには、そうした気持ちが隠れています。その気持ちを理解し、利用者さんに「ありがとう」を伝えられる環境を整え、たくさんの感謝を伝えていくことが大切です。
まとめ:全体を把握したら、それぞれ深堀りをしていきましょう!
重要なのは、参加者が「参加してよかった」「何か一つでも学びがあった」と感じられることです。そのためには、参加者が本当に知りたいことは何かを考えることが不可欠です。全体像を説明したら、それぞれを深掘りする機会があってもよいかもしれません。
ぜひ一度、ご自身が現場で働き始めた頃の気持ちを思い出してみてください。初心に立ち返ることで、参加者の視点に寄り添った内容を提供できるようになります。
■あわせて読みたい記事

認知症の方とのコミュニケーション方法とは?よくある事例と対応方法を解説します! | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/438[2025年4月15日更新]認知症の方は脳の認知機能が低下しているため、コミュニケーションをとることが難しい場合があります。しかし、傾聴や受容の姿勢を持つことで、コミュニケーションを行うことができます。この記事では、認知症の方とのコミュニケーション方法や、事例別の対応方法を紹介します!【コラム執筆者/専門家:古畑佑奈】
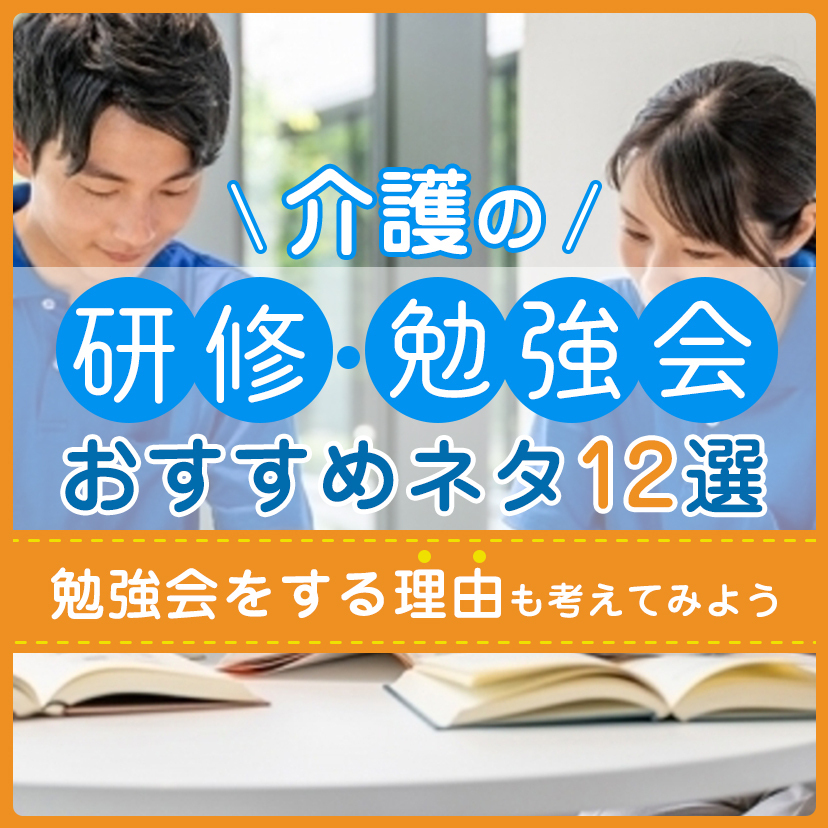
【介護の研修・勉強会】おすすめネタ12選!勉強会をする理由も考えてみよう | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/801[2024年11月更新]介護施設で行う勉強会や研修のおすすめテーマを紹介します!研修テーマを考えるときは「何の研修をしようか?」ではなく、「なぜ研修をするのか?」を考えてみると、よい研修テーマ決めが行えます!ぜひ、思考のチェンジをしてみましょう。【執筆者:専門家/大庭 欣二・伊藤 浩一】

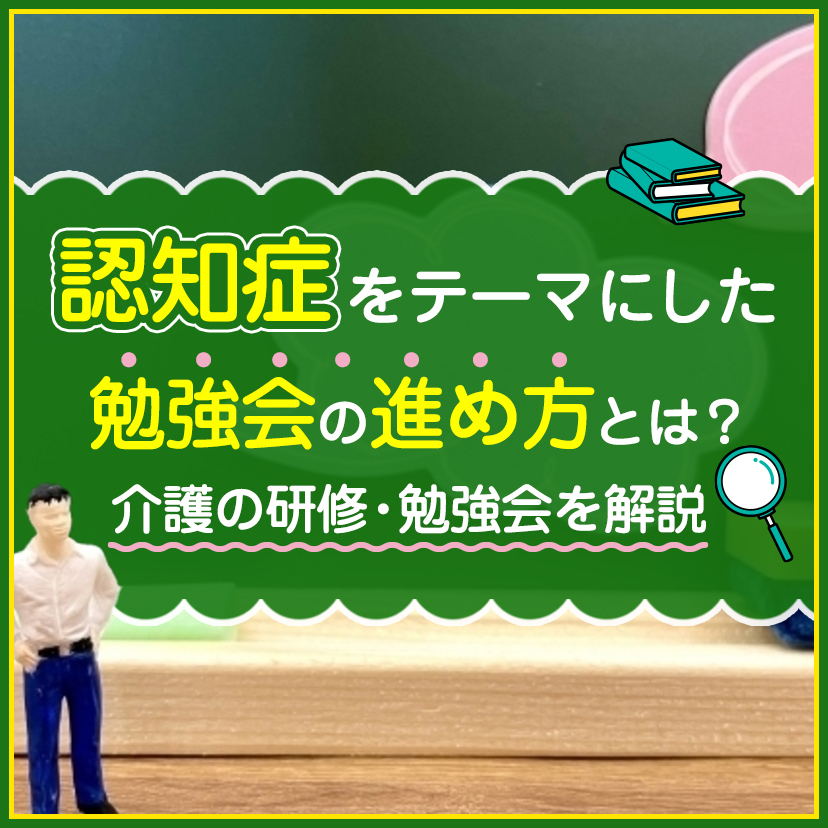















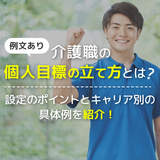













・けあぷろかれっじ 代表
・NPO法人JINZEM 監事
介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士