本日のお悩み1:医師からコールを抜いてよいとの指示…でも罪悪感でいっぱい
しかし、コールを抜くことは介護職として虐待をしているような罪悪感あります。有料老人ホームで働く介護職の対応としてこの対応は正しいのでしょうか?どのように解決したらよいでしょうか。
ナースコールが頻回な原因とは?自分に置き換えて考えてみましょう
■執筆者/専門家

ゆりかごホールディングス株式会社 代表取締役 株式会社ゆりかご 代表取締役 茨城県訪問介護協議会 副会長 茨城県難病連絡協議会 委員 水戸在宅ケアネットワーク 世話人 介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・看護師・介護支援専門員・相談支援専門員
精神疾患のある利用者さんの頻回にわたるコールについては、苦労されているところも多いかと思います。
ご質問者さんは、きちんと専門職である医師に確認をとっているということ、その対応は素晴らしいと思います。
■まずはコールを抜くことに違和感を持てたことが大切
いくら医師が良いといっても、ご質問いただいた方のおっしゃる通り、罪悪感やちょっとそれってどうなんだろうという違和感を持てることが、とても大切ではないかと思います。
■利用者さんはなぜコールをする?自分に置き換えて考えてみよう
例えば飲食店に行った際に注文を伝えようとしたとき、私たちは店員を直接呼ぶ、もしくはコールを押して店員を呼ぶことが多いと思います。 おなかが空いていて、注文が決まったのに、店員さんが全然注文を取りに来てくれないとどんな気持ちになるでしょうか?
このように、コールが多いとただ決めつけるのではなく、相手の状況を自分に置きかえてみると、利用者さんの心情を理解することができるでしょう。
●コールは自分の意志表示をするもの
そのような状況を本人が了解するでしょうか?そもそも、この件に本人が了承できるのであれば、何度もコールはしないと思います。
●家族は施設に遠慮している可能性も
施設からこの内容について連絡を受けた家族は、自分の家族が施設に迷惑をかけてしまっていると感じるでしょう。もしかしたら、施設で受け入れてもらえなくなるかもしれない、または本人にとって不利益なことが起こるかもしれないと感じてしまい、本心では納得がいかないが、仕方なく了承するというようなことになる可能性があると感じます。
■利用者さんのナースコールが頻回な場合に施設でできること
2.コールのあった時間帯、曜日などを分析する
3.コール前後での出来事について情報収集を行う
4.コールの対応方法について、情報共有する
●1.コールの内容を精査する
●2.コールのあった時間帯、曜日などを分析する
●3.コール前後での出来事について情報収集を行う
これによって、コールをするまでの状況が明らかになり、その状況への対応策を行うことでコール回数が抑制されると考えます。
●4.コールの対応方法について、情報共有する
受けた側の対応によっては、次のコールを発生させてしまう可能性もあります。本人がコールをした目的をしっかりと汲み取ったうえで、どのような対応をおこなったのか、その対応が適切だったのかをチームで共有し、検討していく必要があります。
■「コールを抜く」以外の対応を検討して
折り合いをつけるという妥協はすべきではなく、ご自身が感じている罪悪感に素直に向き合い、コールを抜く以外の方法を再考いただきたいと考えます。
本日のお悩み2:耐えきれなくてナースコールを抜いてしまった…私は介護士失格?
これって犯罪でしょうか。またこのようなことでイライラしてしまう私は、介護職に向いていないのでしょうか。
ナースコールが頻回になった要因を分析し、状況に応じた対応を具体的に考えましょう
■執筆者/専門家
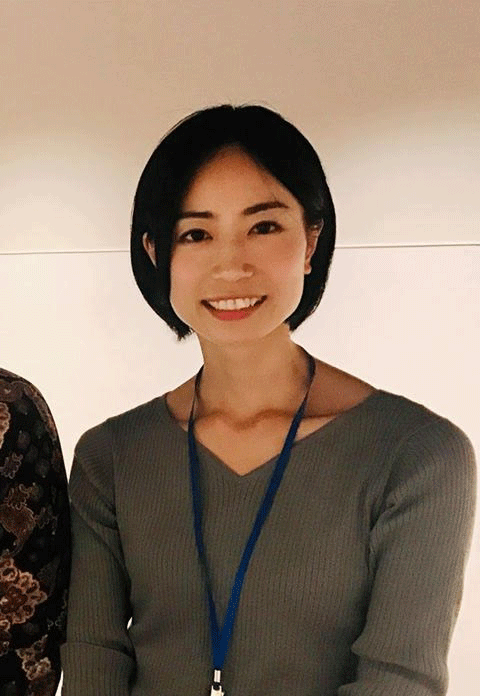
社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員 特別養護ホーム生活相談員、訪問介護事業、地域包括支援センターにて介護支援専門員の経験あり。 現在は、デイサービス管理者として勤務。 地域でのネットワーク活動では事務局として「死について語る会」や「3大宗教シンポジウム」など幅広いテーマの勉強会やイベントを企画・運営の経験がある。 すきな食べ物はラーメン。
■ナースコールを抜くことは虐待にあたるか?
高齢者虐待防止法では、「必要な用具の使用を限定し、高齢者の要望や行動を制限させる行為」を虐待と定義しています。 そして、その具体的な内容として「ナースコール等を使用させない、手の届かないところに置く」と挙げられています。
このことから、ナースコールを抜くという行為は、虐待に該当するとわかりますね。
■やってしまったことは反省し、繰り返さないようにする
いずれにしても、自分の行為に疑問を感じ、質問をくださったあなたは、真面目な方なのだと思います。私たち介護職には、何よりもまず、サービスを利用されている方々の権利を守る責任があります。 してしまったことについては、反省をして、振り返り、何よりこれから同じことを繰り返さないということが重要です。
■なぜナースコールを抜いてしまったのか?対応策も考えましょう
おそらく理由は1つではなく、さまざま考えられると思います。できれば、1人ではなく職場の方と相談し、時間を取って振り返り、対応策を考えてみましょう。
対応策は可能な限り、具体的に検討する必要があります。「こういう状況になったらこうする」と具体的な行動を決めておくと、考える余裕がないときでも、迅速かつ適切な対応をおこなうことができます。
また、誰しも仕事以外のことで気持ちに余裕がないときもあります。そのようなときは無理をせず、自分を労わることも大切にしてくださいね。
利用者さんのナースコールが頻回になる理由
次に、利用者さんはなぜナースコールを頻繁に押してしまうのか、またそのような場面に遭遇した場合、どのような対応が適切であるのかを紹介します。
■1.介助を求めている
利用者さんの中には、介助がないとトイレに行くことができなかったり、病気や服薬の影響で頻尿になっていたりする場合もあります。これらのサインを見落としてしまうと、膀胱炎などといった病気の原因に繋がる可能性があります。
「またか」と思う気持ちもわかりますが、利用者さんの様子は必ず確認し、重要なサインを見落とさないようにしましょう。
■2.孤独や不安感を抱えている
職員とのコミュニケーション不足は悪循環に繋がる可能性があるため、一方的に断ち切ることはせず、相手が背景に抱える事情などを探るようにしましょう。
■3.ナースコールを押しても応答がなかった
忙しい介護現場では、利用者さんの状況などに応じて優先順位をつけて対応をおこないます。しかし、待たされている利用者さんにとっては、待機時間が長く感じ、「他の利用者さんは対応してもらているのに自分は後回しにされている」と感じてしまいます。その結果、ナースコールが頻回になってしまうことがあるでしょう。
ナースコールが頻回な利用者への対応方法4選

2.行動パターンの把握と分析
3.見守り体制の強化
4.感情のコントロール
■1.利用者さんへの関心と温かい対応
たとえば、利用者さんのお話に対して「なんでそう思ったのですか?」「そのあとどうなったのですか?」など5W1Hを用いながら話を聞くと、利用者さんは関心を持って聞いてくれていると感じるようになります。
また、忙しく、すべてに対応することが難しい場合は、温かい笑顔で接するだけでも利用者さんに安心感を与えることができます。
■2.行動パターンの把握と分析
■3.見守り体制の強化
また、施設全体で見守り体制を作っておけると、様子がわからないからとりあえず駆けつけなければならないといった状態をなくすことができ、職員の負担も軽減できます。
まとめ:介護の仕事は自身の人間性と向き合う仕事
しかし、利用者さんにとっては一人ひとり、何かしらの理由があって、時に必死に、時に遠慮しながら押しているということ、そして究極的にはナースコールが鳴る前に声がかけられることを目指すのが私たちの仕事であるということを、最後にお伝えしたいと思います。
介護の仕事は、自身の人間性と向き合わなくてはならない仕事ですが、自分が完璧な人間ではないと理解するからこそ、他者にも寛容になれるのではないかとも思います。どうか、今回の出来事を自分だけの課題として抱え込まず、さまざまな角度から考えてみてください。応援しています。
■あわせて読みたい記事

介護職が利用者さんに依存されてしまったときは?対応策を3つご紹介します! | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/435介護職が利用者さんに依存されてしまったときの対応を、専門家の実体験を交えて解説します。先輩がその考えに至った「原因」「しくみ」に目を向けてみましょう【脇 健仁 大関 美里】

「羞恥心に配慮した声掛け」とは?声掛けの方法や考え方を解説 | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/543[2025年1月28日更新]恥ずかしいと思うことは人によって違います。介護の仕事は「すべてがプライバシーに触れる」と理解したうえで、羞恥心に配慮した声かけのポイントを紹介します!【執筆者/専門家:古畑 佑奈】







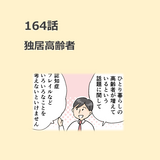
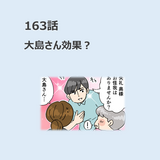







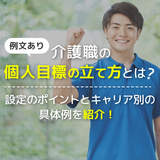












ゆりかごホールディングス株式会社 代表取締役
株式会社ゆりかご 代表取締役
茨城県訪問介護協議会 副会長
茨城県難病連絡協議会 委員
水戸在宅ケアネットワーク 世話人
茨城県介護支援専門員協会 水戸地区会幹事
茨城県訪問看護事業協議会 監事
水戸市地域包括支援センター運営協議会 委員
水戸市地域自立支援協議会全体会 委員
介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント
日本社会事業大学大学院 福祉マネジメント研究科修了(福祉マネジメント修士)
聖路加国際大学看護リカレント課程 認知症看護認定看護師課程 在籍中
介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・看護師・介護支援専門員・相談支援専門員・FP2級