本日のお悩み:かまってちゃんな高齢者への対応方法は?
ナースコールの頻度が高い、他の利用者さんとの会話を妨害してくるなど、いわゆる「かまってちゃん」な高齢者への対応に悩んでいます。
日々の業務の中でどの程度対応を行えばよいのかわからず、他の業務とのバランスに悩んでいます。対応方法を教えてください。
利用者さんの困りごとや不安をアセスメントしなおしてみましょう!
■執筆者/専門家

・けあぷろかれっじ 代表 ・NPO法人JINZEM 監事 介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士 『介護福祉は究極のサービス業』 私たちは、障がいや疾患を持ちながらも、その身を委ねてくださっているご利用者やご家族の想いに対し、人生の総仕上げの瞬間に介入するという、責任と覚悟をもって向き合うことが必要だと感じています。 目の前のご利用者に『生ききって』頂く。 私たち介護職と出会ったことで、より良き人生の総仕上げを迎えて頂ける為のサポートをさせていただく事が、私たちに課せられた使命だと思っています。
・依存心が強い
・ナースコールの頻度が多い
・いつも職員を頼ってしまう
そんな利用者さんについては、多くの介護職員が悩んでいるかもしれません。 特に他にやるべき業務があるときは、コールや話しかけてくる頻度が多い利用者さんの対応に困りますよね。
実は介護職員の皆様が悩まれているのと同じように、利用者さん側にも悩みがあったうえでその行動をとっているのです。
■まずは丁寧に再アセスメントを!
そのご利用者さんのアセスメントをもう一度丁寧におこなってみましょう!
その際、特に大切なのは『ご本人の困りごとや、不安の解消をする』という視点を持っておくことです。
なぜなら、そのご利用者様が必要とするケアの量によって、必要な関わりの時間の長さも違ってくるからです。
かまってちゃんな高齢者の原因と特徴
2.孤独を感じている
3.注目されたい気持ちが強い
4.他者の感情を察することが苦手
■1.病気(認知症など)が隠れている
これらの背景には、うつ病や認知症などといった病気が関連している可能性もあるため、最近いつもと様子が異なると感じた場合には、しっかりと記録を残し、周囲の職員や専門職などに相談をするようにしましょう。
■2.孤独を感じている
長年慣れ親しんだ環境ではなくなることで、不安感や孤独感を感じる利用者さんも多くいます。また、今まで当たり前にできていたことが老化が原因でできなくなっていくことなども重なると、職員に対して自分の存在意義や居場所を求めるため、かまってちゃんな行動に繋がります。
■3.注目されたい気持ちが強い
施設での生活と、働いていた頃の自分とを比較し、「周囲に認められたい」「もっと気にかけてほしい」といった気持ちが強くなることがあります。この場合、昔の話を自慢げに何度も話したり、内容を大きくして話したりすることが多いでしょう。
■4.他者の感情を察することが苦手
この場合、自分が話している時間が長く、職員が困っているなどといったことには気づくことができません。ただし、むやみに突き放してしまうと、先述した感情を強めてしまう要因となるため、適度な距離を保つことが大切です。
かまってちゃんな高齢者への対応方法と注意点
ここからは、かまってちゃんな高齢者の対応方法や注意点を紹介します。
2.他者との交流機会を増やし、役割を与える
3.施設一丸となって対応方法を個々に検討・共有する
4.家族と共に対応策を検討する
■1.相手を否定せず話を聞く
しかし、職員側が感情的な対応をしてしまうと、利用者さんの気持ちもヒートアップしてしまう可能性があります。そのようになってしまうと、関係性がこじれたり、カスタマーハラスメントに繋がったりとさまざまなリスクがあります。
しつこいと感じても、優しい言葉で接することや、寄り添いの気持ちを持つことを忘れないようにしましょう。
■2.他者との交流機会を増やし、役割を与える
このような利用者さんに自信を持ってもらうためには、ボランティア活動や、地域のイベントへの参加、施設においてお手伝いをしてもらうなどを通じて、役割を与えることが大切です。社会で自分は役に立てていると感じることができると、自己肯定感を高めることができ、かまってちゃんが少し落ち着く場合もあります。
■3.施設一丸となって対応方法を個々に検討・共有する
サービス担当者会議やケース会議で、「この議題で話し合いたい」と自ら申し出ても良いと思います。 質問者さんと同じ気持ちを持っている職員もいらっしゃると思いますし、もしかしたら話し合うなかで、利用者さんの精神的不安が大きくなるような対応をしていたことが見つかるかもしれません。
その際に、共通の対応方法を考えるのではなく、利用者さん一人ひとりの背景事情と向き合い、個々に対応方法を検討するようにしましょう。利用者さん一人ひとり、必要なケアの量は異なります。その人に必要なケア、必要な時間を考えましょう。
■4.家族と共に対応策を検討する
家族に介護施設での様子を伝え、コミュニケーションの取り方や施設での過ごし方を決めていきましょう。
ナースコールが多い利用者さんには、どう対応する?
その不安が解消されると、「不安なことが少ない状態=ナースコールを押さなくても安心できる状態」になるでしょう。 その安心感が、徐々に利用者さん本人の状態の変化として現れてきます。
利用者さんとしっかり向き合って解決する課題だからこそ、これを解決するのは介護職員の腕の見せ所ですね。
■「できることは利用者さんご自身で」という声かけの盲点
その議論の中で、「できることはご本人にやっていただこう」という話題になり
その対応として、「できることは自分で行いましょうね」と声掛けをする。という解決策が出たとするならば、注意が必要です。
なぜなら、誰かを頼りたいときに、声をかけた人から「自分でやって:という言葉を返されると不安になったり寂しくなったりしますよね。
その精神的な不安は、そのあとの利用者さんの精神状態を悪化させてしまう可能性もあります。
そのため、言葉がけを行う際には以下の点に注意するようにしましょう。
・職員の声色
・利用者様の表情
・利用者様の体調
・対応者と利用者様の信頼関係
これらを忘れて、画一的な言葉掛けを行うことは、利用者さんを傷つけてしまう可能性があります。声かけの際には、注意するようにしましょう。
最後に:視点を変えて利用者さんの対応をしてみましょう
利用者さんも不安や悩みを多く抱えています。かまってちゃんではなくその不安を取り除きたいという気持ちで声をかけてきているのではないでしょうか。
そのため、どの程度利用者さんの要望に付き合うのか?という視点ではなく、「利用者さんの不安や困りごとを解決するためには?」という視点で議論をしたり対応をしてみたりしてください。
■あわせて読みたい記事
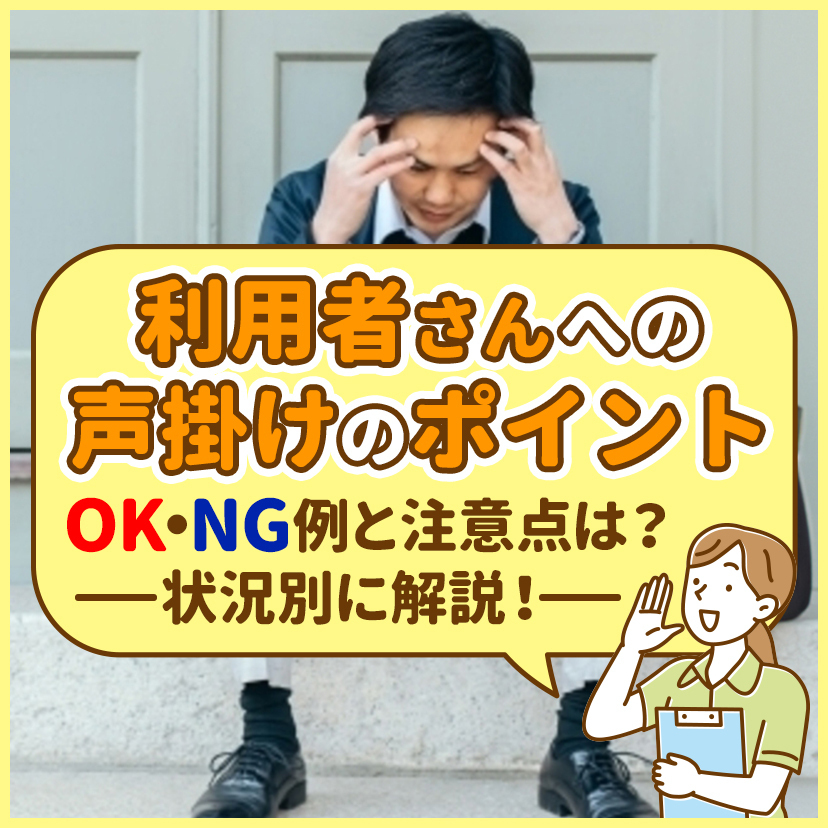
利用者さんへの声掛けのポイント|OK・NG例と注意点は?状況別に解説! | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/415[2024年9月更新] 利用者さんとのコミュニケーション。比較的得意であると感じている方でも、一度は苦戦したことがあるのではないでしょうか。この記事では、コミュニケーションの基本から、利用者さんの状況別対応方法まで詳しく解説します!【回答者/専門家:古畑 佑奈】

「羞恥心に配慮した声掛け」とは?声掛けの方法や考え方を解説 | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/543[2025年1月28日更新]恥ずかしいと思うことは人によって違います。介護の仕事は「すべてがプライバシーに触れる」と理解したうえで、羞恥心に配慮した声かけのポイントを紹介します!【執筆者/専門家:古畑 佑奈】

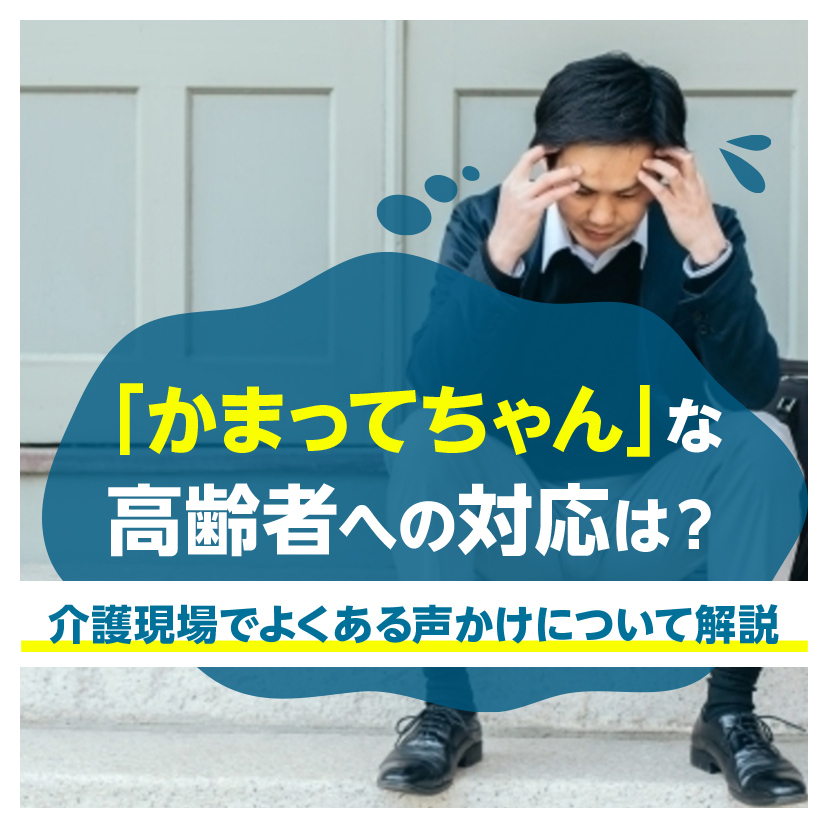





























・けあぷろかれっじ 代表
・NPO法人JINZEM 監事
介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士