軽度認知障害(mild cognitive impairment)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1.本人や家族から記憶低下の訴えがあることが多い。
2.診断された人の約半数がその後1年の間に認知症(dementia)になる。
3.CDR(Clinical Dementia Rating)のスコアが2である。
4.日常生活能力が低下している。
5.治療には、主に抗認知症薬が用いられる。
1.本人や家族から記憶低下の訴えがあることが多い。
1.(○)軽度認知障害は、認知機能障害が一部に認められるものの、日常生活動作は自立している状態です。認知症が進行すると記憶低下の自覚はなくなりますが、軽度認知障害の段階ではもの忘れなどの自覚があり、多くは本人や家族から記憶低下の訴えがあります。
2.(×)診断された人のうち、5~15%の人がその後1年間で認知症に移行するといわれています。
3.(×)CDRは認知症の重症度を評価する指標の一つであり、0(健常者)~3(重度認知症)で点数化します。軽度認知障害のスコアは0.5となります。
4.(×)全般的な認知機能は正常範囲内であり、日常生活能力の低下はみられませんが、年齢だけでは説明のつかない記憶障害が存在します。
5.(×)抗認知症薬の効果は否定的であり、保険適用の薬物療法はありません。運動療法、脳トレ-ニング、生活習慣の見直しなどの非薬物療法が行われます。
若年性認知症(dementia with early onset)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1.75歳未満に発症する認知症(dementia)である。
2.高齢者の認知症よりも進行は緩やかである。
3.早期発見・早期対応しやすい。
4.原因で最も多いのはレビー小体型認知症(dementia with Lewy bodies)である。
5.不安や抑うつを伴うことが多い。
1.(×)若年性認知症は、65歳未満で発症した認知症の総称です。
2.(×)高齢者の認知症より進行スピードが速いことが、若年性認知症の特徴の一つです。
3.(×)現役世代での発症であり、症状が現れてもうつ病やストレス障害、更年期障害などが疑われるケースが多く、早期発見は困難だといえます。
4.(×)若年性認知症の原因で最も多いのは、約半数を占めるアルツハイマー型認知症であり、次いで血管性認知症、前頭側頭型認知症となっています。
5.(○)現役世代での発症となることから、仕事や育児に関する不安、抑うつを伴うことが多いとされています。
軽度の認知症(dementia)の人に、日付、季節、天気、場所などの情報をふだんの会話の中で伝えて認識してもらう認知症ケアとして、正しいものを1つ選びなさい。
1.ライフレビュー(life review)
2.リアリティ・オリエンテーション(reality orientation)
3.バリデーション(validation)
4.アクティビティ・ケア(activity care)
5.タッチング(touching)
2.リアリティ・オリエンテーション(reality orientation)
1.(×)ライフレビューは、これまでの自分の人生を回想し、評価や総括を行う活動です。他者が質問することでサポートを行う場合もあります。
2.(○)リアリティ・オリエンテーションは、日付、季節、天気、今いる場所、家族の名前などを、日常の会話に入れて伝えることで認識してもらう療法であり、見当識障害に対する認知症ケアの一つです。
3.(×)バリデーションは、認知症患者の言動に共感し、受け入れることによりコミュニケーションを取る方法です。
4.(×)アクティビティ・ケアでは、芸術文化活動、体操、散歩などにより、日々の充実をめざします。
5.(×)タッチングとは、直接手で触れる、さする、揉むなどして、安心感を与える非言語的コミュニケーションの一つです。
Cさん(80歳、女性)は夫(85歳)と二人暮らしである。1年ほど前から記憶障害があり、最近、アルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimerʼs type)と診断された。探し物が増え、財布や保険証を見つけられないと、「泥棒が入った、警察に連絡して」と訴えるようになった。「泥棒なんて入っていない」と警察を呼ばずにいると、Cさんがますます興奮するので、夫は対応に困っている。
夫から相談を受けた介護福祉職の助言として、最も適切なものを1つ選びなさい。
1.「主治医に興奮を抑える薬の相談をしてみてはどうですか」
2.「施設入所を検討してはどうですか」
3.「Cさんと一緒に探してみてはどうですか」
4.「Cさんの希望通り、警察に通報してはどうですか」
5.「Cさんに認知症(dementia)であることを説明してはどうですか」
1.(×)興奮を抑える目的で抗精神病薬などが処方されることもありますが、BPSD(認知症の行動・心理症状)においては、関わり方を変えることで症状が軽減されるケースが多くみられます。
2.(×)Cさんの夫が相談したいのは「興奮するCさんへの対応」であるため、在宅における対応方法を助言するべきです。
3.(○)もの盗られ妄想がみられるため、Cさんの言動を否定せずに一緒に探してみることで、不安や混乱を軽減できると考えられます。
4.(×)もの盗られ妄想による発言であり、警察に通報しても問題解決にはつながりません。
5.(×)興奮している状態のCさんに認知症であると伝えても、理解できずに混乱をきたすばかりです。




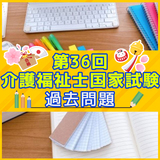
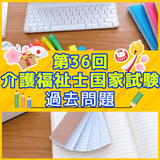
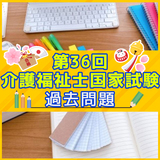







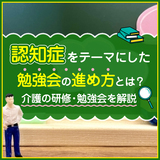













ささえるラボ編集部です。
福祉・介護の仕事にたずさわるみなさまに役立つ情報をお届けします!
「マイナビ福祉・介護のシゴト」が運営しています。