介護職と看護職の間でトラブルが起こる原因と、解決策3つ
回答者

介護という仕事は多職種が連携しあうことにより、仕事の質が上がり、利用者さんの満足度もより高まると思います。ですから、介護職と看護職も、出来たらトラブルがなく、お互いに仕事を認め合える関係ができれば、チームとしてしっかりと機能していくと思います。
では、具体的にどのようなことが原因でトラブルが発生し、どのような対処法があるかを考えていきましょう。
私は大きく分けると、3つの要因に分類できるのではと思います。
もちろん、それぞれの職種の個人的な素養が原因である場合もありますが、ここでは、職種特有の要因に触れてまいります。
■原因① 過去の歴史や事業形態からくるもの
医療法人系の事業所などでみられるケースです。「医療現場における職のヒエラルキー」が要因となります。
「ヒエラルキー」とは、簡単に言うとピラミッド型の「階層」「階級制」を意味する言葉です。
医療現場でいうと、医師を頂点に、薬剤師や看護師、臨床心理士といった医療専門職が続き、介護職はその次。先にも紹介しましたが、介護職は過去に「看護助手」「補助看さん」などと呼ばれ、看護師の補助職のような仕事の位置づけであった時代もあり、いまだにその名残がある事業所もないとは言えません。
すると、介護職を下に見てしまう看護職のような構図ができ、看護職からの指示が命令のように感じたり、看護職が雑用を押し付けたりということもあるようです。
そこに反発する介護職とのトラブルが多発し、不満を持つ介護職の離職などに繋がります。
解決策
ズバリ、その文化の解消しかないと思います。
つまり、経営トップが、職員の声にしっかりと耳を傾け、方針を打ち出し、多職種間に尊厳を持ち合う仕組みづくりをし、環境を改善することです。
■原因② 看護職と介護職の「職」としての就き方の違いからくるもの
極端な表現をすると、「看護」を、学生時代からしっかり学び、仕事への「誇り」や「責任感」を高く持たれ、「命」や「危険」に対する意識を叩き込まれている「看護職」。ともすれば、他業界から転職をしてきた「無資格」「未経験」の介護職。(もちろん、そうでない方も多くいらっしゃいます。)
仕事に対する意識や知識の違いが大きく異なるケースも少なくありません。
とりわけ、「与薬」や「栄養摂取」、「事故防止」「感染予防」などでは、違いが顕著に表れます。
看護職は「なんでこんなことも分からないの」と嘆き、介護職は「教えてもらったことがないから」と諦めるといった構図もあるようです。
解決策
ここで大切なのは、「業務上、必要な情報の共有方法の確立」です。
医療の観点から、少なくとも、これだけは守ってほしい、知っていてほしいというものは、マニュアル化し、丁寧な研修を重ね、業務に落とし込むことです。医療に詳しくない方でも理解できるやり方を組織として確立しましょう。
■原因③ 看護職と介護職の特性の違いからくるもの
医療からのアプローチをする看護職と、生活からのアプローチをする介護職という違いから生じるトラブルです。
考え方の相違は、看取りや食形態、リハビリテーション、外出レクリエーションや事業所内行事など、さまざまな場面で生じます。それは、職業特性の違いから来るものも多くあります。
食形態を例にとると、リスクをなるべく回避し、しっかりと栄養が取れる状態を作ろうとする看護職、好きなものはなるべく自由に食べさせたい介護職。家族の差し入れに対し、衛生面や栄養面でのリスクを考え断ろうとする看護職、笑顔で受け取り、利用者に喜んでもらおうとする介護職。(もちろん、そうでない方も多くいらっしゃいます。)
極端な例ですが、このようなケースは多くの職場で起こっているようです。
解決策
やはりお互いの視点に立った考え方を意識したうえで、職場でのルールを定めることですね。
その際に互いの考え方を尊重しながら、決して押しつけにしないこと。施設の理念に立ち返ることを忘れずに。
■大切なのは、お互いの視点に立つこと
以上、3つの要因からくる事例をあげさせていただきましたが、いずれのケースも、互いの視点に立って、考えをすり合わせることが大切です。それを意識するだけで、そこに共感が生まれ、多くのことが解決していくと思います。
看護職と介護職だけでなく、すべての職種同士に当てはまるので、是非ともチャレンジしてみてください。
介護職と看護師のトラブルに関連したお悩み
施設にいる看護師が介護職をあきらかに見下していて、偉そうで気分が悪いです。
なぜこうなってしまうのでしょうか?
どこの職場でも同じような話を聞きます。
「チーム」という意識の浸透を進めてはいかがでしょうか
介護職と看護職の間のトラブルは、多くの事業所で、様々な場面で見受けられますね。
と申しますか、成熟しきれていない介護の現場ではいまだに散見されているようですが、しっかりと多職種連携が機能し、チームケアを実践できている現場では、そのようなことはほとんどないようです。
■職種の違いは、役割の違い
そもそも、筆者は職種により「偉い」とか「上」や「下」などは、存在しえないと考えます。
見下しているその看護師さんは、その職場においてしっかりと役割を担えているでしょうか。
もしかしたら、ご自身の仕事や役割において自信が持てていないから、職種や資格を振りかざしているのかもしれませんね。
過去の医療や介護の現場において、介護職員が看護職員のサポート役のような捉え方をされている時代もありました。
そのような時代を生き抜かれた看護職員さんの中には、その名残を持っている方もいまだにいらっしゃるようです。
今や介護職員は、介護の現場における「専門職」として、貴重な役割を担っています。
そこには「看護が上」だという概念は存在せず、それぞれが同じチームの中で異なる役割を担うチームメイトなのです。
■解消法は、責任者が全体に方針を伝えること
では、ご質問のような状況をいかにして解消するか。
まずは、経営者や管理者が「チーム」の存在する目的、「チーム」として向かうべき目標を明確にすること。
そして「チーム」の目標達成のために多職種連携が必要であり、そこには職種による上下は無いということを掲げ、組織図や評価の仕組みの中で「見える化」をしてもらうこと。
これは、組織を動かすことになるので、凄く大変な作業ではありますが、冒頭で記したような成熟した現場を望む経営者ならしっかりと理解され、必要なアクションを起こしてくれると思います。
この看護師さんに、ご質問者さんが直接伝えることは難しいと思います。
チームを営む責任者に「チームの方針」「チームの考え方」として、チーム全体にしっかりと伝えてもらいましょう。
■「専門職」としての介護職のポジションを確立する
あと、介護職側でもやることはあると思います。
それは、介護職員が介護の専門職としての「知識」「技術」「矜持」を持ち、それを実践し、「専門職」としてのチームの中のポジションをしっかりと確立することです。
「介護」という仕事を自ら貶めるような言動しかできていない介護職員がいることも事実です。
自分自身は、そして自分の同僚はどうなのかをしっかりと確認し、介護の専門職として、看護職だけでなく他職種からしっかりと認めてもらえる存在になることも大切だと思います。












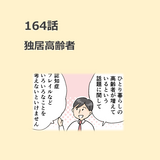




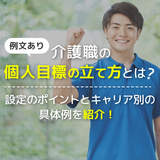













福岡福祉向上委員会 代表