本日のお悩み
ある男性利用者さんが苦手です。わざわざ訪れた共同スペースのテレビや音楽の音、介助をしている職員の声や作業音をうるさいと怒鳴ったり、小言や舌打ちをします。
難聴の方も多く、声が大きいことがあるのは申し訳ないとは思いますが自分の介護を否定されるようで落ち込みます。
その人が近くに来ると身構えたり目を逸らしてしまうようになりました。職員としてダメだとは思っていますが…体や声も大きく怖いのが本音です。
認知症もなく、上司が話をするとその場は素直に聞くのですが一般職員の話は馬鹿にしたように聞き流し「上に悪いように言いつけてやろうか」と笑いながら言われた職員も一人二人ではないです。
諸事情で家がなくなり老健に入所したのですが、身体的に自立しているうえ拒否があるためリハビリもしていません。
自立しているのに施設にいることや制限のある生活に対する不満などがあることは理解はできますが、ここまで自立している人がそれを理由に職員への暴言が許されるのでしょうか?これも職員の理解不足や技術不足といわれるのでしょうか?
老健へ来てリハビリもせずそんなにも不満ばかりなら他所へ行ってはどうですか、という言葉を何度飲み込んだかわかりません。
この人のことを納得できない、受け入れられないのは自分の力不足で、自分は介護士失格なのかもしれないと思うとつらいです。
質問者:さおり さん
ご自分を追い込みすぎです。チームで解決していきましょう!
ご質問ありがとうございます。とても深刻な相談だと感じました。
ご質問者さんは、制限のある生活に不満を抱いているご利用者さんに、一定の理解を持ちながらも、認知症ではないご利用者の心無い言葉に対して、心を傷つけておられるのですね。
これまで培われてきた知識や技術が否定されているようで、ご自身が介護職員失格なのではないだろうかと、自問自答されてしまうのですね。
私もこれまでの現場経験で、同様のケースに悩み、周囲の協力を得ながら、チームで対応してきたケースがあります。
そこで実践してきた内容を整理しながらお伝えさせていただきます。
■ご利用者の状況を整理してみましょう
まず初めに、それぞれの状況や想いを整理してみましょう。
ご利用者の方についてです。
ご相談内容から抜粋すると、
① 自立度が高い。
② 共用部のテレビや音楽の音、介助者の声や作業音をうるさいと怒鳴ったり、小言や舌打ちをする。
③ 認知症ではない。
④ 上司の話には耳を傾ける。
⑤ 一般職員の話は馬鹿にしたように聞き流し、『上に悪いように言いつけてやろうか』と笑いながら言う。
⑥ 諸事情で家が無くなり老健に入所している。
⑦ リハビリには拒否がある。
■質問者さんの気持ちと状況も整理しましょう
続いてご質問者さんについてです。
質問者さんの想いを考察する為に、相談内容の文章とは、一部あえて言葉を変えて記載してみますね
① この男性利用者さんが苦手。
② 難聴の方もいて声が大きいことは申し訳ない。
③ その方が来ると怖くて身構えてしまったり、目をそらしてしまう。
④ その行動が職員として駄目だと分かっている。
⑤ 自立しているのに施設にいて、制限も多く不満に思われていることは理解している。
⑥ ここまで自立している(理解している人)が、それを理由に職員への暴言が許されるのか疑問。
⑦ 職員の理解不足や技術不足ではなく、この方の気質的な問題なのではないかと思っている。(パワハラに感じてします。)
⑧ 本音は、そんな不満であれば、他所へ行って欲しい。
⑨ でもやっぱり、納得できなかったり、受け入れられないのは、自分の力不足なのではないのかと自問自答してしまい、介護職員としての自信を失ってしまう。
そんなことを思う自分は介護職員失格なのではないかと思っている。
ご自身の感情をストレートに表現するために、少しアグレッシブな言葉に変換している点は御了謝下さい。
■考察1.工夫で解決できることはありそうですか?
この整理を基に、対応について考察していきましょう。
まずはご利用者さんから。
① テレビや音楽の音ですが、静かな環境で過ごしたいと思われているのでしょうか?小言を言うと有りますが、内容はどのようなものですか?居室のご移動や、配慮できる点はありますか?
この方の強い言葉を投げかける可能性の一つとして、職員の日常やルーティーンの中で、職員は当たり前に感じていることが、ご利用者さんからすると、当たり前ではなく、不快に思われてしまう事が多々あるように感じています。『いつもそうだから』や『これが普通だから』と、決めつけすぎずに、職員の配慮や工夫で解決できることがないのか情報をまとめてみてはいかがでしょうか?
特に、スタッフ全体にこの配慮が共有されていないことで、スタッフによって対応が変わってしまい、『この人はやってくれて、この人はやってくれない』というように、サービス水準に差が出てしまう事は改善していく必要がある事かと思います。
また、このご利用者さんが信頼しているスタッフの方はいませんか?
一人でもいるのであれば、その方から対応の方法や、ご本人の愚痴や悩みなどを聞いていないか確認が取れると良いと思いますし、その方がなぜ信頼されているのか等、その方の対応にヒントがあるかもしれません。
■考察2.ご利用者さんの気持ちはどうでしょうか?
⑥⑦についてですが、諸事情で家が無くなり、リハビリにも拒否がある。
ご質問者さんがご理解されている通り、とてもつらい経験をされて入所されてきていますね。
ご本人がまだ事実を受け入れられずに、未来に希望が見えていないからこそ、リハビリにも意味を持たせられない可能性はありますね。
元気になったところで、家に戻れるわけではないとご理解されているからこそ、活動自体を拒否されているのかもしれませんし、今はリハビリもできないほど、心がボロボロなのかもしれません。
自宅は難しい状況ですが、在宅復帰計画や今後の先行きの見通しも、現状では立っていない状況でしょうか?
そのような不安な状況下で、ご本人の焦りや不安、不満や恐怖が、最高潮なのかもしれません。
どうにかしたいけれど、自分では何もできない、もどかしさや葛藤。自分の状況を理解してくれる味方なんて、どこにもいない。
本当は、そんなことをするつもりもないのに、どうしてか弱い立場であろう一般職員に強く当たってしまう。そんな自分も嫌だし、そんな態度をとっていたら、だれも味方がいなくなってしまう事も理解できている。でもこのイライラや不満を吐き出さないと、どうにかなってしまいそうな恐怖を感じていらっしゃる。
でも、どうしたら今の状況を抜け出せばよいのかわからない。。。
そんな心情なのかもしれません。
■もう一度チームでこのご利用者さんと向き合ってみませんか?
私は、このご利用者の想いも、ご質問者さんの想いも考察することはできますが、その方と話せていないので、思い描く事しかできません。ご質問者さんにとっては、『そんなことは自分も分かっているけれど、そうではない違和感があるから相談しているの』と思われるかもしれません。
『だからこそ、未来を具体的にイメージできるように、もう一度チームでこのご利用者さんと向き合ってみませんか?』
これが私のご質問に対する回答です。
■自立度が高いからこそ、一緒に解決策を見つけていけるかも
少し怖いイメージのご利用者さん。スタッフの皆さんと、気持ちの上でも距離がありませんか?
その距離を少しでも縮めるために、介護支援専門員、相談員、介護リーダーや主任、理学療法士、看護師、医師、外部の協力者の皆さん等で、もう一度、希望の見える未来を、ご利用者と一緒に考える時間を作ってみてはいかがでしょうか?
認知症がない、自立度の高いご利用者だからこそ、当事者の方と一緒に出来ることを見つけていくことは可能だと思っています。
少しずつ、何かが変わるかもしれません。
その際には、ご利用者さんの気持ちや状況を理解したうえで、ご利用者さんの発言について、心を痛め、傷ついている職員がいることも伝えましょう。
人は向き合わないと始まらないし、意思疎通をしないと相手のことなんて理解できないと考えています。それでも、本音はわからない。それが人だと常々思っています。
でも、間違いなく言えることは、『人』は、誰かに頼られ、認められ、褒められないと前を向いて歩みを進められないということです。
自分は必要のない人間だと思ってしまうと、歩むことすら諦めてしまいます。
そう思わせない、もしくはそう思ってしまっている人に、もう一度自信を取り戻せるのも介護職員だと信じています。
チームで向き合い、より良い解決策を模索していきましょう。
その方の歩んできた歴史を紐解いてみると、その方を知る上でのヒントがたくさん隠されていると思いますし、日常のコミュニケーションの質も高くなってくると思いますので、そんな情報も集めてみてくださいね!
■ご質問者さんは、すばらしい介護職員だと感じました!
ご質問者さんは正義感が強く、ご自身の中で、『善悪の判断基準』や、ご自分や介護職員の『あるべき姿』といった信念をお持ちの方だと思います。
だからこそ、そのご利用者さんへの態度や感情が沸き起こってきたのだと思います。
ご質問者さんも、もっとご自身を認めて褒めて差し上げて下さいね。
そして、一人で抱え込まずに、周囲を巻き込み、頼ってみてください!
私は、ご質問者さんのことを素晴らしい介護職員だと感じましたよ。
最後に、認知症がないという事に、ご質問者さんがこだわられているように感じましたので、
認知症の有無ではなく、ご利用者ご本人と向き合ってみてくださいね。
ご本人にも皆さんの想いが届くと信じています。
今一度、究極のサービス業である介護職員として、対人援助の原点に戻り、丁寧にアセスメントを行い、課題を明確にしながら、ご本人と共にチームで考えた計画を実行していただければ幸いです。
一朝一夕で解決しないことは、よく理解しています。
この経験がご質問者さん、ご利用者、チームにとって、明日に活きる経験や学びとなることを切に願っています。
よろしければ、続報をお寄せいただけると幸いです。
ありがとうございました。











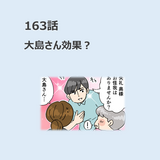


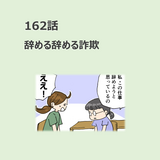



















・けあぷろかれっじ 代表
・NPO法人JINZEM 監事
介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士