本日のお悩み:仕事に慣れた一方で空回りしてミスをしてしまいます
最近は仕事に慣れてきた反面、ミスや事故が増えてしまい、先輩から注意されることが多くなりました。「この仕事、自分に向いているのかな…」と不安になる毎日です。
先日の夜勤では、1人で2ユニットを担当していて時間に追われ、オムツ交換の前に食事を配ってしまいました。そのことで夜勤の先輩やユニットのスタッフに怒られました。私が悪いのですが、要領よく動けず、早めに動かないと終わらないと思って焦ってしまったんです。
一生懸命やっているつもりでも、空回りしてしまうことが多くて、どうしたらいいのか分からなくなっています。
業務の棚卸をしてみましょう!
■執筆者/専門家

特に業務が重なっているときは、どうしても焦ってしまいますよね。 時間に追われる中で冷静な判断ができず、結果的にミスにつながってしまうこともあると思います。
■手際のいいスタッフ、憧れますよね
手際の良いスタッフは、複数の業務を同時にこなしながら、スムーズに動いていて「さすがだな」と思う反面、自分と比べて落ち込んでしまうこともあります。でも、そんな姿に少し憧れたりもしますよね。
この記事では、介護現場で多い事故の内容を確認したうえで、原因や防止策について解説していきます。
よくある介護事故やミスとは?
.png)
それぞれの事故について詳しく解説します。
■転倒・転落・滑落
つまり、介助者の目が届きにくい場面で、利用者さんが歩行中にバランスを崩したり、ベッドから転落したりするケースが多いということです。逆に、直接介助中に起きる事故は少ないこともわかっています。
さらに、骨折の診断では、大腿骨頸部や転子部の骨折が多く、手術が必要になるケースがほとんどです。高齢者の場合、長期入院によってQOL(生活の質)が低下し、合併症が起きてしまうこともあり、残念ながら死亡に至るケースも報告されています。
■誤嚥・誤飲・むせこみ
これらは、食事介助中に起こることが多い事故であるため、防止するには利用者さんの状況や体調をしっかりと把握し、それぞれに合った硬さや形状の食事を提供する必要があります。
今まで普通に食べることができていた食事でむせてしまった場合は、体調の変化がある可能性があるため医師や看護師など、専門職の方と連携をして、事故を防ぐようにしましょう。
■送迎中の交通事故
事故を防ぐために、送迎時はより一層注意深く周囲を確認する必要があります。
介護における滑落事故とは?
・転倒:立っている状態からバランスを崩して倒れること(例:歩行中につまずいて倒れる)
・転落:高い場所から勢いよく落ちること(例:階段やベッドから落ちる)
こうした事故を防ぐためには、先述した通り、利用者さんの動きに注意を払い、ベッド柵の使用やポジショニングや声かけの工夫などを施設全体で検討することが大切です。
滑落事故の原因
以下で、事故が起きやすい場面や要因を詳しく説明します。
■施設による環境的側面
・トイレや浴室
・車椅子や椅子
・床や通路
ベッド柵が低い、座面が滑りやすい、手すりが使いづらいなど、設備の不備や配置の問題が原因になることがあります。また、床が濡れていたり、段差があると、移動中にバランスを崩して滑落することもあります。
このように、施設の環境が整っていないと、利用者さんのちょっとした動きが滑落事故につながることがあります。日々の点検や、利用者さん一人ひとりに合わせた環境調整が、事故を防止するうえで重要です。
■利用者さんによる個人的側面
・認知機能の低下
・不安や焦り、せっかちさなどの心理的な要因
まず、身体機能の低下では、筋力やバランス感覚が弱くなることで、座っている姿勢を保てず、ずり落ちてしまうことがあります。また、認知機能の低下では、自分の身体の状態や周囲の状況を正しく判断できず、無理な動作をしてしまうことで滑落につながることがあります。
さらに、不安や焦り、せっかちさなどの心理的な要因で早く動こうとしたり、介助を待てずに自分で動こうとすることで、姿勢を崩してしまうこともあるでしょう。
これらの要因に対応するために、個々の状態をよく理解し、適切な声かけや見守りを行うことが大切です。
■介護スタッフによる行動的側面
また、介助のタイミングや声かけが遅れることで、利用者さんが不安になり、無理に動こうとしてしまうこともあります。介護職が利用者さんの状態をよく理解し、適切なタイミングで介助や見守りを行うことが、滑落事故の予防につながります。
もう繰り返さない!明日から実践できる介護ミスの再発防止策
対策は、個人でできるものと施設や事業所全体で取り組めるものに分けられます。
■【個人】メモ・指差し確認・質問を徹底する
次に、作業ごとに指差し確認を行うことで、手順や対象の利用者さんをしっかり意識することができます。慣れた業務ほど確認を怠りがちなので、あえて「見て・指差して・声に出す」ことでミスの防止に繋がります。
そして、わからないことはすぐに質問することも重要です。「上司が忙しそうで聞きづらい」「自分で何とかしよう」と思って判断を誤るより、早めに確認してミスを防ぐ方が安全です。小さな確認が、大きな事故を防ぐ第一歩になります。
■【組織】ヒヤリハットを共有し、仕組みでミスを防ぐ
さらに、共有された事例をもとに、業務手順や環境の見直しを行い、ミスが起きにくい仕組みを整えることが大切です。例えば、記録のフォーマットを統一する、声かけのタイミングをルール化するなどです。
個人任せにせず、チームで支え合う体制が、利用者さんにとって安心・安全な介護につながります。
ミスで落ち込んだ心のケアと気持ちを切り替える方法

ここからは、落ち込んでしまったときの心のケアと気分転換方法について紹介します。
■失敗は誰にでもあると受け入れ、客観的に振り返る
そのうえで、何が原因だったのかを冷静に振り返ることが、次につなげる第一歩です。感情ではなく事実に目を向け、「どうすれば防げたか」「次はどう動くか」を考えることで、同じミスを繰り返さず、失敗を自分の力にすることができます。
■睡眠・運動・趣味で心身をリフレッシュする
また、軽い運動やストレッチで体を動かすと、気分転換になり、ストレスも軽減されます。さらに、自分の好きな趣味の時間を持つことで、気持ちが前向きになり、自然と切り替えができるようになります。自身がリフレッシュできる趣味を日ごろから探しておけるとよいでしょう。
■信頼できる同僚や上司に相談する
また、第三者の視点からアドバイスをもらうことで、自分では気づけなかった改善点が見えてくることもあります。
■どうしても辛いなら転職も一つの選択肢
転職は逃げではなく、自分に合った働き方や職場を見つけるための前向きな行動です。無理を続けて心や体を壊してしまう前に、「自分らしく働ける場所はどこか?」と考えてみることも大切です。
介護ミスを防ぐための業務の棚卸し
そのうえで、過去にヒヤリとした場面やミスが起きた場面を振り返り、原因を探っていきます。たとえば、服薬の確認漏れや記録の入力忘れ、見守り中の滑落など、具体的な事例を挙げて分析することがポイントです。
次に、時間帯や人員配置に応じて、業務の順番や担当を見直してみましょう。朝の忙しい時間帯には記録業務を減らす、見守りを強化する時間を設けるなど、効率的な動き方を考えることで、ミスの予防につながります。
最後に、改善策を具体的に業務に組み込んでいきます。チェックリストの導入や声かけのルール化、情報共有のタイミングの見直しなど、現場で実践できる工夫を取り入れることで、ミスを未然に防ぐ体制が整います。
■全体を俯瞰すると、「準備のための準備」ができるようになる
また、利用者さんごとの対応方法にも気づきが生まれます。例えば、○○さんは起立時に排尿が始まってしまうため、ズボンを下ろす前に一度手すりにつかまり、5秒ほど立位保持していただくことで、排尿のタイミングを調整できます。これを起立訓練と併せて行えば、トイレ誘導時の失敗も防げます。こうした対応は記録に残すことで、他のスタッフとも共有できます。
業務の流れを俯瞰して見ることで、動線の非効率さにも気づき、改善につなげることができます。事前準備を整えるための「準備」を意識することで、焦りが減り、注意点に配慮した安全な介助が可能になります。結果として、事故予防にもつながり、業務の質が向上します。
■「丁寧な対応ができる」という長所も大切に
焦って動いてしまうと、せっかくの丁寧なケアが不十分になってしまうこともあります。だからこそ、業務の棚卸しをして、流れを整理することで、どこで時間を節約したり効率化したりできるのかが見えてきます。仮に非効率な動きがある場合は、そこを改善し、次に行うことが予測できることで焦りが解消できます。
さらに、この時間軸を基に、リーダーや主任の方にどのような動きをしているのか聞いてみるのも参考になると思いますよ。
最後に:ミスを次に活かすことも大切
しかし、業務の棚卸しや事前準備、チームでの情報共有を徹底することで、ミスの再発を防ぐことができるでしょう。大切なのは、失敗を責めるのではなく、次に活かす姿勢です。焦らず丁寧な対応を続けていきましょう。
■あわせて読みたい記事

介護現場におけるヒヤリハット報告書の書き方や事例をご紹介! | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1334介護現場においてヒヤリハットの事案と事故の境界線に迷う方も多いのではないでしょうか。この記事では、ヒヤリハットの定義について確認したあと、報告書の書き方についても解説します!【執筆者/専門家:後藤晴紀】

介護のリスクマネジメントとは? 介護事故の事例や対応方法を解説 | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1190[2024年9月更新] 介護現場では、常に転倒や誤飲などの事故が起こるリスクがあるため、施設全体でリスクを把握し、事故を防ぐための対策を講じる必要があります。介護事故の事例やリスクマネジメントの実践方法、事故が起こった場合の対応方法を解説します。【監修者/専門家:望月 太敦】

















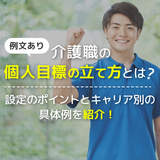












・けあぷろかれっじ 代表
・NPO法人JINZEM 監事
介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士