介護者の息抜きを行う支援「レスパイトケア」を徹底解説!
高齢者の増加に伴い、介護が必要な人もますます増加すると予想されるなか、介護する側(要介護者の家族など)の休息を目的とした「レスパイトケア」が注目されています。
この記事では、レスパイトケアとはそもそも何なのかであったり、レスパイトケアの目的、効果、サービスの種類など幅広く解説します。
出典:厚生労働省 我が国の人口について
■執筆者/専門家
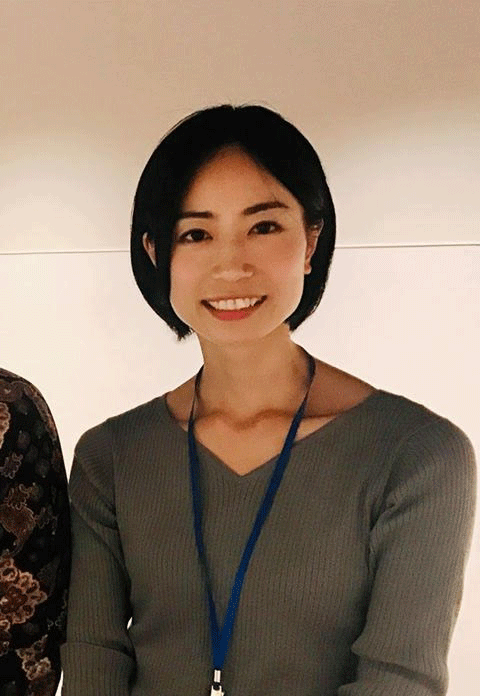
社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員 特別養護ホーム生活相談員、訪問介護事業、地域包括支援センターにて介護支援専門員の経験あり。 現在は、デイサービス管理者として勤務。 地域でのネットワーク活動では事務局として「死について語る会」や「3大宗教シンポジウム」など幅広いテーマの勉強会やイベントを企画・運営の経験がある。 すきな食べ物はラーメン。
レスパイトケアとは?
■長期間続く介護の負担を和らげる支援
介護から一時的に離れることで、リフレッシュすることができ、介護者の心身の健康を保つことができるでしょう。介護者の健康は不可欠です。
■介護職とのかかわりが増え、助言も受けられる
また、レスパイトケアを受けることで介護職との関わりも増え、日々の介護に対する助言を受けることもできます。
レスパイトケアの目的
介護者が、一時的に休息をとることでリフレッシュをすると、より良いケアを継続的に行うことができます。レスパイトケアをおこない、介護職からのサポートを受けることで在宅での介護を継続していくことができます。
レスパイトケアで得られる効果
2.社会的孤立の防止
3.介護を受ける側の精神的負担の軽減
4.介護者と要介護者の関係性改善
■1.介護者のストレス軽減
■2.社会的孤立の防止
介護以外に興味のあることや、取り組めることがあると、孤独感やストレス軽減に繋がるでしょう。
■3.介護を受ける側の精神的負担の軽減
レスパイトケアを活用し、家族や親戚が休息をとれている姿を見てもらうことで、介護を受ける人も安心感を持って過ごすことができます。
■4.介護者と要介護者の関係性改善
そのため、レスパイトケアを活用し、リフレッシュすることで、関係性を良好に保ち続けることができるでしょう。
レスパイトケアを提供するサービスの種類6選

■レスパイトケアとして利用できる訪問サービス
●1.訪問介護
訪問看護、訪問リハビリ、訪問入浴といったサービスも訪問サービスにはあるため、介護者の大変さや利用者の状態によっては、訪問介護の一択ではなく、適切なサービスを選べるように進めるとよいでしょう。
■レスパイトケアとして利用できる通所サービス
●2.通所介護(デイサービス)
●3.認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)
また、介護者にとっても専門的な介護職から、認知症に関する知識や接し方などを学ぶことができ、日々の介護の質を高めることができます。
■レスパイトケアとして利用できる施設サービス
●4.小規模多機能型居宅介護
また、地域密着型であるため、介護を受ける人にとっても住み慣れた環境で介護サービスを受けることができるといったメリットもあります。
●5.短期入所介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
また、ショートステイは介護サービスの体験のような役割も果たします。入居型の施設に入るか迷っている方や、施設に対して抵抗がある介護を受ける人にとって、短い期間だけ入所をしてみると、介護施設の過ごしやすさや、ケアの質の高さに驚き、前向きな気持ちになることができる場合があります。
●6.レスパイト入院
また、介護者にとっても専門的な医療機関でケアを受けさせることができるため、安心して過ごすことができるでしょう。
レスパイトケア利用時に押さえておきたいポイント3つ
■1.レスパイトケアの目的を正しく理解し、ネガティブな利用ではないことを認識する
先述しましたが、レスパイトケアの目的は「介護者が一息つくことができるようにサポートすること」です。介護者がしっかり休むことで、介護を受ける側も質の高い介護を受け続けることができ、長く在宅介護を行うことができます。このように、目的をしっかり理解したうえで、レスパイトケアを活用していけるとよいでしょう。
■2.予約が必要で、急な利用は不可
また、レスパイトケアを利用するためにはケアマネージャーや地域包括支援センターの職員によるケアプランの作成も必要です。ケアの利用を希望する際は、担当のケアマネージャーや地域包括支援センターに相談してみるとよいでしょう。
■3.環境の変化によるリスクを考慮する
慣れない環境や、知らない人からケアを受けることは、本人にとって精神的な負担となる可能性があります。また、精神的に疲弊してしまうことから身体面の不調にも繋がる場合があるでしょう。これらのリスクを把握したうえで、本人の不安に思う点は解消したうえで、レスパイトケアを利用していけるとよいでしょう。
介護職の視点で、利用者やご家族に対して配慮すべきこと3つ
■1.環境が変わることでの混乱に注意
レスパイトケアを利用する際には、本人の自宅での生活リズム・食事量・排泄のリズムなどをよく把握し、できる限りそれらを継続することが大切です。 また、自宅へ帰ってから混乱することもあるので、利用後の様子にも注意が必要です。
■2.理想論だけを述べない
その際、つい介護の理想論を伝えてしまいたくなるかもしれませんが、介護者が知りたいのは理想ではなくどのように今の状況を回避すればよいのかという現実的な生活の工夫である場合が多いです。 そうした気持ちを理解し、具体的で実用的な助言を行うことを心がけましょう。
■3.介護者を気遣う言葉がけ
介護者は、申し訳ないという気持ちを感じ要望や悩みを言うことを遠慮していたり、サービスを利用している間も不安を感じていたりする場合があります。これらの不安を解消するためにも、積極的にコミュニケーションをとるよう意識しましょう。
レスパイトケアの課題
■1.急なサービス利用に対応しづらい
そのため、家族の急な体調不良や突発的なサービス利用については対応しづらい現状があります。 ケアマネジャーが介護者についても適切にアセスメントを行い、計画的に利用できる状態を作っておく必要があります。
■2.介護者の訴えがあるまで気づきにくい
ケアマネジャーの訪問で直接会えなかったり、本人の様子だけを話して介護者についてはあまり話せなかったりということが重なると、知らないうちに1人で負担や悩みを抱え込んでしまうこともあります。 かかわるサービス事業者それぞれが、介護者の様子も気にかけ、介護への負担感を大きく感じているようであればレスパイトケアの促しを行うために、ケアマネジャーへの相談が必要です。
■3.利用者さん主体のサービスを提供する
しかし視点を変えると、自宅の外へ出て介護者以外の人とかかわるという機会は、社会生活を送るうえで利用者さんにとってもプラスとなる場合が多いです。サービスの利用で、介護者にとってメリットがあるだけではなく、利用者さん自らが利用したい、利用してよかった、と思うようなサービスの提供を行えるようにすることが、介護職の使命であると思います。
まとめ:レスパイトケアを活用し、より質の高い介護を行っていきましょう!
誰かに頼る、誰かに悩みを打ち明けるというのはハードルが高いように感じる場合もありますが、レスパイトケアについて、目的をしっかり把握し、継続的な在宅介護が行えるよう、適宜活用していけるとよいでしょう。1人で抱え込まないこと、これだけは忘れないように介護生活を送ってください。
■あわせて読みたい記事

もしも家族に介護が必要になったら|制度や事業所を頼り、介護と仕事の両立を目指そう | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1200家族の介護は突然やってくるものです。いざやってきたときに、すぐに行動方針を決めることができる方は少ないと思います。また、介護と仕事を両立していけるのだろうか、慣れない介護をうまくできるのだろうかなど不安も多くあることでしょう。この記事では、いつ来るかわからない介護に備えて、どのような支援体制があるのかを解説していきます。【執筆者/専門家:牧野 裕美】

介護と仕事の両立|「介護離職」を防ぐために何ができるか | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1197超高齢社会の日本において、親の介護を抱えている労働者は非常に多くいます。また、介護を理由に仕事を辞めてしまう「介護離職」も一定数いるのが実情です。この記事では、仕事と介護の両立を目指すためにどのような工夫ができるか、実体験をもとに専門家が解説します。【執筆者/専門家:大関 美里】

【独居高齢者】一人暮らしの高齢者が抱える課題と介護施設の職員ができることとは? | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1176超高齢社会である日本には一人暮らしの高齢者が多くいます。もちろん健康意識の高い方も多くいますが、独居高齢者の中には引きこもりがちになったり、体調不良に気づくことが遅れてしまったりする方もいます。これらの問題に社会全体で取り組むために、高齢者と接する機会が多い介護職員は何ができるのでしょうか。[執筆者/専門家:羽吹 さゆり]







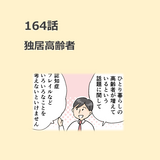
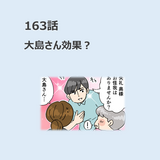







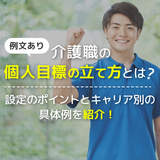












ささえるラボ編集部です。
福祉・介護の仕事にたずさわるみなさまに役立つ情報をお届けします!
「マイナビ福祉・介護のシゴト」が運営しています。