もしもの介護に備えよう!必要なサービスや制度を適切に見分けるには?
■執筆者/専門家

株式会社ケアサービスひかり 介護福祉士/介護支援専門員 日本ホームヘルパー協会東京都支部 副会長 2000年4月より24時間365日型の訪問介護事業所の管理者・サービス提供責任者として医療的ケア児から障害・高齢者の在宅介護支援に携わっています。 ヘルパーは、利用者の伴走者であり、先導者でもあり、より安全な暮らしができるように生活見守り隊でもあります。ヘルパー自身も生きて活かされるこの魅力ある仕事を発信し、繋ぎたいと奮闘しています。
■家族の介護は突然にやってくる
家族と同居・別居、兄弟姉妹の有無などに関わらず、家族の介護はある日突然やってきます。
それは、想定外の出来事だったり、振り返ってみるとやはりちょっと変だったと思ったり状況は人それぞれですが、これから始まる未知なる生活への漠然とした不安に襲われることは多くの人にとって共通の事項でしょう。そして、生活のほとんどの時間を費やし、生計を立てる手段の「仕事」に対して「続けられるのだろうか」「続けて良いのだろうか」「両立できるのか」という悩みや、今まで培ってきたキャリアを強制終了されそうな、もしくは、しなくてはいけないような焦りに駆られることもあるでしょう。
筆者も風邪をひいて寝ているところすら見覚えのない、働き者で病気知らずの母親から「一度帰ってきて、母さん手術しないと死んでしまうそうなのよ」と、訪問介護の移動中の一本の電話が鳴り、そこから親の介護が始まりました。
最初に湧いた感情は「こんなに忙しいのに邪魔をしないで」という仕事が増えたという感覚での苛立ちでした。母の体の心配はそのとき第一には浮かびませんでした。なんてひどい娘でしょうか。人に寄り添う介護のプロでありながら、うろたえました。
介護が必要になったら?適切な相談や制度利用で安心できる介護生活を
■介護を必要とする方が住んでいる地域の窓口で相談しましょう
そこで、自身の経験も踏まえたうえで、「突然のことで何から手をつけて良いかわからない」という方に、おすすめするのは、介護を要する方が住んでいる地域(現住所地)で相談をすることです。「介護保険制度」という介護を必要とする方に向けた制度は国の統一された制度ではありますが、介護サービスの内容によっては、自治体によって実施されていないサービスもあります。特に「地域密着型・・」という名のつくサービスは行われているかどうか確認が必要です。
地域にあわせたアドバイスを受けるためにも相談先としては「地域包括支援センター」を利用しましょう。地域包括支援センターは、各市町村や都道府県に中学校区(おおむね30分以内)に1つという目標で設置されていて、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員などが配置されています。住民の健康促進と保持、生活の安定を目的とした施設で、そのまま介護保険申請をすることもできます。土曜日も開所している所が多くあり、相談の予約をすることができます。
家族に介護が必要となった際、まず初めに、申請をして要介護度認定を受けることから始まります。在宅で介護保険サービスを利用する際には、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成し、介護サービスの種類や事業所、利用料金の提示を受けることができます。但し、介護保険は自己選択・自己決定を基本としているため、介護支援専門員が勝手に決めるのではなく、利用者本人やその家族の希望を考慮して決定していきます。
■必要な介護サービスを1人で選択することは難しい
介護保険サービスには自宅(居宅)にいながら受けることのできるサービスと、施設に入所するサービスがあります。ここでは、それぞれについて簡単に説明しますが、ご家庭の状況や利用者さん、ご家族の気持ち等も考慮しながら適切なケアを選択しましょう。
■自宅で介護を受けられる「居宅サービス」
居宅サービスと一概に言っても、訪問サービス・通所サービス・短期入所サービスなど様々な種類に分けられます。
ー訪問サービス
また、体の状態によっては、医師による往診や、看護師が訪問して医療を受けることもでき、診断に基づいて処方された薬は薬剤師によって届けられます。
ー通所サービス
リハビリを中心に受けるのをデイケアサービス、レクリエーションや生活援助を中心に受けるのをデイサービスと呼びます。
ー短期入所サービス
■入所して介護を受ける「施設サービス」
介護老人保健施設は、比較的要介護度が低い方が入所をするため、在宅復帰を目的としています。
■住み慣れた地域で生活を続ける「地域密着型サービス」
小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護は、デイサービスと宿泊・訪問介護の複合型でどこにいても馴染みのスタッフのケアが受けられます。
介護者も介護支援制度を利用して、生活環境を整えましょう
そのため、子育てとタイミングが重なったり、介護する側も年齢的に体の変化が現れたりする場合もあるでしょう。介護をする側も心身の健康は第一です。
介護者が心身ともに健康で過ごせるように、介護者として利用できる介護支援制度を確認しましょう。
■介護休業・介護休暇制度
.png)
そのほかにも会社独自の制度や民間の介護割引等もありますので、家族の介護が始まる前に確認しておきましょう。
■テレワーク(リモートワーク)の活用
要介護度5という寝たきりのご両親の介護を長女様一人で担っていた方もいるご家庭がありました。訪問介護での排泄介助、訪問看護で体調確認、訪問入浴、デイサービスを利用してチームで支援しました。長女様はリモートワークを時々利用しながらケアの様子を確認したりケアの繋ぎをしたり、時には臨時的に訪問介護を増やし飲みに行ったりと仕事と介護・ご自身の生活のバランスをとっていました。
介護サービスを導入しても家族としての役割が変わることはありません。要介護者になったとしても一番望むのは家族の幸せです。ある制度は利用して、頼れる人には頼って、社会と繋がり続けることが介護と仕事が両立できる秘訣です。
最後に:もしもに備えてはやめの準備をしましょう
いかがだったでしょうか。今回はあくまで大枠の部分を説明しましたが、介護と仕事を両立するための仕組みは多くの企業や自治体でつくられています。家族の介護は、明日突然始まることもあります。その「もしも」に備えて今から準備をしておけると、いざというときに安心して、自身の生活とのバランスを崩すことなく介護に取り組めるでしょう。
■あわせて読みたい記事

【独居高齢者】一人暮らしの高齢者が抱える課題と介護施設の職員ができることとは? | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1176超高齢社会である日本には一人暮らしの高齢者が多くいます。もちろん健康意識の高い方も多くいますが、独居高齢者の中には引きこもりがちになったり、体調不良に気づくことが遅れてしまったりする方もいます。これらの問題に社会全体で取り組むために、高齢者と接する機会が多い介護職員は何ができるのでしょうか。[執筆者/専門家:羽吹 さゆり]

老老介護の現状や解決策を解説!今後の日本で大切なこととは。 | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/96450年後の日本人口を紐解き、深刻な超高齢社会によって生じる老老介護・認認介護等、新たな課題にどう日本は立ち向かうべきなのかを専門家が解説します。【コラム:後藤 晴紀】


















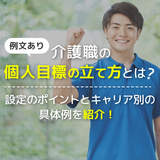













株式会社ケアサービスひかり 介護福祉士/介護支援専門員
日本ホームヘルパー協会東京都支部 副会長