高齢者の認知症予防に手遊びは効果がある?
■執筆者

ささえるラボ編集部です。 福祉・介護の仕事にたずさわるみなさまに役立つ情報をお届けします! 「マイナビ福祉・介護のシゴト」が運営しています。
■認知症の原因と最新治療薬
日本では抗認知症薬は現在4種類のため、5つ目の薬となります。
国内約600万人といわれる認知症患者の約6割〜7割はアルツハイマー型認知症です。
そして、その原因は「アミロイドベータたんぱく」が神経細胞を壊し、記憶力や判断力を低下させるとこと言われています。
レカネマブは、この脳内に蓄積した異常なタンパク質「アミロイドベータ」の除去を狙います。
この新薬のお話をとってみても、認知症予防として重要なこととしては「アミロイドベータたんぱくを蓄積させないこと」となるわけです。
■手遊びは脳を活性化させ、認知症予防に間接的効果があり
脳が活性化することは、認知機能への働きかけも期待できるため、手遊びは認知症の予防にも間接的な効果をもたらすと考えられます。
高齢者の脳トレにおすすめの手遊び12選
簡単に取り組めるものや、道具を用いるものなど、さまざまな種類のものを紹介しますので、利用者さんの状態に応じて選定してみてください。
■簡単に取り組める手遊び

■1.指折り体操
・親指から順番に1本ずつ折り曲げていきます。
・すべての指を折りたたみ終えたら、次は小指もしくは親指から順に広げていきましょう。
・「1・2・3」などと数字を数えながら指を折ると脳への刺激にもなります。
指を折り曲げる動作は、高齢になってくると難しく感じる場合もあります。無理に実施させるのではなく、ゆっくりと様子を見ながら進めていきましょう。
また、他のレクリエーションをする前に準備運動としても活用できるでしょう。
■2.指離し体操
・左親指と右親指、左人差し指と右人差し指など対称の指がくっついている状態を確認します。
・親指から順に1本ずつ指先を離していきます。
・上記動作をする際に、意図しない他の指が離れてはいけないルールをつけておきましょう。
一見、簡単な動作ですがスピードアップなどをしてみると難易度の調整ができます。利用者さんにとって可能な範囲で少しスピードをあげると脳への刺激にもなるでしょう。
■3.指回し体操
・他の指先同士はくっつけたまま、親指から順に指同士が当たらないよう指先をぐるぐるまわしてみましょう。
中指や薬指をまわすときは難易度が高いかと思います。できているかどうかを周囲の人と確認しながら行うことで、コミュニケーションのきっかけにもなるでしょう。
■4.親指グーパー体操
慣れないうちは両手が同じ動きでもよいですが、難易度をあげたい際には、右手の親指は内側、左手の親指は外側のように左右で違う動きをとるのもおすすめです。
■5.後出しじゃんけん
・ここでは後出しじゃんけんなので、相手が出したものに「負ける」ようにあとから手を出す、「勝つ」ようにあとから出すなど条件に合う手を出していきます。
難易度をあげたい場合は、「左右それぞれに異なる条件を出す」、「スピードを上げてみる」など利用者さんにあわせて変更が可能です。
■6.腕伸ばしじゃんけん
・はじめは情報量が多くなるので「グー」と「パー」のみで練習をするなどがよいでしょう。
実際にじゃんけんをするとなると、難易度が高いため利用者さんの様子を見つつ、進めるようにしましょう。難しいものに無理に挑戦させることは利用者さんの自尊心を損ないます。
■道具を使う手遊び

■7.あやとり
(細い紐や、硬い紐は利用者さんの手を傷つける可能性があるため、毛糸などがおすすめ)
・1人でつくることが難しい場合、2人で協力して実施できる方法もあります。
作るものによって難易度の調整ができます。利用者さんの指先の動きなどを確認しつつ、まずは簡単なものから始めるようにしましょう。
■8.お手玉
(数は1人2~3個を目安に用意しましょう)
・上に投げている間に、空いた手に反対の手にあったお手玉を移します。
慣れてきたら、お手玉の数を増やしてみたり、歌を歌いながらやってみると難易度を調整することができます。
■音楽に合わせた手遊び

■9.むすんでひらいて
・「むすんで」:手をグーにする
・「開いて」:手をパーにする
・「手を打って」:両手で拍手をするように手を打つ
・「むすんで」:手をグーにする
・「また開いて」:手をパーにする
・「手を打って」:両手で拍手をするように手を打つ
・「その手を上に」:腕を腕にあげバンザイするようなポーズをとる
麻痺などで、人によっては難しい動きを含まれています。利用者さんにとって無理がない範囲で実施をしましょう。
■10.おちゃらかほい
・「おちゃらか おちゃらか おちゃらか」:リズムにあわせ自分の右手を自分の左手の甲の上→自分の右手を相手の左手の甲の上と交互に繰り返します。
・「ほい」:このタイミングでグー・チョキ・パーのいずれかを出し、じゃんけんをします。
・「おちゃらか」:リズムにあわせ自分の右手を自分の左手の甲の上→自分の右手を相手の左手の甲の上と交互に繰り返します。
・「勝ったよ(負けたよ)(あいこで)」:勝った人はバンザイ、負けた人はしょんぼりおじぎ、あいこのときは両手を腰にあてます。
・「おちゃらかほい」:リズムにあわせ自分の右手を自分の左手の甲の上→自分の右手を相手の左手の甲の上と交互に繰り返します。
最後の「おちゃらかほい」のあとはもう一度じゃんけんをし、飽きるまで繰り返すということもできます。場の盛り上がりを確認し、あわせて対応しましょう。
■11.あんたがたどこさ
・あんたがたどこさの曲に合わせて両手を叩きます。
・「さ」が出てきたときは、自身の手ではなく相手とハイタッチをします。
・これを「さ」が出てくるたびに繰り返します。
曲のスピードなどで難易度の調整ができます。力を入れすぎると利用者さん同士のトラブルにもなりかねないので、力加減等は注意をするようにしましょう。
■12.ちゃつぼ
・片手を「グー」にして茶つぼに見立てます。
・反対の手を「グー」の上にかぶせ、蓋にします。
・次に、曲のテンポに合わせて「グー」の下に手を移動し、お皿にします。
・この動作が終わったら次は手を逆にして同じ動作をします。
動作に慣れてきたらスピードをあげて難易度の調整を行いましょう。
高齢者向けに手遊びを取り入れる際のポイント
2.難易度を少しずつあげる
3.コミュニケーションを意識する
■1.毎日行えるように隙間時間を利用する
施設などでは、空いた時間で実施ができると暇つぶしにもなるため、利用者さんたちはより楽しんでくれるかもしれません。
■2.難易度を少しずつあげる
■3.コミュニケーションを意識する
一方で、簡単であるからこそ単調になりがちです。利用者さんに声をかけたり、一緒に盛り上がったりする工夫が大切です。
【専門家のコラム】認知症を予防するには
■執筆者/専門家
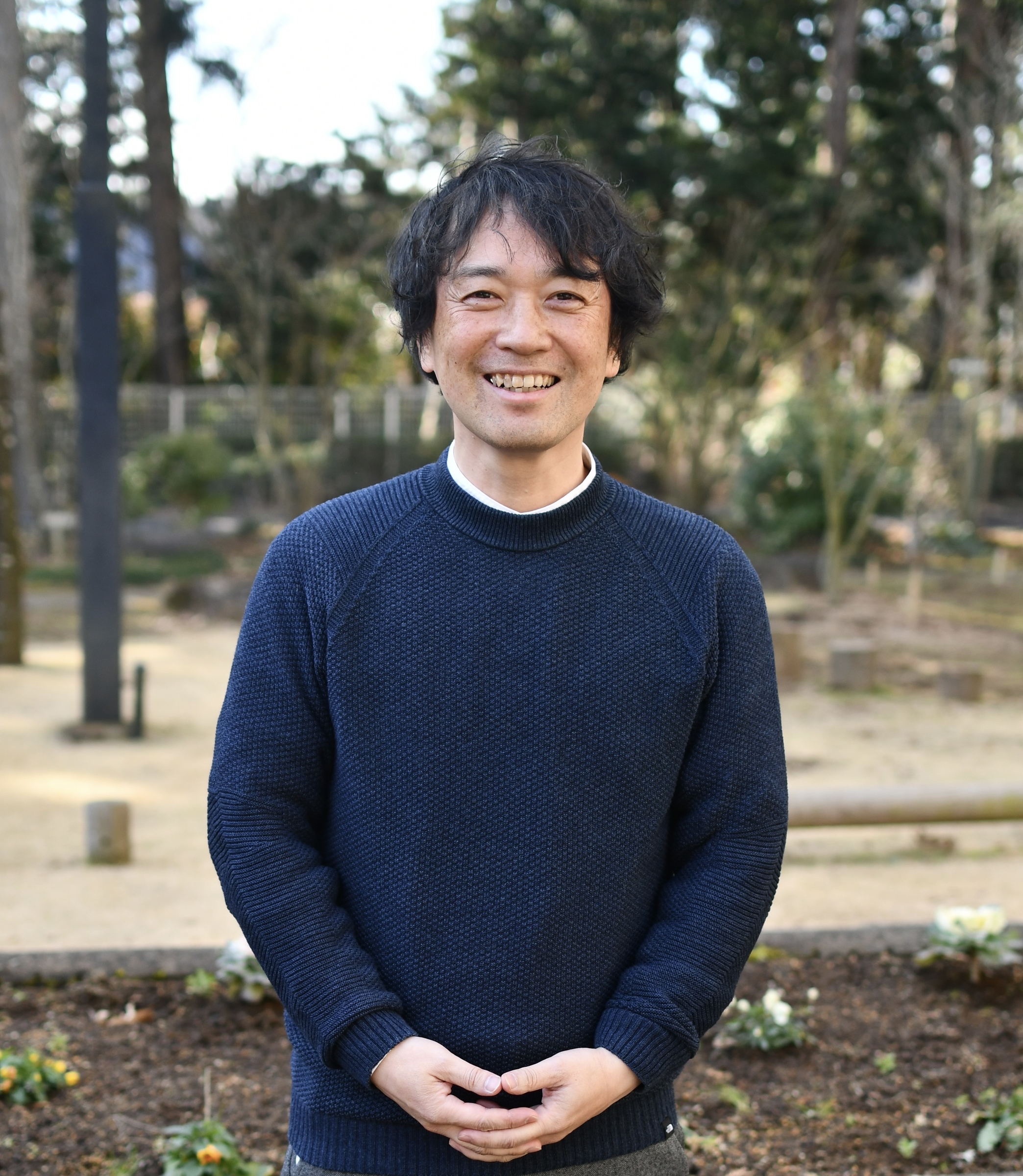
茨城県介護福祉士会副会長 特別養護老人ホームもくせい施設長 いばらき中央福祉専門学校学校長代行 NPO法人 ちいきの学校 理事 介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント 介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員 MBA(経営学修士)
●1日3杯コーヒーを飲む(新潟大学医学部発表)
●良質な睡眠をとる(脳の老廃物を洗い流す)
などの方法が明示されているものの、まだまだその効果が明確とは言えないようです。
しかしながら、脳の活性化に関しては、脳を使わない人より使う人の方が認知症のリスクを軽減させるケースが科学的に立証されています。
脳の活性化という意味では、後出し負けジャンケン(利き手でない手で相手に負けるようにジャンケンをする)は、普段使わない手で直感的には勝とうとしてしまう脳に逆の考え方をさせるという脳とって効果的な介護予防になりうる「手遊び」かもしれません。
ただし、この「手遊び」という考え方、毎日同じものの繰り返しでは利用者さんのニーズと嚙み合わなくなってしまいます。
■利用者さんのニーズの変化により、レクリエーションの内容も進化している
※団塊の世代…(終戦直後1947〜1949年生まれ、75〜77歳)
これらの年代の方は、高度経済成長、バブル経済、核家族への移行などを経験しており、娯楽も整った時代を生きてきました。
そのため、趣味・趣向の質も高く、レクリエーションという感覚よりもより質や効果を求める傾向へ変化しています。
最近は、昭和歌謡がブームになっていますが、まさしく昭和時代のオンタイムの人々です。
当時の曲ってとても質が高いですよね。
昭和の時代の世代は質の高い娯楽のなかで生きてきた世代ということなのです。
実際に最近、流行っているデイサービスをみてみると、
●本格的なカルチャーの先生がいる
●リハビリの専門職がいる など
ご利用者のニーズとサービスの質がマッチしているところのように感じます。
そのため、手遊びなどのレクリエーションを行う際は、さまざまな種類のものを工夫しながら実施することが大切です。
まとめ:「人と話すこと」が脳の活性化に効果的
そして、直接的に認知症を予防できる方法もまだ確立されてはいません。
そのなかで、認知症を予防するためには、生活習慣病を防ぐ、脳を活用することは効果的と言われています。 最近の研究では、計算問題のようなよくある脳トレより「人と話すことと」が脳の活性化にはより効果的という話も出ています。
レクリエーションを利用者さん同士の会話のきっかけとし、施設内で、利用者さん同士が関わる機会を増やしていけるようにしましょう。
■あわせて読みたい記事

高齢者向け脳トレゲーム25選! 脳トレの目的や実施時のポイントも解説 | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1155介護施設で行われているゲームや計算問題など脳トレは、高齢者の脳を活性化して認知機能を鍛えるほか、認知症予防にもつながるといわれています。脳トレの目的や実施する際のポイントとともに、具体的なアイデアと方法を紹介します。【執筆者:ささえるラボ編集部】

認知症の人向けのレクリエーション26選! 効果や押さえておきたいポイントも解説 | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1131レクリエーションは認知症の人にも好影響をもたらしますが、実施する際には認知症の人に適した内容を考える必要があります。認知症の人へのレクリエーションの効果や押さえたいポイント、具体的なレクリエーションのアイデアを紹介します。 【執筆者:ささえるラボ編集部】
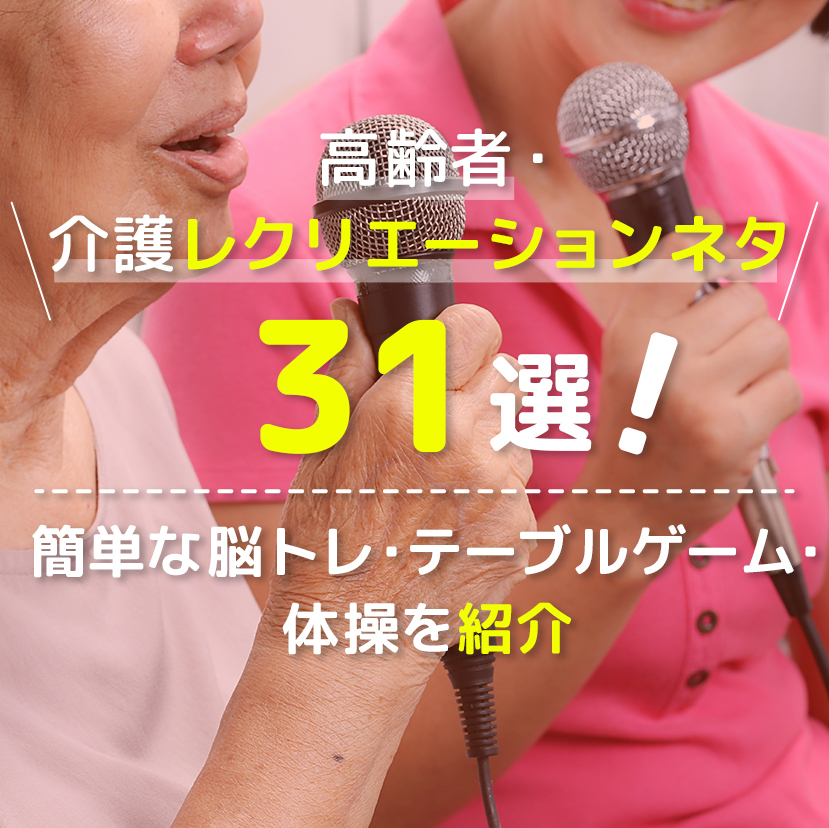
高齢者レクリエーション31選!道具なしでも簡単にできるゲームや盛り上げるコツをご紹介 | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/750[2024年9月更新]介護施設で実施されるレクリエーションには、利用者を楽しませ、身体機能を維持するという目的があります。レクリエーションの目的や種類、注意点といった基礎知識とともに、簡単にできる脳トレ・ゲーム・体操の具体例を紹介します。【監修者/専門家:後藤 晴紀】

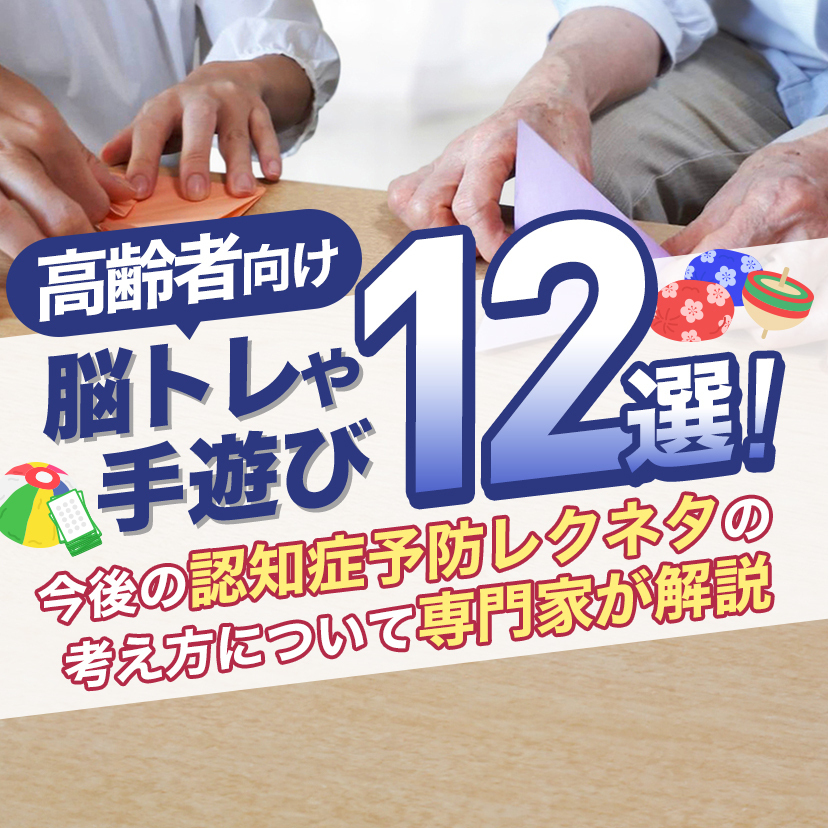


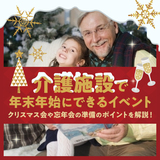
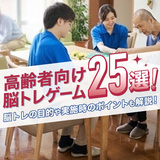










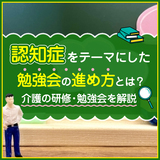














茨城県介護福祉士会副会長
特別養護老人ホームもくせい施設長
いばらき中央福祉専門学校学校長代行
NPO法人 ちいきの学校 理事
介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント
介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員 MBA(経営学修士)