■執筆者

ささえるラボ編集部です。 福祉・介護の仕事にたずさわるみなさまに役立つ情報をお届けします! 「マイナビ福祉・介護のシゴト」が運営しています。
今回は、介護施設でレクリエーションとして実施したい脳トレのアイデアと方法を紹介。あわせて、脳トレの目的、実施する際のポイントや注意点、利用者に楽しんでもらうコツについても解説します。
脳トレを実施する目的
◆コミュニケーションの活性化
◆ストレス発散
■認知機能の維持・向上
脳トレを行うと、脳の前頭前野が刺激されて活性化されるため、認知機能の低下防止や改善につながると考えられていて、幅広い介護施設でレクリエーションとして取り入れられています。
■コミュニケーションの活性化
介護施設では、複数の利用者を集めて脳トレを実施するのが一般的です。仲間といっしょにクイズやゲームをすると、コミュニケーションの機会が増え、楽しみや生きがいにつながります。仲間や担当の職員と会話を交わすことで、脳も刺激されます。
■ストレス発散
また、頭を使いながら脳トレを行いクイズや計算問題に正答することで、達成感や心地よさがもたらされ、日々の充実につながるというメリットもあります。
脳トレゲームを企画・実施する際のポイント
◆幅広い種類の脳トレを取り入れる
◆簡単にできる内容にする
◆仲間といっしょにできるものを選ぶ
◆余裕のある時間設定にする
◆参加者に合わせた内容にする
◆参加者の気持ちを傷つけない
■できるだけ継続して行う
■幅広い種類の脳トレを取り入れる
そうすることで、複数の認知機能を活用することができます。
■利用者が達成感を得られる内容にする
そのほかのゲームは、ルールや遊び方が理解しやすいものを選びましょう。
■仲間といっしょにできるものを選ぶ
レクリエーション中は、参加者同士が円滑にコミュニケーションをとれるように、様子を見ながら声をかけてサポートをすることも、職員の大切な役割です。
■余裕のある時間設定にする
焦らずに脳トレに取り組めるように、参加者の認知機能レベルを考慮して、余裕のある時間配分で予定を組みましょう。
■参加者に合わせた内容にする
また、参加者のなかには体が思うように動かせない人や車椅子の人もいるため、特に手遊びや体操などは、参加者の体の状態に合わせた内容にすることが大切です。
さらに、どんな認知機能を鍛えられる脳トレなのかに着目すると、より目的や参加者に合ったレクリエーションを実施することができるでしょう。
■参加者の気持ちを傷つけない
たとえば問題が全部解けなかったときに、「あと少しだったのに、残念」と言えば、参加者は能力不足を指摘されたように感じて自信をなくすかもしれません。そのほか、強い口調での指示出しやほかの利用者と比べるような発言も、参加者の気持ちを傷つける原因になります。
常に参加者の気持ちを想像しながら、「うまくできていますよ」「今日もがんばりましたね」などと、ポジティブな声かけを心がけましょう。ゲームのルールや方法などを教えるときは「次はこうしませんか?」「こうしたらもっとよくなりますよ」と提案する言い方で伝えるとよいでしょう。
脳トレゲームのアイデア25選

2.計算力アップ脳トレ
3.注意力アップ脳トレ
4.思考力アップ脳トレ
5.脳トレ効果のある手遊びや体操
■1.記憶力アップ脳トレ
脳トレで思い出す力を中心にトレーニングすることで、記憶力の低下を防ぐ効果が期待できます。実施する際には、必要に応じて紙やホワイトボードを活用しましょう。
◆しりとり
ただし、何の縛りも加えずに行うと少し退屈に感じる参加者もいるかもしれません。全員に楽しんでもらうためにお題を決めるなどの工夫もしてみてください。
・「ごま」「まり」「りんご」などしりとり言葉が書かれた紙を10回ほど用意し、参加者に頭文字と語尾がつながるように並べてもらう
◆神経衰弱
ただし、トランプを使った一般的な神経衰弱は、記憶力や視力が低下した高齢者には難しい場合があるので、カードを準備する際は工夫をしましょう。
・職員がオリジナルのイラストを描いたカードを作る(一般的なトランプだと絵柄も多く高齢者には難易度が高い場合がある)
・一般的なトランプより大きいカードを用意する(視力が低下した方も楽しむため)
◆漢字クイズ
・四文字熟語の一文字を空白にして当てはまる漢字を考えてもらう
・難しい熟語の読み方を当ててもらう
◆ことわざクイズ
・4択問題を作って解答してもらう
◆クロスワードパズル
パズルの素材は、インターネットでダウンロードできるほか、多数のクロスワードパズルを収録した本や雑誌もあります。施設でレクリエーションとして実施する場合、各自にプリントを配って解いてもらうこともできますが、そのほかにも様々な工夫をすることで仲間と盛り上がることができるでしょう。
・プロジェクターで映写するなどして参加者全員で共有し一体感を楽しむ
・職員がヒントを読み上げて、当てはまる言葉を思いついた人から手を挙げて発表してもらう
◆都道府県クイズ
・あまり知られていない都道府県を出すなどで難易度の調整を行う
・参加者同士の会話が弾むよう、参加者の出身地である都道府県を出題する
◆昭和クイズ
記憶力アップに加えて、「回想法」と呼ばれる心理療法と同様の効果が期待できます。「回想法」は、思い出の品や昔流行した音楽などを手がかりに、高齢者から話を引き出すという方法で行われます。
昔を思い出すことで脳を活性化させるとともに、自信を取り戻すきっかけになり、精神に安定をもたらすといわれています。
・昭和時代の消費税は何%だったでしょう。
◆歌クイズ
記憶力アップにつながるのはもちろん、昔を思い出すことで「回想法」と同様の効果も期待できます。
・職員が歌詞の冒頭だけを読み上げ難易度をあげる
・曲名を当てた人にその歌を歌ってもらう
・正解が出た後にその曲をスピーカーで流す
■2.計算力アップ脳トレ
◆足し算・引き算
・計算力が高い人もいるので難易度の幅は広く準備しておく
・大きめの文字で数字を書くことで高齢者に見やすいようにする
◆そろばんを使った計算問題
・事前に参加者がそろばんを使えるか確認しておく
・そろばんより電卓を使い慣れている場合があるのでその場合は電卓も用意する
◆お金の計算問題
・値札のついたさまざまな品物を用意し「5,000円以内で好きなものを買う」など買い物感覚で計算をしてもらう
◆時間の計算問題
参加者の認知レベルに合わせて問題の難易度は調整しましょう。
◆サイコロを使った計算ゲーム
さまざまなゲームのアイデアが考えられ、使用するサイコロの数などで参加者に応じて難易度の調整ができます。
・サイコロを振るたびに出た数をホワイトボードや用紙などに記録し、最後に参加者全員で合計数を足し算してもらう
■3.注意力アップ脳トレ
どんなゲームであっても、一定の時間、集中的に取り組むことは注意力アップにつながりますが、なかでも次のようなゲームが効果的です。
◆間違い探し・仲間はずれ探し
素材はインターネットや本でも探せますが、参加者がより盛り上がるために他にも以下のような工夫ができます。
・担当の職員が手作りする
・大きめにプリントして掲示したり、プロジェクターを使ってスクリーンや壁に映したりして参加者間で共有できるようにする
◆点つなぎゲーム
点と点をつなぐ際には鉛筆で線を引く必要があり、頭と同時に手も動かすので、より広範囲に脳を刺激することができます。間違い探し、仲間はずれ探しと同様、インターネットや本から素材を入手することができます。
・数字やアルファベットの数を増やすことで難易度の調整ができる
・各自で作業をした後にできあがった絵を全体で発表すると参加者が一体感を持つことができる
◆ジグソーパズル・図形パズル
完成形を想像しながら平面や立体の図形を組み立てる図形パズルも、手を使って楽しみながら脳を刺激できるアイテムです。注意力や想像力はもちろん、判断力、空間認識力などの認知機能を鍛える効果が期待できます。
・ピースが小さいジグソーパズルだと、人によってはつかみにくい場合があるので、ピースが大きめのパズルや高齢者向けのパズルを選ぶ
◆迷路
参加者の認知度などに応じて以下のように工夫をしてみましょう。
・動物や季節の風物などをかたどった迷路を使う
・難易度を上げるために途中で花や木の実などを拾うなどミッションをこなしながら進む迷路を取り入れる
■4.思考力アップにつながる脳トレ
◆なぞなぞ
解答する際には柔軟な発想が必要になるため、思考力や想像力が鍛えられます。また、参加者同士で会話を交わしながら答えを考えることで、コミュニケーションも活性化します。
・9匹の虎が乗っている車は?(答え:トラック)
◆回文
認知機能のレベルによっては回文を考えることは難しいので参加者が楽しめるよう工夫をする必要があります。
・職員が回文を考え、穴埋め問題にする
・文字数を認知機能のレベルに合わせて調整する
◆あいうえお作文
言葉の組み合わせによっては的はずれでおかしな文章ができることもありますが、そんなときに笑いが起こって盛り上がるのも、このゲームの醍醐味です。
「あ」味見をしたら
「さ」砂糖が多かった
「ひ」久しぶりの料理
◆文字並び替えゲーム
最初は4~5文字程度の単語で参加者の様子を見て、簡単そうなら徐々に文字数を増やして難易度を上げていきましょう。
・「キョウトウ」→「トウキョウ」
■5.脳トレ効果のある手遊びや体操
◆指体操
インターネット上にある動画やレクリエーションの本などを参考に、参加者の機能レベルに合う指体操を取り入れましょう。慣れてくれば、アレンジも可能です。
1、2、3…と数を数えながら、両手の指を順番に折り曲げていく体操
・「指回し体操」
両手の指をドームのように合わせて、向き合っている指に当たらないように指を1本ずつ回していく体操
◆後出しじゃんけん
簡単そうに思えますが、実際にやってみると意外と難しいため、脳を十分に刺激することができます。ほかの参加者とテンポを合わせて手を上げることで、適度な運動にもなります。
2.職員は「じゃんけんぽん」と言いながら、グー・チョキ・パーのいずれかを出す
3.参加者は職員からの指示通りに「ぽん」と言いながらグー・チョキ・パーのいずれかを出す
◆お手玉
2つのお手玉を両手に持って、右手で一つを上に投げ、左手からもう一つお手玉を右手に移して、落ちてきたお手玉を左手で受けるという動きを繰り返すのが基本の遊び方です。最初は簡単な技から始めて、参加者の様子を見ながら、より難易度の高い技にもチャレンジしてみましょう。
・お手玉の数はある程度多めに準備しておく
→基本の遊び方で難易度を上げることができる
→「的当て」や「玉入れ」、参加者が円座になって一人一人が持っているお手玉を回していく「お手玉回し」など遊びの幅を広げられる
◆足踏み体操
座ったままで下肢の運動機能のトレーニングができるうえ、脳内のほかの脳トレでは刺激できない部分を刺激できるのがメリットです。
・参加者の認知度や身体機能などに応じて指折り体操や手遊びを組み合わせることも考えて準備をしておく
高齢者に脳トレゲームを楽しんでもらうコツ

2.ルールや目的をわかりやすく説明する
3.様子を見ながら声かけをする
4.職員自身も楽しむ
■1.準備をしっかりしておく
そのうえで、頭のなかでゲームの開始から終了までの流れをシミュレーションして、練習や休憩タイムをどこで挟むかなどの計画を立てておきます。
トラブルや事故のリスクを考慮して、安全対策を講じておくことも重要です。
■2.ルールや目的をわかりやすく説明する
また、参加者のなかには、しりとりやクイズ、初歩的な計算問題といった脳トレに対して「なぜこんな子どもの遊びのようなゲームをしなければいけないのか」と抵抗を感じる人もいます。そんな人にも前向きにレクリエーションに参加してもらうためには、その日に実施する脳トレの目的や効果を説明することも必要です。
■3.様子を見ながら声かけをする
担当職員が一人ひとりの様子を観察しながら声かけをして、できる限り全員が脳トレゲームを楽しめるように配慮をして、ムードを作りましょう。
■4.職員自身も楽しむ
まとめ:参加者に合った脳トレを選び、楽しいひとときを
脳トレの多くは、必要な道具を用意すれば手軽に実施できるため、レクリエーションに慣れていない介護職にも実施しやすいでしょう。職員に多数の脳トレのレパートリーがあれば、さまざまな認知機能のトレーニングになるうえ、施設の利用者に飽きずに楽しんでもらうことができます。
今回紹介したアイデアを参考に、利用者の興味や心身の状態に合った脳トレのレクリエーションを企画しましょう。
■あわせて読みたい記事
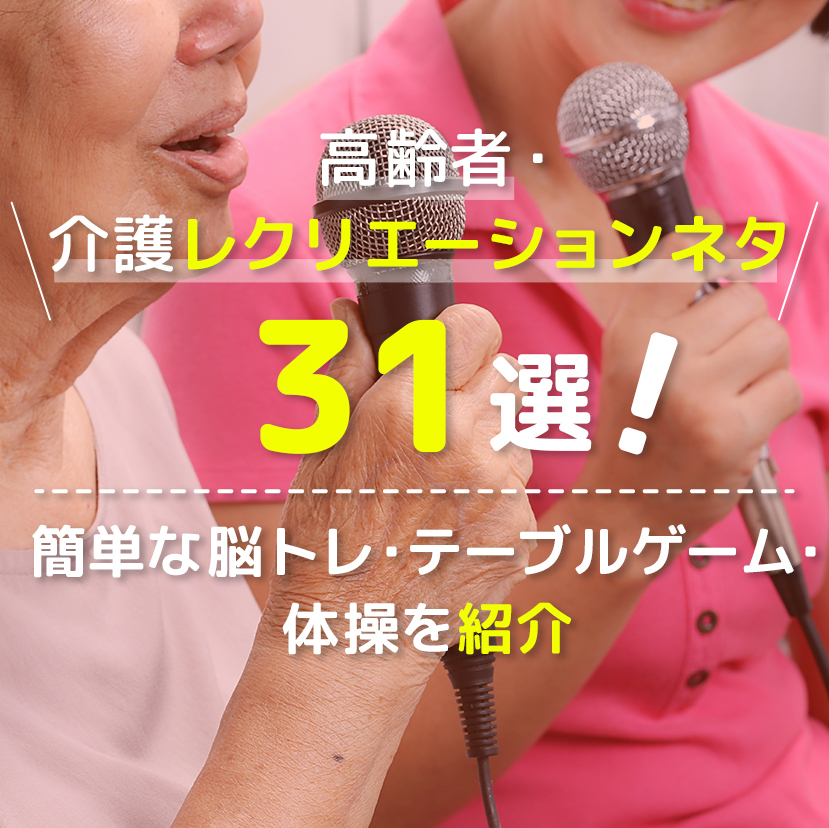
高齢者レクリエーション31選!簡単な脳トレ・テーブルゲーム・体操を紹介 | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/750[2024年1月更新]介護施設で実施されるレクリエーションには、利用者を楽しませ、身体機能を維持するという目的があります。レクリエーションの目的や種類、注意点といった基礎知識とともに、簡単にできる脳トレ・ゲーム・体操の具体例を紹介します。【監修:介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員 後藤晴紀】

認知症の人向けのレクリエーション26選! 効果や押さえておきたいポイントも解説 | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1131レクリエーションは認知症の人にも好影響をもたらしますが、実施する際には認知症の人に適した内容を考える必要があります。認知症の人へのレクリエーションの効果や押さえたいポイント、具体的なレクリエーションのアイデアを紹介します。 【執筆者:ささえるラボ編集部】




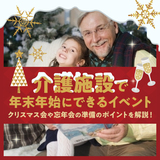

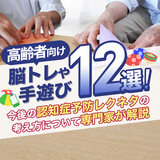









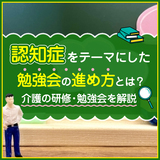














ささえるラボ編集部です。
福祉・介護の仕事にたずさわるみなさまに役立つ情報をお届けします!
「マイナビ福祉・介護のシゴト」が運営しています。