第32回 介護福祉士国家試験 過去問と解説(社会の理解)
■問題1
地域包括ケアシステムでの自助・互助・共助・公助に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 自助は、公的扶助を利用して、自ら生活を維持することをいう。
- 互助は、社会保険のように制度化された相互扶助をいう。
- 共助は、社会保障制度に含まれない。
- 共助は、近隣住民同士の支え合いをいう。
- 公助は、自助・互助・共助では対応できない生活困窮等に対応する。
■解答
5.公助は、自助・互助・共助では対応できない生活困窮等に対応する。
■解説
1.(×)自助とは、自身が抱える課題を自らの力で解決することを意味します。
2.(×)互助とは、公的・制度的な裏付けのない自発的な個人間の支え合いです。
3.(×)共助は、社会保険のように相互の支え合いが制度化されたものです。日本には、5つの社会保険制度(医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険)があります。
4.(×)家族、友人、仲間、近隣住民同士の支え合いは、互助に該当します。
5.(○)公助とは、公的機関による援助であり、税金で成り立つ社会福祉制度です。生活保護は、生活困窮者が健康で文化的な最低限度の生活を送れるように必要な保護を行うものであり、公助に該当します。
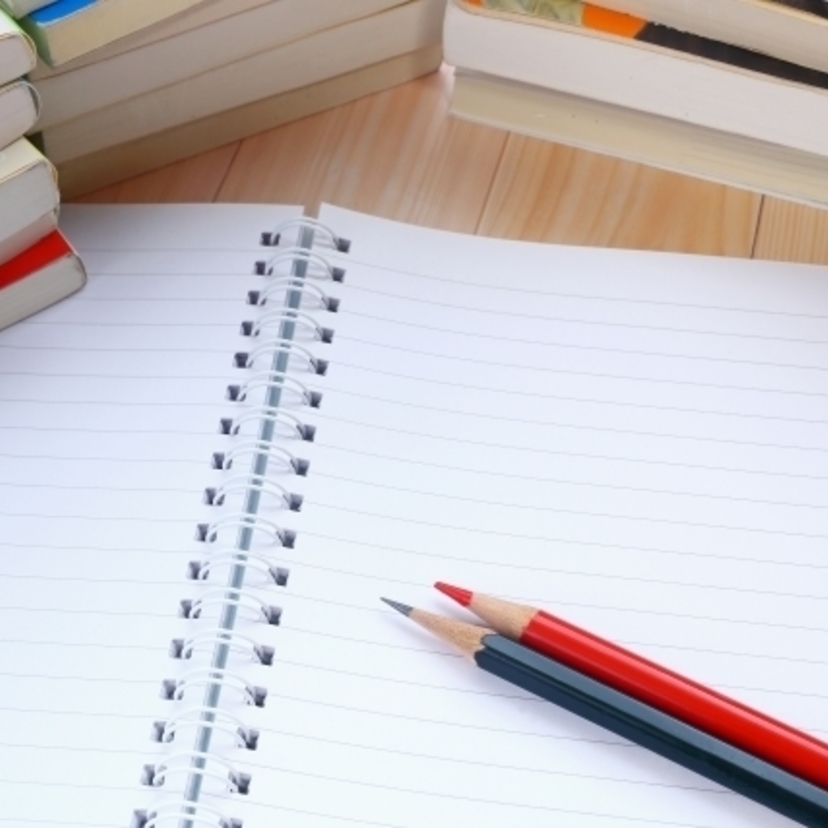



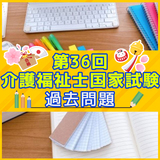
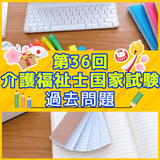
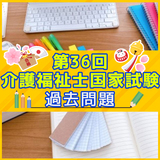









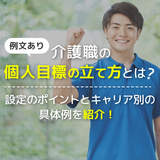












ささえるラボ編集部です。
福祉・介護の仕事にたずさわるみなさまに役立つ情報をお届けします!
「マイナビ福祉・介護のシゴト」が運営しています。