誤薬の怖さを新入職員に伝えるには?3つの方法を解説!

執筆者
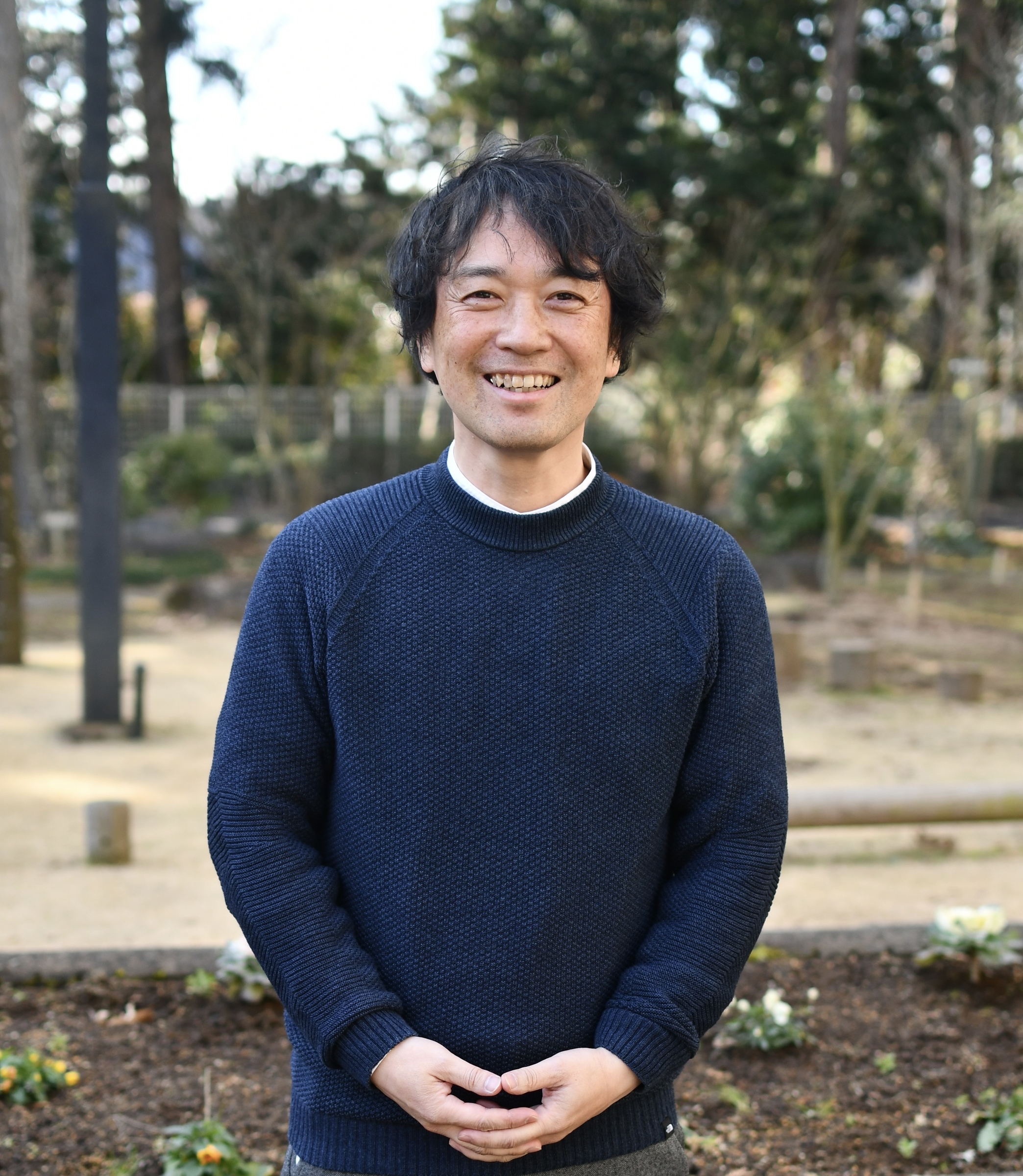
茨城県介護福祉士会副会長 特別養護老人ホームもくせい施設長 いばらき中央福祉専門学校学校長代行 NPO法人 ちいきの学校 理事 介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント 介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員
まもなく4月ですね。
新人さんを迎える時期が間近に迫って参りました。
また、心機一転、新年度から新たな職場で頑張ろうという中途採用の方もいらっしゃるのではないかと思います。
しかしながら、各事業所さんにおかれましては、迎え入れる準備が万端ですというところもあれば、もしかしたら体制に少し不安感を抱いている事業所さんもあるのではないでしょうか。
■誤薬防止のプロセスには、介護の本質が表れている
そのような中で、今回のテーマである「誤薬」については、入社時に必ずやらなければいけないと法令で決められている「身体拘束・虐待防止研修」と並び、私は必ず実施すべき研修と考えています。
なぜなら「誤薬防止」のプロセスは、介護の本質的な要素がほぼ入っていると言っても過言ではないからです。
ではどういった点を研修すればいいのか?
実際、私の法人で実施している研修を実例として皆様にお伝えしたいと思います。
■研修で伝えること① 「自分だったら」に置き換える習慣化
自分が薬を飲むときのプロセスを見える化しよう
私たちは、生活の中で市販薬等の薬を当たり前のように飲んでいます。
もちろん病院から処方された薬を飲むと言うことも皆さん経験がおありでしょう(私自身、この時期、花粉症の薬なしでは生きていけません笑)。
ここで皆さんに質問です。
薬を服薬する時、これは何の薬なのかを確認せずに飲む方はいらっしゃいますか?
「なんか調子が悪いから、ここに白い錠剤があったのでとりあえずよくわかんないけど飲んどくか・・・」とはなりませんよね。通常、薬局に行って症状改善に効果がありそうな薬を購入して服薬する。または、薬局の薬剤師さんに相談する、もしくは、医師から処方された薬を薬局で説明を受けた上で購入し、服薬するという流れではないでしょうか?
そのプロセスを、まずは分解して見える化することが大切です。
薬に対する意識を高く持つために
誤薬が起きる原因は第一に「薬に対する意識の低さ」です。自分が飲むときは確認をするのに、人に飲ませるときは確認をしない。そのため、誤った薬を飲ましてしまう、または飲ませ忘れてしまう。
まず、自分だったらどうなのか?という形で常に置き換えて考えることを習慣化することが大切です。
■研修で伝えること② 体のメカニズムを理解する
誤った薬を服用させてしまったら…と考えてみよう
「もし、誤って薬を服用させてしまったら・・・」その危険性を考えます。
高齢者によくある薬を考えてみましょう。高齢者の特徴としては、高齢、または病気により、内臓機能が衰えます。この衰えを補うことが薬の目的となるでしょう。
例えば、心不全と高血圧の薬を間違えた場合は?
例えば心不全であれば心臓の動きが悪くなってくる=血の巡りが悪くなってくれば、体のむくみが出てきて、心身の不調をきたすと共に行動の制限にもつながっていきます。
この状況下で、血の巡りを良くするお薬を飲ませ忘れれば、場合によってむくみの悪化等身体への悪い影響がでる可能性も考えられるでしょう。
また、血圧が高い(高血圧)の方は、血圧を下げる降圧剤を服用していることがあります。
もしこの降圧剤を血圧の低い方に服薬させてしまった場合は、さらに血圧を下げることになってしまうことにもなりかねません。
そういった状況は生命の危険にもなり得る事はこのメカニズムを考えればわかると思います。
ということで、誤薬を通して人間の体の仕組みを理解する、または、人間の体の仕組みを理解して誤薬に取り組むという研修を行うことができます。
■研修で伝えること③ オペレーションの改善法を学ぶ
誤薬が起きた理由を分析し、オペレーションを改善しよう
誤薬がおきてしまった場合、どうすれば良いのでしょうか?
仕方ないではすませません。なぜ、おきてしまったか?という分析が必要です。
「あるフロアで誤薬事故が発生した」という場合
・それはいつどこで誰だったのか?
例えば、看護師さんが薬を配布する段階で間違ってしまっていたのか、それとも介護職が名前を確認ミスして飲ましてしまったのか?
・ご本人が服薬するというところをしっかりサポートしきれずに実は飲んでいなかったのか?
一つひとつ、なぜそういうことが起きてしまったのかの原因をしっかり分析しましょう。
誤薬防止の取り組みは、組織マネジメントに繋がる
その過程で、誤薬を職員の個人的問題として片付けるのでなく、組織全体の課題として解決しなければならないことも学べます。
つまり、オペレーションの改善です。
私たちは何のために誤薬の撲滅に取り組むのか?「ご利用者の健康な生活や生命を守るため」です。この目的のためにみんなで取り組むことが誤薬ゼロへのプロセスになります。つまり、組織マネジメントということですね。
いかがでしょうか?
このようにただ「誤薬はいけないよ」と言うのではなく、3つの視点から捉えると「介護の本質」を学ぶことにも繋がりませんか?
よろしければ、自事業所の新人研修を振り返り、ご活用いただければ幸いです。
「誤薬」に関連したお悩み
夜勤明けの人が朝食時に薬の介助をするのですが、誤薬が多すぎて悩んでいます。
他の施設では、どのような防止策を取られていますか?
相談者:アッキー さん
誤薬発生のリスクはプロセスの抜け落ちにあり
ご質問ありがとうございます。
誤薬は怖いですよね。
例えば、低血圧の方に、降圧剤を服用させてしまった場合、命にかかわります。
逆に、高血圧の方への降圧剤の服用を忘れることで、心臓病や脳卒中の発症リスクが高まる可能性もあります。
質問から夜勤の職員さんがいらっしゃるようですので、入所施設(特養?老健?グループホーム?有料老人ホーム?)でしょうか。
入所施設をご利用する利用者さんへの誤薬は、なおさらリスクが高まります。
そのような状況にしっかり危機意識を持たれ、なんとか改善を図りたいというお気持ちのあるご質問者さんのヒントとなる回答になれば幸いです。
■4つの思考プロセスで考える、誤薬の防止策
プロセス1 誤薬の定義を分解し課題を特定する。
ご質問では「誤薬が多すぎて悩んでいます」とあります。
しかし、質問者さんの意図する誤薬とはどんな状態でしょうか?
誤薬を分解すると、
(1) 他の利用者の薬を間違えて与えた
(2) 薬の投与量を間違えた
(3) 与薬もれ(落薬の発見によるものを含む)
(4) 指定時間を間違えて投与(朝食時のものを昼食時に与えたものなどを含む)
の4項目に定義できます。
夜勤明けの人が朝食介助で行ってしまう誤薬はどの項目が多いのか?統計をとってみるとことをオススメします。
どの項目が多いかにより対応策は変わってきますよね。
まずは、ぼんやりした課題から一歩課題を特定しましょう。
プロセス2 原因分析
誤薬に関わる夜勤明けの人(職員)の経験年数は平均どのくらいですか?
誤薬はどんな状態(風土、人間関係等)のユニット(フォロアー)で起きていますか?
そもそも、誤薬を起こしているのは特定の人ではないですか?
また服薬手順通りの介助が実施されていたのでしょうか?・・・。
このような形で原因を分析します。これは、シンプルに5W1Hにそった方法です。
when(いつ:朝食時)、where(どこで:ユニット)、who(誰が)、how(どのように)、what(何を:特定された誤薬)
プロセス3 解決策の立案(仮説)
特定された課題(例)を、「朝食時、Aユニットの夜勤明け者が、他の利用者の薬を間違えて服薬させてしまうことが直近半年間で4回あった」と仮定します。
原因例① 誤薬に関わる夜勤明けの人(職員)の経験年数は2〜3年目の職員だった。
→解決策:夜勤が慣れてきたことの油断が感じられる為、同程度の経験年数の職員に注意喚起となる研修を実施する。
原因例② 誤薬は特定ユニットにて、特定の職員が3回起こしていた。
→解決策:誤薬の度の指導は効果的だったのか検証する。
また、夜勤を実施するに適正な人物であるか再考する。
原因例③ いずれの誤薬も誤薬防止マニュアルに沿った手順が実施されていなかった。
→解決策:マニュアルの周知徹底(研修及び個人指導)を図り、投薬に関わる手順の標準化を図る。
また、誤薬の重大性を再度意識付ける為、組織行動の観点から施設長より強く「誤薬を組織目標として無くす」ことを宣言してもらう。
プロセス4 選択した解決策の実行、そして、評価→改善のサイクルを繰り返す。
という感じの思考プロセスを試してみてはいかがでしょうか?
■最後に
介護現場では、目の前のご利用者に集中するあまり、冷静に現実を受け止め、客観的に分析することを忘れてしまいがちです。
また、日々膨大な利用者情報を把握して業務に従事しなければなりません。
情報をインプットすることに意識が割かれ、せっかく情報をインプットしたとしても、活用する為のプロセスが抜け落ち、安易に行動してしまう傾向もあるかと思います。
実は、これがリスクなんですね。
もちろん、ご利用者ファーストは大切ですが、時に、ご利用者を守るために冷静な分析視点も重要になります。
とはいえ、何をどう分析すれば?と悩む時は、是非、4つの思考プロセスを活用してみてください。
意外とシンプルで効果的な「答え=防止策」が見つかるかもしれません。







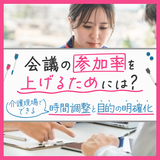






















茨城県介護福祉士会副会長
特別養護老人ホームもくせい施設長
いばらき中央福祉専門学校学校長代行
NPO法人 ちいきの学校 理事
介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント
介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員 MBA(経営学修士)