介護福祉士が行う服薬の介護に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1.服薬時間は、食後に統一する。
2.服用できずに残った薬は、介護福祉士の判断で処分する。
3.多種類の薬を処方された場合は、介護福祉士が一包化する。
4.内服薬の用量は、利用者のその日の体調で決める。
5.副作用の知識をもって、服薬の介護を行う。
1.(×)服薬時間は、医師の指示に従わなければなりません。
2.(×)薬を服用できずに残った場合は、残薬整理(処方日数の調整や飲み忘れ対策の検討など)を行うことがあるため、医療者に報告します。
3.(×)一包化するためには医師の指示が必要です。その指示に基づき、薬剤師が一包化を行います。
4.(×)薬の用量は、医師の指示に従わなければなりません。
5.(○)薬には作用と副作用の両面があり、その知識を介護福祉職も学んでおく必要があります。特に服薬後の副作用発現の有無や程度を、日常の関わりの中で観察する姿勢が求められます。
介護を取り巻く状況に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1.ダブルケアとは、夫婦が助け合って子育てをすることである。
2.要介護・要支援の認定者数は、介護保険制度の導入時から年々減少している。
3.家族介護を支えていた家制度は、地域包括ケアシステムによって廃止された。
4.要介護・要支援の認定者のいる三世代世帯の構成割合は、介護保険制度の導入時から年々増加している。
5.家族が担っていた介護の役割は、家族機能の低下によって社会で代替する必要が生じた。
5.家族が担っていた介護の役割は、家族機能の低下によって社会で代替する必要が生じた。
1.(×)ダブルケアとは、自身の子どもの世話と親の介護を同時に行っている状態を指します。
2.(×)要介護・要支援の認定者数は、介護保険制度の導入時から増加しています。
3.(×)家制度とは、戸主が家族を統率する家族制度の在り方で、戦後の民法改正で廃止されました。
4.(×)要介護・要支援の認定者のいる三世代世帯の構成割合は、介護保険制度の導入時から年々減少しています。
5.(○)三世代世帯の減少も要因の一つとして、現代では家族機能が低下しているため、介護の役割を社会で代替する必要が生じています。介護保険制度が導入されたのもそのためです。
Aさん(48歳、女性、要介護1)は、若年性認知症(dementia with early onset)で、夫、長女(高校1年生)と同居している。Aさんは家族と過ごすことを希望し、小規模多機能型居宅介護で通いを中心に利用を始めた。Aさんのことが心配な長女は、部活動を諦めて学校が終わるとすぐに帰宅していた。
ある日、夫が、「長女が、学校の先生たちにも相談しているが、今の状況をわかってくれる人がいないと涙を流すことがある」と介護福祉職に相談をした。
夫の話を聞いた介護福祉職の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。
1.長女に、掃除や洗濯の方法を教える。
2.家族でもっと頑張るように、夫を励ます。
3.同じような体験をしている人と交流できる場について情報を提供する。
4.介護老人福祉施設への入所の申込みを勧める。
5.介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービスの変更を提案する。
3.同じような体験をしている人と交流できる場について情報を提供する。
1.(×)「今の状況をわかってくれる人がいない」という訴えの根本を捉えた対応とはいえません。
2.(×)さらに家族での頑張りを促すと、負担が限界を超える可能性が高いといえます。
3.(○)設問の事例の長女のようなヤングケアラーは、特に孤立して相談できる相手がいない悩みを抱えがちです。セルフヘルプグループについて情報提供することが適切です。
4.(×)Aさんは要介護1であり、介護老人福祉施設の入所要件を満たしていません。
5.(×)介護サービスの変更は、サービス担当者会議の場で、多職種で協議して決定します。
Bさん(61歳、男性、要介護3)は、脳梗塞(cerebral infarction)による左片麻痺(ひだりかたまひ)がある。週2回訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用し、妻(58歳)と二人暮らしである。自宅での入浴が好きで、妻の介助を受けながら、毎日入浴している。サービス提供責任者に、Bさんから、「浴槽から立ち上がるのがつらくなってきた。何かいい方法はないですか」と相談があった。
Bさんへのサービス提供責任者の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。
1.Bさんがひとりで入浴できるように、自立生活援助の利用を勧める。
2.浴室を広くするために、居宅介護住宅改修費を利用した改築を勧める。
3.妻の入浴介助の負担が軽くなるように、行動援護の利用を勧める。
4.入浴補助用具で本人の力を生かせるように、特定福祉用具販売の利用を勧める。
5.Bさんが入浴を継続できるように、通所介護(デイサービス)の利用を勧める。
4.入浴補助用具で本人の力を生かせるように、特定福祉用具販売の利用を勧める。
1.(×)自立生活援助は、一人暮らしをする障害者を対象に、生活上の困り事の相談を聞き、独力で解決できるように援助するサービスです。
2.(×)浴室を広げることは、居宅介護住宅改修費の対象にはなりません。
3.(×)行動援護の対象は、知的障害や精神障害で単独での行動が著しく困難であり、常時介護を要する障害者です。
4.(○)Bさんの力を生かすためにも、妻の介護負担を減らすためにも、入浴を補助する特定福祉用具の利用を勧めることが適切です。
5.(×)Bさんは自宅での入浴を希望しており、それを可能にする支援を考えます。
社会奉仕の精神をもって、住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める者として、適切なものを1つ選びなさい。
1.民生委員
2.生活相談員
3.訪問介護員(ホームヘルパー)
4.通所介護職員
5.介護支援専門員(ケアマネジャー)
民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された民間ボランティアで、社会奉仕の精神をもって担当区域の住民の生活に関するさまざまな相談に応じ、適切な支援やサービスへつなぐとともに、高齢者や障害者世帯の見守りや安否確認などにも重要な役割を果たしています。近年は民生委員の不足が慢性化しており、対策の必要性が指摘されています。
よって、1.(○)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、5.(×)、となります。
3階建て介護老人福祉施設がある住宅地に、下記の図記号に関連した警戒レベル3が発令された。介護福祉職がとるべき行動として、最も適切なものを1つ選びなさい。
1.玄関のドアを開けたままにする。
2.消火器で、初期消火する。
3.垂直避難誘導をする。
4.利用者家族に安否情報を連絡する。
5.転倒の危険性があるものを固定する。
設問の図記号は「災害種別避難誘導標識システム(JIS Z9098)」において「洪水・内水氾濫」を意味します。警戒レベル3は「避難に時間を要する人(高齢者、障害者、乳幼児等およびその支援者)」は避難すべきとされる状況です。これらのことから、介護福祉職は、対象者を高層階へ避難させる垂直避難誘導を行うことが適切です。
よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、5.(×)、となります。
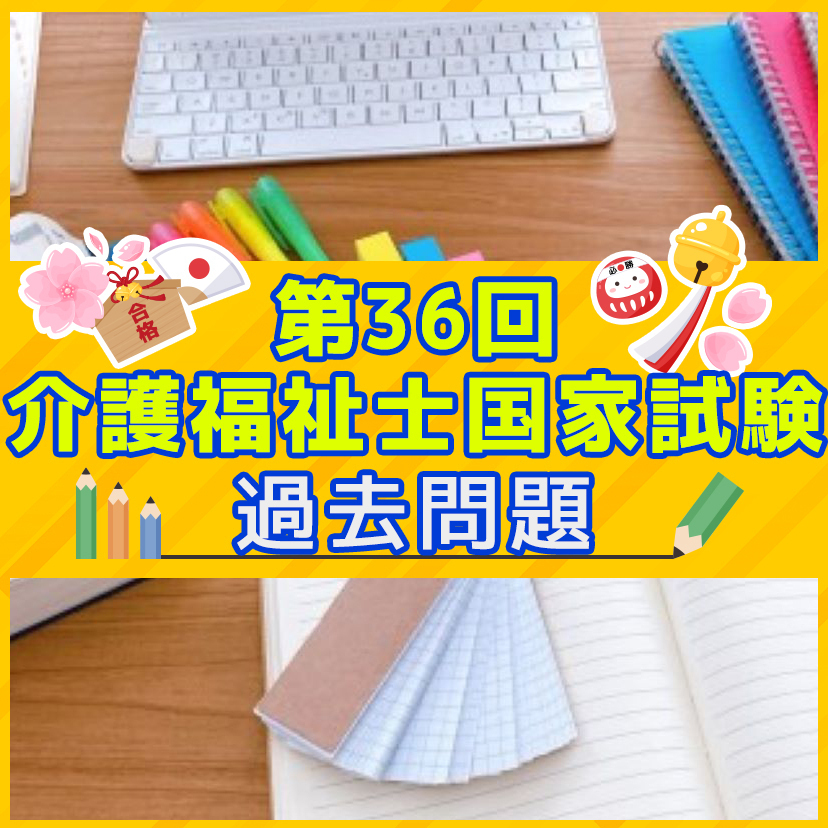




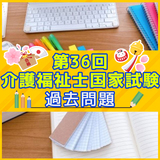
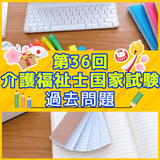
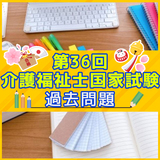
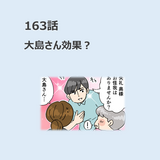


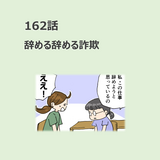

















ささえるラボ編集部です。
福祉・介護の仕事にたずさわるみなさまに役立つ情報をお届けします!
「マイナビ福祉・介護のシゴト」が運営しています。