つまり、福祉の仕事に就きたい人には、幅広い選択肢があるといえます。そこで、福祉業界を目指す人に向けて、25種の福祉の仕事を、必要な資格もあわせて解説します。
■執筆者/専門家

ささえるラボ編集部です。 福祉・介護の仕事にたずさわるみなさまに役立つ情報をお届けします! 「マイナビ福祉・介護のシゴト」が運営しています。
福祉の仕事とは
福祉の仕事には、介護職のほか、生活支援員、職業指導員、児童指導員、保育士など、さまざまな職種があります。職種によっては、業務を行うために資格が必要となる場合もあります。
専門的な知識や技術を活かして、困っている人の力になれること。そして、仕事を通じて社会に貢献できること。これらが、福祉の仕事ならではの魅力といえるでしょう。
対象者別に見た福祉の仕事の種類
高齢者向け、障害者向け、児童向けのそれぞれに特化した支援があり、職種や仕事内容も異なります。以下で、詳しく見ていきましょう。
■高齢者福祉
身体介護や生活援助を行う介護職をはじめ、介護施設の利用者さんやそのご家族の相談に対応する生活相談員、高齢者の心身の状態や課題を把握し、ケアプランを作成するケアマネジャーなど、さまざまな職種が活躍しています。
■障害者福祉
障害者施設で食事や入浴などの介助を行う生活支援員、職業訓練の指導や就業への支援を行う職業指導員などが代表的な職種です。
■児童福祉
虐待やネグレクトといった問題を抱える児童を保護することも児童福祉に含まれます。乳幼児の保育に携わる保育士、障害児の日常生活のサポートや学習指導を行う児童指導員などの職種があります。

福祉の仕事25種!仕事内容と必要な資格
■高齢者福祉の仕事
■1.介護職
チームで業務にあたる施設では、無資格でも介護職として働ける場合があります。
■2.ホームヘルパー
基本的に一人で訪問するため、初任者研修以上の資格が求められることが一般的ですが、生活援助のみを提供する場合は、無資格でも働くことができます。
■3.生活相談員・支援相談員
また、介護老人保健施設(老健)で、同様の業務を担う職種は「支援相談員」と呼びます。生活相談員・支援相談員になるには、自治体によって異なりますが、社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格のいずれかが必要とされることが一般的です。
■4.ケアマネジャー
居宅ケアマネは、要介護者の状態や希望に応じてケアプランを作成し、サービス事業者との連絡・調整を行います。施設ケアマネは、施設内で利用者さんやそのご家族の相談に対応し、ケアプランを作成します。
ケアマネジャーとして働くには、介護支援専門員の試験に合格し、実務研修を修了したうえで都道府県に登録する必要があります。
■5.サービス提供責任者
サービス管理責任者になるには、介護福祉士の資格を持っているか、介護福祉士実務者研修を修了していることが求められます。
■6.介護事務
無資格でも働けますが、介護報酬や介護保険に関する知識が必要です。民間資格を取得しておくと、就職・転職に有利であり、業務にも役立ちます。
■7.福祉用具専門相談員
この職種に就くには、「福祉用具専門相談員指定講習」の受講が必要です。ただし、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士などの国家資格を持っている場合は、講習なしでも働くことができます。
■8.介護ドライバー
普通自動車免許があれば働ける施設が多いですが、介護職が同乗しない場合は、乗降時の介助を行う必要があるため、初任者研修以上の資格が求められることもあります。
■障害者福祉の仕事
■9.生活支援員
資格要件は特にありませんが、身体介護に携わる機会が多いため、初任者研修などの介護資格を持っていると歓迎される傾向があります。
■10.世話人
資格は不要ですが、家事スキルやマルチタスクに対応する力が求められます。
■11.職業指導員
資格は不要ですが、指導する分野のスキルが求められる場合があります。
■12.障害者居宅介護従事者(ホームヘルパー)
働くためには、介護職員初任者研修以上の介護資格、または居宅介護職員初任者研修・障害者居宅介護従業者基礎研修の修了が必要です。
■13.サービス管理責任者
サービス管理責任者になるためには、障害者支援や相談業務などの実務経験を3〜8年以上積み、相談支援従事者初任者研修およびサービス管理責任者研修を修了する必要があります。必要な実務経験年数は、業務内容や保有資格によって異なります。
■14.相談支援専門員
相談支援専門員になるためには、相談支援や介護などの実務経験を3〜10年積み、相談支援従事者初任者研修を修了する必要があります。こちらも、必要な実務経験年数は業務内容や保有資格によって異なります。
■児童福祉の仕事
■15.保育士
保育士として働くには、保育士資格が必要です。資格取得の方法には、指定保育士養成施設(大学・短大・専門学校など)を卒業するか、年2回実施される保育士試験に合格するという2つのルートがあります。なお、無資格でも保育士の補助として「保育補助員」として働くことは可能です。
■16.児童指導員
児童指導員になるには、「児童指導員任用資格」が必要です。この資格は、社会福祉士や精神保健福祉士の国家資格を取得する、高卒後に児童福祉事業で2年以上かつ360日以上の実務経験を積むなど、いくつかの要件のいずれかを満たすことで得られます。
■17.放課後児童支援員
この仕事に就くには、「放課後児童支援員認定資格研修」を修了する必要があります。研修の受講には、保育士資格や社会福祉士資格を持っていること、高卒で児童福祉事業に2年以上従事した経験があることなど、いずれかの要件を満たす必要があります。なお、資格がなくても補助員として働くことは可能です。
■18.児童発達支援管理責任者
この職種に就くには、学歴や保有資格に応じて3年〜8年の相談支援業務または直接支援業務の実務経験を積み、「児童発達支援管理責任者研修」を修了する必要があります。
■医療福祉の仕事
■19.看護師・准看護師
准看護師もほぼ同様の業務を行いますが、医師や看護師の指示のもとでしか業務を行えず、自らの判断で看護を行ったり、看護計画を立てたりすることはできません。
看護師になるには、看護大学や専門学校、高等学校専攻科で3〜5年学び、看護師国家試験に合格する必要があります。准看護師資格は、中学卒業後に准看護師養成所または高等学校衛生看護科で2〜3年学び、准看護師試験に合格することで取得できます。
■20.看護助手
資格は不要で、未経験からでもチャレンジできますが、介助業務が多いため、初任者研修などの介護資格を持っていると採用されやすくなります。
■21.理学療法士(PT)
この職種に就くには、大学や専門学校などの養成機関で3〜4年学び、理学療法士国家試験に合格する必要があります。
■22.作業療法士(OT)
福祉分野では、介護施設のほか、障害者支援施設や就労支援事業所などでも活躍しています。資格取得には、大学や専門学校などの養成機関で3〜4年学び、作業療法士国家試験に合格する必要があります。
■23.言語聴覚士(ST)
高齢者のリハビリを行う介護施設のほか、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスなどで、発達障害児の支援や指導に携わるケースもあります。資格取得には、大学や専門学校などの養成機関で3〜4年学び、言語聴覚士国家試験に合格する必要があります。
■相談対応の仕事
■24.ソーシャルワーカー
活躍の場は、医療機関、地域包括支援センター、児童相談所、福祉事務所など多岐にわたります。また、介護施設で働く生活相談員や支援相談員をソーシャルワーカーと呼ぶこともあります。
ソーシャルワーカーとして働くための要件は職場によって異なりますが、社会福祉士や精神保健福祉士などの資格が求められることが一般的です。
■25.ケースワーカー
この職種に就くには、社会福祉主事任用資格を取得したうえで地方公務員試験に合格し、福祉事務所に配属される必要があります。なお、社会福祉士や精神保健福祉士の資格を持っている場合は、社会福祉主事任用資格を保有していると見なされます。
無資格・未経験から福祉の仕事につくには?

もちろん、目指す職種に必要な資格を取得してから就職・転職する方法もありますが、「まず福祉業界で働いてみたい」と考えている人は、興味のある分野や職種で、無資格・未経験OKの求人に応募してみるのも良い選択です。
実際に介護職や生活支援員として働きながら、資格取得にチャレンジすることも可能です。現場での経験を積むことで、福祉の仕事への理解が深まり、将来的なキャリアアップにもつながります。
まとめ:誰かの役に立ちたい思いが強い人は、「福祉の仕事」を選択肢の一つに
「困っている人の役に立ちたい」「利用者さんに寄り添いたい」という気持ちがある人なら、福祉の現場のどこかに、きっと自分の力を活かせる場所があるはずです。まずは福祉の仕事の種類や仕事内容を知り、自分の適性や目指す方向性を考えながら、納得のいく職場・職種を選びましょう。
■あわせて読みたい記事

介護職の仕事内容とは? 施設の種類による違いや仕事の魅力についても解説! | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1192近年、高齢者や障がい者への支援のニーズが高まるなか、社会的なニーズも高まり、将来性のある仕事として注目されている介護職。そんな介護職の主な仕事内容、施設の種類による仕事内容の違い、給与事情、仕事の魅力など、介護職の仕事に関する基礎知識を徹底解説します。【執筆者:ささえるラボ編集部】

介護業界に踏み出そう!意外と知らない業界の魅力を徹底解説! | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1173日本の高齢化に伴って、高齢者への支援のニーズは年々高まっています。介護業界で仕事をしたいけど、実際どんな業界なんだろう?とお考えの方へ。この記事では「簡単」かつ「わかりやすく」介護業界を紹介します!介護職・ヘルパーに転職をしたい方、これから働くか迷っている方、まだ興味はうすいけれど業界について知りたい方は、ぜひお役立てください!










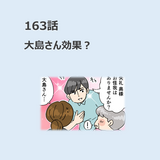


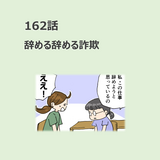


















ささえるラボ編集部です。
福祉・介護の仕事にたずさわるみなさまに役立つ情報をお届けします!
「マイナビ福祉・介護のシゴト」が運営しています。