本日のお悩み:介護施設の配置基準を3:1から4:1にすることについてどう思いますか?
賛成している人は、どのような理由で賛成しているのでしょうか?
代わりにロボットを導入するにしても全施設で対応できるほどの予算がないと思いますが…。
自分達が介護してもらう側になる時も想定した方が良い時期に来ています
■執筆者/専門家
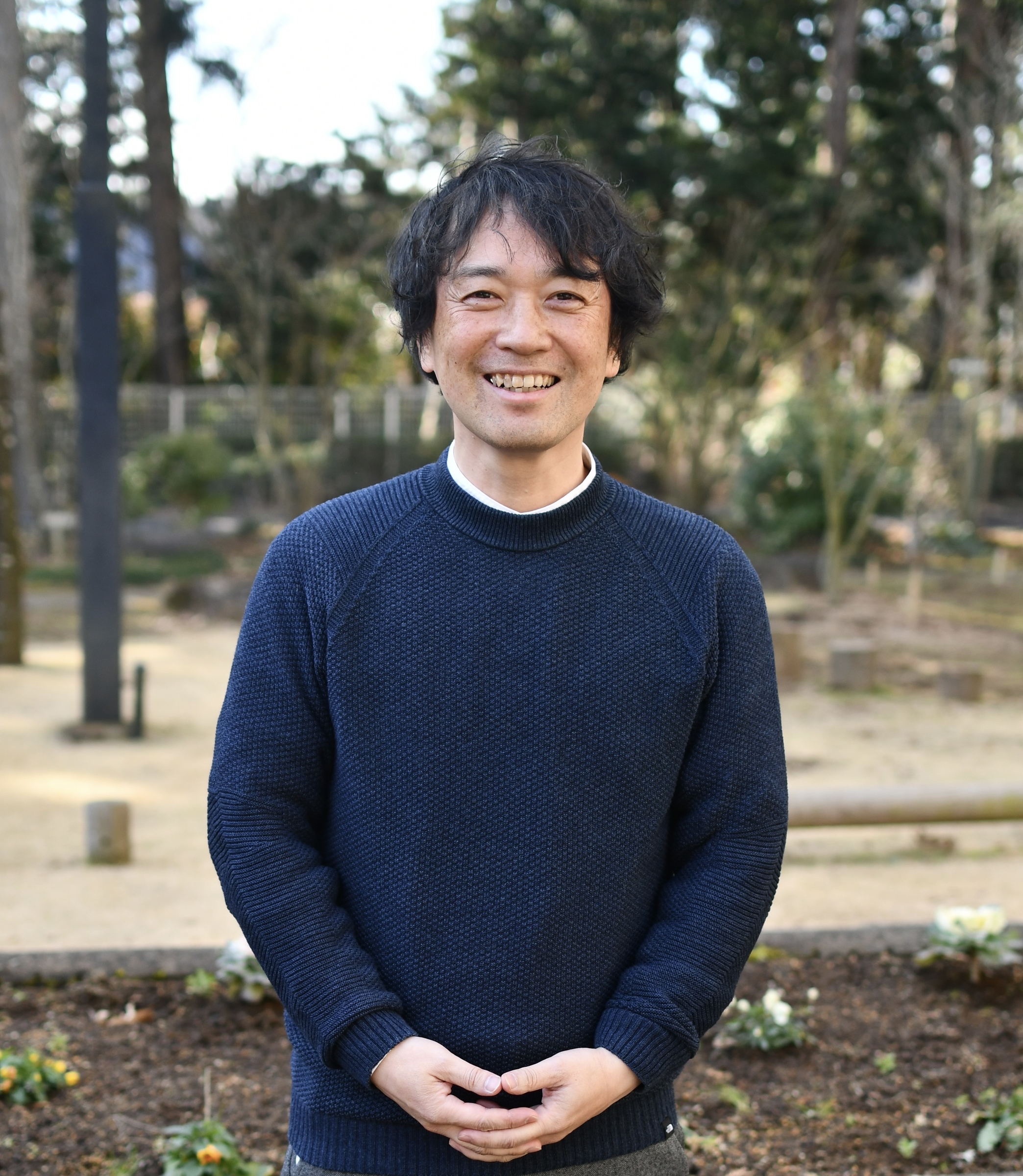
茨城県介護福祉士会副会長 特別養護老人ホームもみじ館施設長 いばらき中央福祉専門学校学校長代行 NPO法人 ちいきの学校 理事 介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント 介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員
また、「介護は人と人とのつながりが大切なのに、ロボットを導入するなんてありえない。そもそも、人の代わりになるロボットなんて存在しないじゃないか?」という叫びも耳にします。
こうした皆さんの思いには、私も深く共感しています。それでも、私はこの提案の方向性には賛成の立場です。その主な理由は以下3つです。
・賛成理由2:介護人材不足は、間違いなくこれから更に顕著になるから
・賛成理由3:チャレンジする組織に介護現場が変わらなければならないから
■賛成理由1:そもそも「配置基準を4:1にする」でなく「4:1を可能に規制緩和する」議論だから
この提案は、12月20日に内閣府の規制改革推進会議で取り上げられたもので、「配置基準を4:1にする」と決定されたわけではありません。実際には、介護の人員配置に関する規制を緩和する方向で検討するという内容です。※
もう少し噛み砕いて言えば、「見守りITなどを活用して対応できる事業所に限り、4:1までの配置でも認める制度にしてはどうか?」という提案であり、すべての施設に一律で4:1を求めるものではありません。つまり、ITの活用が難しい事業所は、これまで通りの基準で運営しても問題ないということになります。
私自身も特別養護老人ホームを運営していますが、現状の3:1ではとても対応しきれません。実際には、2:1に近い体制で、職員の皆さんに頑張ってもらっているのが現状です。
この配置基準はあくまで最低ラインの話であり、仮に制度が4:1まで緩和されたとしても、それを上回る人員配置をしている施設については、今後も何ら問題はないと考えています。
※参照:内閣府 規制改革推進会議 会議情報
■賛成理由2:介護人材不足は、間違いなくこれから更に顕著になるから
■介護職員の人材不足の現実
「4:1なんて無理だよ」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、失礼ながら、質問者さんは今おいくつでしょうか?
※出典:厚生労働省 介護人材確保に向けた取組
■人口構造の変化と介護現場の年齢構成
今の介護現場を支えているのは、実は40歳以上の職員が中心で、若い世代の職員は非常に少ないというのが現状です。これは、現場で働いている方なら肌感覚で理解できることではないでしょうか。
※出典:厚生労働省 日本の人口ピラミッドの変化
■若手不足と外国人材の不安定さ
このままでは、現行の3:1の配置基準を維持すること自体が現実的に難しくなっていくのではないでしょうか。
■解決手段となるIT・ICT化
安定的に供給できる手段として考えられるのがロボットの活用です。もちろん、ロボットの導入においてもコストの問題や半導体不足などは生じますが、人材不足を補うという点では有効的です。
さらに、ロボット以外だとセンサー技術の活用や、記録の電子化なども介護施設に取り入れられるIT・ICT化の例です。これらを活用することで、介護の質を保ちながら人員の負担を軽減することができる可能性が見えてきます。
■伊藤先生の実体験と介護業界の展望
若い頃は、夜勤手当を目当てに月5〜6回の夜勤にも積極的に取り組んでいましたが、今では体力的に少し自信がなくなってきました。この先は、さらに厳しくなるかもしれません。
これらの背景も踏まえたうえで、今は、2040年を見据えて制度を見直していくべきタイミングに来ているのだと思います。
■賛成理由3:チャレンジする組織に介護現場が変わらなければならないから
私の勤務する特養では、眠りの見守りシステムを導入しています。睡眠のリズムや体動を感知して見守りができるため、夜間の巡視を2時間おきから4時間おき、あるいは不要にすることも可能になりました。(もちろんケアプラン上での同意を得たうえで)この成果として、職員の負担が減り、利用者さんの安眠にもつながっています。
実際、利用者さんの立場になったときに、睡眠中2時間おきに誰かが部屋に入ってきたら、落ち着いて眠れませんよね。私自身、かなり敏感な方なので、ドキッとして眠れなくなるかもしれません。
つまり、利用者さんにも職員にも良い環境がつくれるなら、4:1も選択肢のひとつです。工夫次第で可能性は広がります。私たち自身が考え、変わっていくことが求められているのだと思います。
配置基準を「4:1」にすることで生じる課題

2.職員の給与低下のリスクがある
■1.単純な変更は介護職の負担増加に繋がる
しかし、IT・ICT化を前提としてものであるため、その準備が不足した状態で配置基準を変更してしまうと、単に職員1人あたりの負担が増加することに繋がってしまうのです。
■2.職員の給与低下のリスクがある
しかし、現状の3:1でも多くの介護現場では、労働基準法に違反したシフトを作成しないと対応できないことから、施設独自の基準を設けて2:1に近い基準で配置しているところが多く、東京都高齢者福祉施設協議会の調査では58%の特養で独自の基準を定めていることがわかります。※
これらのことから、今後4:1が基準となった場合、より職員の給与水準が低下してしまう可能性があるので、IT化やICT化への取り組みを強化していく必要があるでしょう。
※参照:東京都高齢者福祉施設協議会 特養における利用率及び介護職員充足状況に関する実態調査(概要)
IT・ICTの導入に向けて補助金を積極的に活用しましょう!
しかし、国としても介護業界の人材不足を懸念していることから、「介護テクノロジー導入支援事業」として、介護職員の業務負担軽減や職場環境の改善に取り組む介護事業者がテクノロジーを導入する際の経費を補助し、生産性向上による働きやすい職場環境の実現を推進する施策を実施しています。
このような申請を面倒と捉えず、積極的に活用することで、長期的に見て安心して働くことができる介護事業所を作っていけるのです。
最後に:時代の変化とともに、介護業界にいる私たちも変わらなくてはいけない
社会にはさまざまな課題がありますが、なかでも人口減少は確実に進行しています。今が大変なのは間違いありませんが、だからこそ、私たち自身が未来を見据えて変わっていくことが求められています。
「変わらなければ間に合わない。」自分たちが介護される立場になる日を想定して、今から備えていくべき時期に来ているのだと思います。
■あわせて読みたい記事

介護業界のIT化・ICT化が進まないのはなぜ?導入のメリットも紹介! | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/824[2024年6月更新]近年介護業界においてもIT化、ICT化が求められています。しかし、いまだに印鑑・紙文化が根強く残る介護業界。なぜIT化が進まないのでしょうか?介護業界のIT・ICT化が遅れている4つの理由と、その先にある未来について解説します。(執筆者/専門家:大庭 欣二)

訪問介護において外国人ヘルパーは活躍できるのか?|事前に知っておきたい懸念点やメリットを紹介! | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1186厚生労働省は、2024年6月の「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」で、訪問介護において外国人介護人材を雇用することを認めるといった考えの中間まとめを提示しました。特に、人手不足が深刻化する訪問介護において、外国人介護人材の雇用はメリットもあれば、不安な声も挙がっています。この記事では訪問介護事業所の視点で、メリットや懸念点、それに対して事前に準備できることなどを紹介します![執筆者/専門家:牧野 裕美]






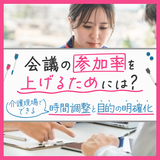








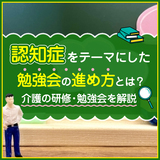















茨城県介護福祉士会副会長
特別養護老人ホームもくせい施設長
いばらき中央福祉専門学校学校長代行
NPO法人 ちいきの学校 理事
介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント
介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員 MBA(経営学修士)