排泄介助とは「人間らしく排泄ができるよう援助を行うこと」
■執筆者/専門家

社会福祉士、介護福祉士、認定排泄ケア専門員、排泄機能指導士 介護現場の職員の後、祖父の在宅介護での後悔と、自身の介護うつ経験から、そのきっかけになった排泄の支援を追求すべくおむつメーカーへ転職。 1000人以上の方のおむつ交換に触れ、介護する側もされる側も双方が「シッカリ出して、スッキリ生きる」ことが、より良い人生に繋がる。気持ち良く「出す」ことをサポートすることで良い循環が生まれることを実感する。
■そもそも排泄介助とは
一概に、高齢だから・認知症だからという理由では括れないのが排泄ケア
認知症だからといって、必ず失禁するわけではなく、100歳だからといって、絶対おむつが必要というわけではないのです。
でも、何十年も休まず動いてきた膀胱や尿道、腸や直腸は、年齢を重ねると支障が出てきます。
そんな時、年齢のせいにして考えることを止めるのではなく、どんなトラブルが起きやすいのかを事前に知っておき、適切な排泄方法をとっていくことで、他者からの援助が必要であっても自分を嫌いにならずに生活を続けていける可能性があります。
そのうえで、排泄介助とは何か?というと、「サポートが必要なところがどこかを調べて、人間らしく排泄ができるように援助を行うこと」になります。
■排泄介助の具体的な仕事内容4ステップ
1.排尿、排便それぞれどんな障害があるのかを調べる
(排尿・排便日誌、食事日誌、失禁タイプのチェック、残尿測定などの情報を集める)
2.どのような対応ができるかを考える
3.本人の気持ちを聞きつつ、専門家(医師や看護師)の意見を聞きつつプランを立てたものを実行する
4.実行した中で起こった反応や事柄を伝えてケアに再度生かしていく
排泄介助で未経験者がつまづきやすいポイントと注意点!
■介助のスピードは気にしない!まずは丁寧に対応することを意識しましょう
ケアの速さについては慣れの問題も大きいですが、一番大事にしたいのは「ケアのスピード」ではなく「利用者さんの気持ち」です。スピードを重視するあまり、利用者さんに嫌な気持ちや恥ずかしさを感じさせる介助を行っていたとしたら、それは本末転倒です。
まずは丁寧にその方に対応することを大事にしていきましょう。
すると、おのずと手際もよくなり、いろんなシーンの想定もできるようになることで、スピードも後からついてきます!
排泄ケアのやり方が分からなくて介助が遅くなってしまうのであれば、先輩のやり方を見て真似たりアドバイスをもらった上で、動画などで予行練習をするなどの準備をしてみると、苦手を克服できるのでおすすめです。
■排泄介助で注意すべき点とは?
ここからは、よく介護現場で目にする具体的な排泄介助の中でも、特に注意したい点について解説していきます。
1.焦らず立ち止まって考える
2.ADL(日常生活動作)に合わせた用具の選択をする
■1.焦らず立ち止まって考える
まずは立ち止まって、以下のことを確認してみましょう。
・どの部分にサポートが必要なのか?
・どのタイプの失禁なのか?
・この状態が命の危険に繋がっていないか
・その人の生きる力(生命力)を奪っていないか
■2.ADL(日常生活動作)に合わせた用具の選択をする
ここで押さえておきたいのは「トイレでの排泄が難しくなったのはなぜなのか」ということです。
排泄障害のある方に対して、漏れるからと言って安易におむつを使用してしまうと、本人やご家族、介護者のQOLを脅かしてしまうことにも繋がります。
ADLを考慮した排泄用具の選択チャートなどを参考に、まずはどのような環境が想定できるのかを考えてみましょう。
※用具によって問題が解決に向かう排泄障害のタイプは、主に排泄系の臓器が原因ではなくトイレまでが遠く運動機能の障害などで間に合わない「機能性失禁」が中心です。
溢流性やその他のタイプではそもそもの解決には至らないので、介入時のアセスメント(排尿日誌や失禁タイプのチェック表など)にて、失禁のタイプの推測、適切な用具の選択、排泄介助の時間の推測をしていきましょう。
ADL(日常生活動作)に合わせた排泄介助と、用具選びのポイント
ここからは、対象の方ができる動作に合わせて、それぞれの用具の使い方とポイントを解説します。
■1. 立つことができる~歩行ができる方
和式タイプ便座でしゃがむ姿勢をとることが難しい場合、洋式便座への改修や上置き式の便座で形状変更が可能です。
また、安定した排泄姿勢を維持することと立ち座り補助のため、手すりの位置を変更したり見やすい色(赤や緑)に工夫して設置することも検討します。
足台で足底を安定させる、前傾姿勢保持のテーブル付きの手すりを使用する、大きなクッションで直腸肛門角を広げ出しやすくするなどの環境設定を行い、排便しやすい姿勢を確保することがおすすめです。

■2. 股関節や膝関節が痛む方・動きが悪い方
ただし、他の家族や利用者との兼ね合いが難しかったり、掃除する箇所が増えるために手間がかかるなどのデメリットもあります。
同様の機能を持つ用具として、自動昇降機(電動で必要な時だけ昇降する用具)もあります。どこが一番解決したいことなのかを導入時に整理して用具を検討しましょう。
大切なのは、対象者の立ち上がり機能や歩行機能を維持することです。
トイレでの排泄を継続するための工夫をしていきましょう。

◆少々の漏れを軽減するアイテム例◆
・失禁パンツ
・軽失禁用のパッド
・男性用のコンドーム型の排尿管理システム
・プロテクト付きの下着(転倒による骨折などを予防する)
■3.座ることができる~立てる方
自分の力で立ち上がったり歩いたりできなくなるとポータブルトイレを選択しがちですが、その他にも方法があります。
◆ポータブルトイレを利用する場合◆
・ベッド上からそのまま横移動できるもの
・標準型と呼ばれるポリプロピレン製で軽量のもの
・木製で居室に馴染みやすいタイプ
・スチール製
・水洗タイプ
・排泄物をひとつずつラップして処理が簡単になるタイプ
など、様々な種類があります。
立ち上がる際に蹴込みがないものや、軽量のものは転倒の危険もあるため、設置時環境とともに注意が必要です。
トイレでの排泄が最終目標の場合には継続したアセスメントと工夫を忘れず、介護者のスキルや、使用する方の意向を尊重してアイテムを検討していきましょう。

◆ポータブルトイレを利用しない場合◆
この場合、ベッドから車椅子・車椅子からトイレへと、介護者が移乗動作を複数回取る必要があります。
双方に負担のない介助法を身に着けることが難しく、座位をとることができる状態の方ならば、楽にトイレへお連れすることができる「移乗椅子」や「移乗支援用ロボット」を選択することも可能です。

■4. 寝たままの方
寝たままの対応となるのは、腰をあげることが難しい方・意思疎通が困難な方など、ご自分でできる動作がほとんどないような方です。
この場合、排泄物の肌への付着を最小限にすることがとても大切で、尿意や便意の訴えがあるかどうかによって使用するアイテムが変化します。
◆尿器や差し込み便器を利用する◆
尿意や便意の訴えがあり、タイミングがとれる場合には、尿器や差し込み便器などが適応となります。
差し込み便器を使用する時、ベッドは30°位のギャッジアップをすると比較的腹圧がかかりやすくなります。

◆大人用のおむつを利用する時の注意点◆
大人用のおむつは、尿意を訴えることがなく動くことが難しい方が対象です。
この場合、アウターとインナーの2種類を利用します。
アウター:テープ止めタイプや履くタイプのおむつ、パッド併用型のアウター
インナー:尿とりパッド
※フラットタイプのシートはインナーとして使用しません。
1.アウターのサイズをその方の身体のサイズに合わせること
2.インナーはその方の尿量に合わせ、基本的には1枚で使うこと
3.尿道口への密着を、可動域を制限させないようにホールドすること
1.アウターのサイズをその方のお身体のサイズに合わせること
股下の隙間が漏れの原因となります。下の図のようにテープが中心に集まったら、ひとつ下のサイズに変えましょう。
排尿量や使用方法に合わないパッドは、横漏れや外漏れにつながるだけでなく、コストもかかります。

2.インナーはその方の尿量に合わせ、基本的には1枚で使うこと
3.尿道口への密着を、可動域を制限させないようにホールドすること
おむつの選び方や使い方で、二次障害を起こさないようにしていきましょう。
排泄介助に関するお悩み:排泄介助がどうしてもきつい!
■本日のお悩み
介護の仕事について1年目です。排泄介助にどうしても慣れることができません。。。
においとか、その他にもいろいろときついです(察してください…)
本とかネットには「尊厳を大切に!」とか「自分でできることは手伝わない!」とか書いているのを目にするけれど、そんな事を言っていられないのが現実です。
利用者さんと接するのは好きなのに、排泄介助だけがきついです。
苦手と思うことを分解することと、想像力がカギになります
とても素直なご質問をありがとうございます。
介護職だからといって、物心ついた時から他人の排泄物を好ましいと思う方は少ないと思います。
本当はご質問者さんと同じように思っているけれど、「介護職なんだから」そう思うべきじゃない、と思っている方もいるかもしれないので、ご質問して下さったことに感謝です。
■きついと感じるのは「自我境界」が発達するから
というのも、人は成長の過程で、然るべき場所で然るべき方法で排泄する事ができるように 自分の排泄物ですら「汚いもの、自分から遠ざけるべきもの」とインプットされる「自我境界」というものが発達するのです。
ちょっと難しい言葉を使いましたが、人間が人間らしく社会的に生きていく上で排泄物を汚いと思うのは、衛生的に生きていく上では大切な機能なのです。
なので、あなたはとても人間らしく、清潔な意識をお持ちなのです。
これはご質問者さんにとって強みでもあることをまず、受け止めてくださいね。
■利用者さんと接するのが好きなのはなぜですか?
(実際に介護現場から離れた役職に就くならば別かもしれませんが)
そんなあなたにおすすめの考え方を一つ、お伝えできたらと思います。
質問者さんは、利用者さんと接するのはお好きとのこと。
一番大切な気持ちかもしれませんが、その「好き」の気持ちも分解してみましょう。
きっと、利用者さんが笑ったり、喜んでくれたり、生きていて良かったと、そう思ってもらったりすると、とっても嬉しくありませんか?
例えば映画を一緒に観て感動を共有したり、美味しいご飯を一緒に食べて「おいしいね」って笑ったり、できないことができるようになったりして、その喜びを共有したり… ご質問者さんが思い浮かぶ「幸せ」のシーンは、実は全て「あること」ができているからなんです。
■適切な排泄は利用者さんの幸せの土台となっている
楽しい映画も、美味しい食事も、何かをやってみよう!と思う気持ちも、全部気持ちよく排泄が出来ていなければ、心の底から楽しい、幸せ!と思うのは実は難しいのです。 お腹が苦しかったり、常にトイレに行きたいと思っていたり、お尻が気持ち悪かったら、何よりもそれを何とかして欲しいと思うのではないでしょうか?
目の前の排泄物にだけ注目してしまうと単に汚いものに見えるかもしれませんが、利用者さんの幸せの根底にアプローチできるのは介護職なんですよね。
そして、そこを解決できたら、本当の利用者さんの笑顔が引き出せるはずです。
■別の方向から「排泄介助」をとらえてみましょう
本来排泄は、出したら気持ち良いものなのです。その体感は人と共有できないもののため難しいのですが、そこの気持ち良さまで想像できると、介護の仕事全体が変わるかもしれないくらいのインパクトで、もっと介護の仕事が好きになってしまうかもしれません。
そんな風に排泄介助を捉えてみるのはいかがでしょうか?
最後に:排泄介助にむかうための心構え
■「排泄介助=おむつ」の時代はもう終わり
と聞くと、介護職といえば「おむつ交換」をイメージされる人にとっては驚きかもしれませんね。
これは、国の方針として「できるだけトイレで排泄をすることをサポートする施設に加算がつく(=評価する)」ようになったからです。これを、「排せつ支援加算」と言います。
■大切なのは、トイレをすぐに諦めないこと
人の身体は、座位で排泄するからこそ直腸や膀胱から排泄物が出し切れるようになっており、寝て排泄するようにはできていないのです。
「おむつしてるからそこでしても良いよ」という安易な声かけは、出しきれない不快感から便秘や膀胱炎などに繋がります。
それは結果的に、その方の生命力を奪うことになり、より介護を困難にしていくと感じます。
まずは対象の方の排泄状態をアセスメントし、必要なケアとアイテムを適合する引き出しとフローを、チームで考えていきましょう。 一歩ずつその方の排泄支援に関わっていただけたらと思います。
これから介護の世界で仕事をしていこうと思っている方は、ぜひ厚生労働省の情報や、国の動向もチェックしてみましょう。
そして未来に向けて、自分が将来、受けたくなるような介護を一緒につくっていきましょう!
■あわせて読みたい記事

利用者様にトイレを我慢させる、排泄介助に大勢の職員で入る…など排泄介助に関するお悩みに専門家が回答します![執筆者/専門家:大関 美里] | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/689(2024年5月更新)排泄介助は利用者にとってセンシティブなケアです。利用者は声かけや、表情などいつも以上に介護職員の様子を見ているかもしれません。本日は、周囲の職員の言動が気になった方のお悩みに専門家である大関先生が回答します!

排泄ケアのお悩み。もっと心地の良い支援を行うには?排泄の不都合を取り除くポイントを解説します。 | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/962トイレでの排泄か?ベッド上での排泄か?ケアの場所を選ぶときのお悩みに専門家が解説します。職員が一緒に見て、話ができるツールを紹介しますので、ケアの方針検討に活用ください。【回答者:大関 美里】









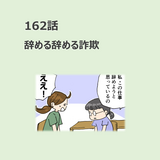

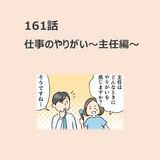


















社会福祉士、介護福祉士、認定排泄ケア専門員、排泄機能指導士