入浴介助でよくあるトラブルを防ぐために、大切なこととは?
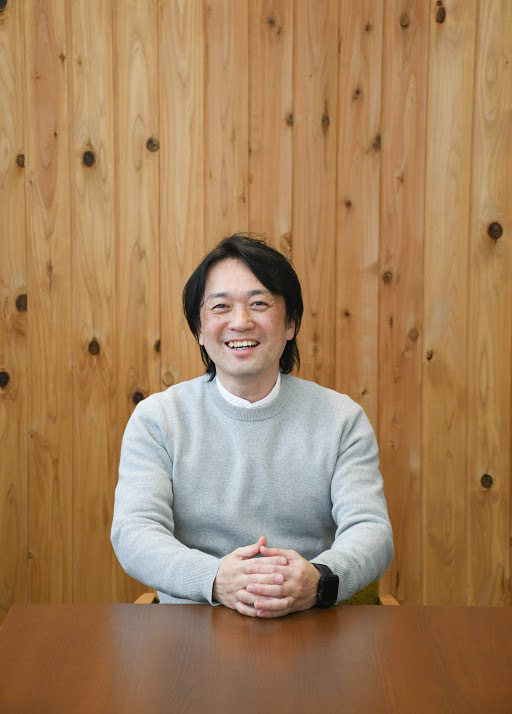
茨城県介護福祉士会副会長 特別養護老人ホームもみじ館施設長 いばらき中央福祉専門学校学校長代行 NPO法人 ちいきの学校 理事 介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント 介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員
「今日、午後浴室担当かよ・・」
「おっ、今日午後から入る人少ない、ラッキー」
なんて言葉には出せませんが、思ったことある介護職の方、たくさんいるのではないでしょうか。かく言う私もその一人。
担当表を見ながらそんなこと考えてたな・・・なんて苦い現場時代の失敗を思い返しました。
入浴介助時のリスクマネジメントについて「私の失敗談」を題材にその要因を考えてみたいと思います。
■専門家・伊藤さんの入浴介助での失敗談
現場時代、私は入浴介助が大好きでした。
なぜなら、お風呂を楽しみにしている入居者の方が多かったことと、勤務していた特養の浴室は昔ながらの銭湯のような雰囲気だったからです。
季節に応じて柚子湯や菖蒲湯を演出し、そして民謡のカセット(20年前はまだまだカセットも使っていた)をラジカセで流せば、ちょっとした旅行気分も味わってもらえたのかとても喜んでいただけました。入浴を楽しみの一つとしてサポートしていくことにやりがいを感じていたんですね。
しかし、いつの日か、冒頭で取り上げたような言葉が脳裏に浮かぶようになりました。
それは、現場のリーダーとなってからです。
リーダーになったことによる気持ちの変化
ひとりの「介護職」という立場から、リーダーとなった時、1日に○人入っていただかなければ運営基準にある週に2回の入浴を達成できない、誰と誰を組ませたら重度の介護が必要な〇〇さんの介助がスムーズにいくか?など、今までの「今日はどうやってお風呂を楽しんでいただくかな?」という発想から、「いかにまわすか?」の発想に切り替わったことによる気持ちの変化でした。
つまり「介助」が「作業」に変わった瞬間です。
転倒事故を起こしてしまった伊藤さん
そんな時、私は転倒事故をおこします。
入居者Aさんが入浴後、着替えも終え、脱衣用の椅子から車椅子に移乗する時でした。
ふと、脳裏に、「次に入る人は〇〇さんだから、B職員に声をかけてきてもらってもいいかな。」と浮かび、PHSで連絡をとろうとした瞬間、
ドンっと鈍い音を立てて転倒されるAさんが・・・(座位の安定は確認していたものの大丈夫だろうとの過信)。
幸い、Aさんには大きな外傷、打撲もなく済んだのですが、当たりどころが悪ければ命にも関わってもおかしくない事故でした。しかし、この事故はご本人やご家族にご迷惑をおかけしたことはもちろんですが、リーダーとして初歩的な事故を起こしてしまったことが悔やまれる失敗となりました。
言うまでもなく要因は、「介助」でなく「作業」をしていたことです。
■「介助」と「作業」の違いとは
「介助」とは「介=ささえる」、「助=助ける」、ご本人の思いを支え助けることです。
「作業」とは「作=つくる」、「業(ぎょう)=なすべきこと」、職員が仕事としてなすべきことになります。つまりは、主語が違うんですね。
浴室は転倒転落事故等のリスクが発生しやすい現場です。
しかし、その要因は、シンプルで入居者の視点に立っているか?と言うことだと思います。
■実際によくある、入浴介助のトラブル
衣類の着せ間違え
軽微なトラブルとして「衣類の着せ間違え」があります。
介助者からすれば違う服を着てしまっただけかもしれませんが、自分の身に置き換えれば、人の服を着るのって抵抗ありますよね。
お湯の温度が利用者さんに合っていない
「お風呂のお湯の温度」、これも一般的な適温はありますが、熱い湯が好きだった方にとってぬるめのお湯では入った気はしないでしょう。
いずれも入浴した事実は残りますが、果たしてご本人の思いを支え助けた時間となったのか?
作業になっていたのではないでしょうか。
■入浴介助の事故・トラブルを防ぐには
入浴は、清潔を保つだけでなく、血液の循環を良くする、リラックス効果を得るなど日本人の生活には欠かせない多くの役割を担っています。
「なんのために入浴するのか?=楽しみとしての入浴」、その初心を忘れず介助を心がければ、事故・トラブルは防げると思います。
もう一度、私の入浴介助は「作業」になっていないか?考えてみてください。
それが、シンプルかつ一番有効性の高いリスクマネジメントとなるはずです。
■男性(異性)の利用者さんへの入浴介助、セクハラも…注意点は?
「男性利用者さんからお風呂介助で毎回言葉で性的セクハラや罵声をあびせられます。」 というお悩みが、ささえるラボにも寄せられています。
専門家の羽吹さんに、対応策を聞きました。
ご利用者様のアセスメントを徹底しましょう
残念ながら、入浴介助中に性的な発言をされたり罵声を浴びせられたりする経験は、珍しいことではないのが現場の現状です。
何事もなかったかのように受け流すことで、ご利用者の尊厳保持につながることもあると思いますが、毎回のことだと、こちらの方が疲れて仕事に対するモチベーションも下がってしまいますよね。
そこで、介護の専門職として改めて考えていただきたいことがあります。
利用者さんはもともとどんな方だったか?に注目
それは、このご利用者様の元々の性格についてのアセスメントです。
たとえば、普段の会話に性的な発言が多い方だったか、罵声を浴びせることが多い方だったか、
などの情報をご家族様から聞いたりすることから始められてはいかがでしょうか?
元々ユーモア交えて性的な話をする方だったり、威圧的なコミュニケーションを取る方であった
ことが分かれば、自分が返答に困ってしまうことをはっきりと告げたり、大きな声を出されるたびに悩んでしまうことを伝えても良いと思います。
ただし、自分のケアによって、ご利用者様の発言や行動に異常が生まれる場合は、ご自分の
関わり方に何か問題があるかもしれないと考えてみることも大切です。
ご利用者様の発言や行動には意味があるものが多いと考え、分析し、より良い関係を作り上げる
ことに関心を持つことも重要です。
入浴介助に関連したお悩み相談
コロナ対策で入浴介助中にもマスクをしなければならず、熱中症になりそうだと意見が出ています。
でもマスクをしないわけにもいかず、声掛けをしないわけにもいかず…。
皆さんの施設ではどうしていますか?
■「みんなで考えるプロセス」が感染予防の肝
ただでさえ湿度も温度も高い浴室で、マスクの着用。
本当にたいへんですよね。私も入浴介助を行っていましたので現場でのたいへんなご苦労が想像できます。
そもそも、現在の新型コロナウイルス予防ですぐ浮かぶものとして、マスク、フェイスシールドがあげられますが、マスクは、残念ながらウイルスを吸い込むことの予防ではなく、無症状の感染者の口から飛沫が出ないようにする「感染源のコントロール」です。
そして、フェイスシールドは、透明のシールドで顔を覆うことにより、飛沫が顔にかかるのを防ぐ効果はありますが、顔に完全に密着しているわけではないのでウイルスを100%防ぐことはできないと言われています。フェイスシールドは、マスク着用困難な場合が推奨されていますが、浴室内となるとシールドが曇ってしまうことも考えられ、適切とは言えなさそうですね。
■マウスガードはいかがですか?
そこで、今回は、一つの選択肢として「マウスガード」をご紹介します。
マウスガードは、口元だけをガードする透明のシールドです。新型コロナウイルス流行以前からマスクに替わって使用する飲食店もあり、ご存知の方も多いのではないでしょうか。しかし、マウスガードでは、飛沫を防げることができるのかと不安になる方も多いともいます。
ここである製造会社さんの取り組みをお伝えします。
熱気の籠る工場で勤務する従業員の為、ベストの感染予防はないかと着用調査したところ、マスク、フェイスシールドよりマウスガードが良いとのアンケート結果が出たそうです。とはいえ、本当に飛沫を防げるのか?と従業員から不安の声が上がったので、部屋を煙で満たしてレーザーを照射し、咳をした時の空気の流れを高速カメラで撮影すると、煙が顔の正面でなく上に流れることを確認し、導入したとのことでした(日本経済新聞)。
もちろん、スーパーコンピューターを使用した飛沫分析ではないので100%ではないことを前提での記事でしたが、もしよろしければ、導入を検討してみてはどうでしょうか?
■全員を巻き込んで解決していきましょう
また、このマウスガードの件、実は、全員を巻き込んで対策を考えることにこそ、感染予防の肝があると勉強になったお話でした。
新型コロナウイルスは、何もない所から突然発生するものではなく、感染経路があります。どうすれば感染を予防しながら質の高い業務を行うことができるのか?みんなで考えることにより、一人ひとりの感染に対する意識も高まり、業務効率と感染予防の両方が達成できるものと思います。
あわせて読みたい関連記事

入浴介助、マスク着用で熱中症に。感染予防でしんどい時は?…今の知識が正しいか?を疑うことも大切! | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/542【回答者:伊藤 浩一】それは本当なのか?疑問を持ってみると意外と解決する







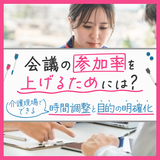









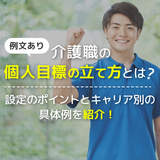












茨城県介護福祉士会副会長
特別養護老人ホームもくせい施設長
いばらき中央福祉専門学校学校長代行
NPO法人 ちいきの学校 理事
介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント
介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員 MBA(経営学修士)