2.本人や配偶者が現役世代で生活への影響が大きい
3.若年性認知症の患者さんに接する際は役割を与えるなど感謝を伝える場を増やそう
若年性認知症とは65歳未満で発症する認知症のこと
一般的には65歳以上の高齢者に多い病気ですが、65歳未満で発症した場合「若年性認知症」といわれます。
出典:政府広報オンライン 知っておきたい認知症の基本
補足:若年性アルツハイマーは若年性認知症を引き起こす原因の1種
しかし、アルツハイマーというのはあくまで認知症を引き起こす原因となる病気の1種で、アルツハイマーが原因で引き起こされた認知症のことをアルツハイマー型認知症といいます。
他にも、脳血管障害(脳卒中など)が原因で引き起こされる血管性認知症などもありますが、認知症の半数以上がアルツハイマーが原因で引き起こされるので認知症=アルツハイマーと認識されていることがほとんどです。
若年性認知症に特徴はあるの?
■若年性認知症の症状は高齢者のものと変わらない
中核症状とは、最近実施したことを忘れてしまう記憶障害や話したいときに言葉が出てこない失語、近所にいるにもかかわらず迷子になる見当識障害などの症状です。
一方で、BPSDとは怒りっぽくなる、妄想や幻覚などの症状のことで、中核症状などが原因となり引き起こされる二次症状です。そのため、中核症状による本人の不安や悩みを取り除いてあげるとBPSDの症状は緩和されます。
■高齢者の認知症と異なる点は、周囲の環境が異なること
1.「まさか…」という思いから受診が遅れやすい
2.子どもが未成年だったり、配偶者が別の介護をしていたりと周囲への影響も大きい
3.介護サービスに対する利用者本人の違和感が大きい
1.「まさか…」という思いから受診が遅れやすい
一方で、社会に出ているからこそ周囲は本人の仕事のミスが増えたことや怒りっぽくなったことなどの変化に違和感を感じ、気づきやすい傾向もあります。違和感を感じたら本人に伝えることは難しくとも周囲の家族や地域包括センター、警察署などに相談をしてみるのも力になれる場合があります。
2.子どもが未成年だったり、配偶者が別の介護をしていたりと周囲への影響も大きい
また、配偶者が自身の親の介護をしているケースも多いため複数の介護を同時並行することになる場合もあります。
このように、高齢者の認知症も対応方法に悩むことが多いと思いますが、若年性認知症は周囲の人の生活にも影響を及ぼしやすいのです。
3.介護サービスに対する利用者本人の違和感が大きい
一方で高齢者の認知症と異なり、中核症状はあるものの体力は残っているという場合も多くあるため働くことやボランティアに参加することなど本人が社会から必要とされていると感じることができる選択肢も残されています。
「若年性認知症かも」と思ったらすぐにかかりつけ医や産業医などに相談しましょう
一方で、早期発見することで障がい者雇用をやっている企業に再就職をしたり、今働いている企業で職種や配置替えを行ってもらい働き続けることができたりと認知症になったあとの選択肢を増やすこともできます。
もちろん、自分が認知症であると認めたくない気持ちもあると思いますが、症状があるにもかかわらず診断を受けないことで周囲から「忘れっぽい人」「仕事のミスが多い人」と思われ続けることはより自信をなくすきっかけになってしまうと思います。
認知症=障がいではなく1つの個性として自分が自信を持って過ごせる環境を見つけていきましょう。
専門家が解説:施設での若年性認知症の問題行動にどう対応する?
■本日のお悩み
私は、小規模多機能型で働いています。ここ1年で若年性アルツハイマー型認知症の利用者様が通所で来るようになりました。
しかし、高齢者と話が合わない、認知機能の衰えから施設内外を歩き回るなどの行動が目立ち、最近では他の利用者様に手をあげる行為が見られるようになりました。
家にいるときは、ご家族の方と静かに過ごしているようなので訪問に切り替えるかとの相談もあったのですが、つい先日家から出て警察のお世話にもなってしまいました。
ご家族様はまだ施設に通わせたいと思っており、施設長、ケアマネも共にこのままでとの考えです。しかしスタッフの人数も足りないため、その方1人に付きっきりにはなれません。どのように対応したらよいのでしょうか。
感謝を言葉で伝えられる環境を整えてみてください!!
■執筆者/専門家

・けあぷろかれっじ 代表 ・NPO法人JINZEM 監事 介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士 『介護福祉は究極のサービス業』 私たちは、障がいや疾患を持ちながらも、その身を委ねてくださっているご利用者やご家族の想いに対し、人生の総仕上げの瞬間に介入するという、責任と覚悟をもって向き合うことが必要だと感じています。
ご質問ありがとうございます!!
小規模多機能型居宅介護で働いていらっしゃるのですね!日々利用者さんの支援を熱心にされているからこそのご相談かと思います。その想いにしっかりと応えられるように回答させていただきます。
ご質問の内容にある、若年性アルツハイマー型認知症の利用者さんの対応で悩まれているのですね。他の利用者さんもいらっしゃる中で、その方につきっきりになれない歯がゆさを感じていることと思います。
■利用者さんにお手伝いをしてもらうのはいかがですか?
しかし利用者さんの多くは「自分ができることは自分でやりたい」という気持ちがあると思いますし、若年性認知症の方だと、よりその気持ちは強いと思います。
そこで、私の施設でもスタッフの数に限りがあるのもそうですが、利用者さんのできることは自分でやってもらうことを心がけ、今その方にとって必要な支援の量を考えるようにしています。
そして、その方のできることに焦点を当てながら、利用者さんの生活歴などをアセスメントし、活躍できる場をつくることを意識しながらめちゃくちゃお手伝いをしていただいています(笑)もちろん無理強いはしませんし、その方がやってくださるタイミングで、できる範囲でお手伝いいただいています。
そして、行っていただいたことに対して、感謝の気持ちを込めて「ありがとうございます」と言葉で伝えています。
介護職さんの中には、利用者さんから「ありがとう」を言われて嬉しいと話される方がとても多いですよね。それはもちろんうれしいことなのですが、逆に職員さんから利用者さんに、「ありがとう」と感謝を伝えている方は少ないように感じていて、感謝を私たちが利用者さんにお伝えするためのきっかけや、環境を整えることも私たちの役割だと思っています。
ご質問者様も、その利用者さんに、言葉で感謝を伝えられる環境を整えてみませんか?感謝を伝えるために、その方と一緒にスタッフのお手伝いをしていただくというのはいかがでしょうか。
■その行動の根本にあるものと向き合いましょう
もしかするとその利用者さんは、ただただ不安なのかもしれません。他人にどの様に見られているのか、叱責されるかもしれないなど様々なことに自信をなくされ、イライラしているのかもしれません。
恐怖心を軽減し、不安を解消してあげることができるのが、スタッフの皆さんであると感じています。
ご家庭でいる際、落ち着いて過ごされているのは、そこが安心できる環境だからだと思います。馴染みの関係を築ける小規模多機能で、関わり方を変えてみられるのも一つの方法かと思います。
■最後に:認知症と向き合うのではなくその利用者さん一人一人と向き合いましょう!
その方は講演活動もされており、その会場で私たち介護職員に伝えてくれた言葉が忘れられません。 今でも利用者さんの支援を考えるときに頭に浮かぶ言葉です。
『私たちのできる事を奪わないでください』
頭をひっぱたいて下さった感覚になりました(笑)
今まで目の前の利用者さんの何を見ていたんだと反省もしました。
認知症の症状ばかりみて、本当にその人をみていたのか、自問自答したのを思い出します。
若年性認知症の方に限らずですが、認知症の方と関わる際は症状そのものではなく、その人自身を見るようにしましょう。
きっとその方の苦しみや葛藤、恐怖、困りごと、できる事等々、沢山見えてくると思いますよ!! そして、笑顔、うれしい、楽しい、ありがとうを沢山共有していきましょう!
■あわせて読みたい記事

【事例あり】認知症の方とのコミュニケーション方法のポイントを解説!悩みがちな事例についても解説します | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/438【2024年4月更新】認知症の方を理解することは、スムーズなコミュニケーションに繋がります。この記事では認知症の方とのコミュニケーション方法やよくある事例への対応方法を紹介します!

デイサービス利用中、落ち着いて座っていられない…認知症の利用者さんに、どう対応する?[執筆者/専門家:古畑 佑奈] | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/668(2024年5月更新)デイサービスでのケア中、認知症の利用者さんがじっとしていられない、座っていられないなどで悩まれる介護職員の方も多いと思います。この記事ではそのようなお悩みに対して対応方法を専門家の方に説明していただきます!















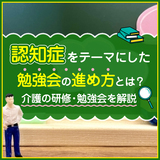















・けあぷろかれっじ 代表
・NPO法人JINZEM 監事
介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士