そもそも認知症とは?主な原因と症状を確認しましょう!
これらの病気の原因は脳にたんぱく質が溜まることなどと言われていますが、たんぱく質が溜まる原因は明確になっていません。
認知症の症状は、記憶障害や見当障害などの「中核症状」と、妄想やうつ、徘徊、暴言などの症状がある「BPSD(行動・心理症状)」の2種類に分けられます。
これらの症状が介護をする側にとってコミュニケーションをとりづらいと感じる要因になっていると言えます。
認知症の方と楽しくコミュニケーションをとるためには相手の状況を把握することが大切です。以下では、コミュニケーションをとるためのポイントを紹介していきます。
認知症の方とのコミュニケーションのコツ5選!
2.否定せず、受け入れる
3.認知症の方にペースを合わせる
4.その人らしさを大切にする
5.スキンシップをはかる
「認知症だから」と捉えるのではなく相手を受け止め尊重することが大切です。
■1.耳を傾け、共感する
「受容」とは認知症の方の話を否定せず受け止める姿勢のことを指します。たとえば、認知症の方にはいないはずの人や動物が見える幻視が起こりがちですが、「あそこに誰か知らない人がいる」と言われたら、まず「誰かがいるのですね」と相手の言葉を受け止め反復します。
次に「オープンクエスチョン」とは「なぜ、どうして」などの言葉を用いて相手に自由に答えてもらえる問いを立てることです。たとえば、先ほどの続きでいうと「どのあたりにいるのですか」「どんな人ですか」など相手に自由な回答ができる質問をします。
話を聞き、会話をすることは相手の不安軽減にもつながります。
■2.否定せず、受け入れる
物を盗まれたと思い込むこともBPSDのひとつです。こうした妄想の裏には「不安な気持ちを聞いてほしい」「もっと気にかけてほしい」という感情が潜んでいる場合もあるので、受け止めて話を聞くことで症状が落ち着くこともあります。
■3.認知症の方にペースを合わせる
低めの声でゆっくりとしたテンポで声をかけ、反応を見ながら、認知症の方のペースに合わせて会話しましょう。
■4.その人らしさを大切にする
記憶障害で新しい体験を記憶しにくくなっても、昔の記憶は残っていることが多いので、認知症の方が過去にしていた仕事や得意なことを話題にすると話が弾む場合もあります。
■5.スキンシップをはかる
肩や腕などに対し、広い面積でやさしく触れることで、安心感を与えることができます。
たとえばケア中に要介護者の手を取るときには、決して手首をつかまず、両手で腕や手を下から支えるようにするといいでしょう。
認知症ケアに効果的なコミュニケーション技法
前述したポイント5つとあわせて使っていくとより効果的なケアができるようになります。
■1.バリデーション
バリデーションの目的としては認知症の方の自尊心を取り戻すことです。感情に焦点を当て、ポジティブなものだけでなく、ネガティブなものも引き出し、その感情に共感することで同じ価値観を共有していきます。
→相手が話したことを反復する
・オープンクエスチョン
→ 「誰が・何を・いつ・どこで・どのように」を問いかけ、相手に自由に返答してもらう
・レミニシング
→思い出を聞き出していくコミュニケーション
■2.ユマニチュード
・話す
・触れる
・立つ
→これらを用いて、相手の状況に応じたケアをおこなっていく
【具体例あり】認知症の方との状況別のコミュニケーション方法4選
■執筆者/専門家
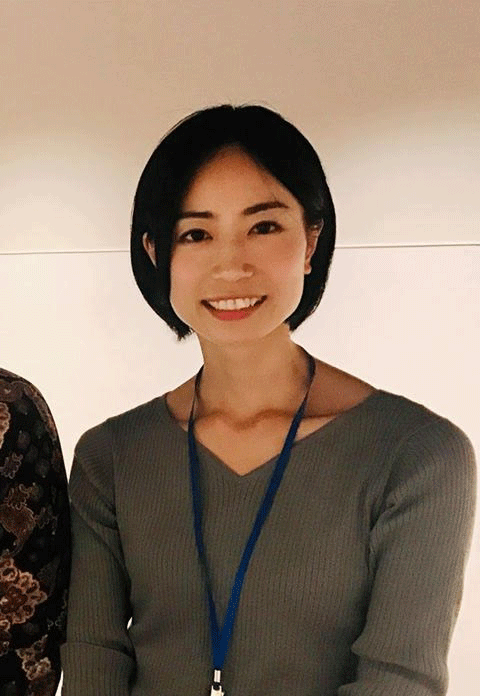
社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員 特別養護ホーム生活相談員、訪問介護事業を経験し、介護業界に9年携わる。 地域でのネットワーク活動では事務局として「死について語る会」や「3大宗教シンポジウム」など幅広いテーマの勉強会やイベントを企画・運営。 現在は介護職やマネジメント経験を活かし、介護系ライターとして研鑽中。 すきな食べ物はラーメン。
2.何度もトイレに行きたがる方への対応
3.大声を出し、攻撃的な方への対応
4.何度も同じ話をする方への対応
■1.「家に帰りたい」と訴える方への対応
具体的な対応方法を見ていきましょう。
●対応手順1:「帰りたい」理由を探る
「慣れ親しんだ家に帰りたい」という思いが自然であることと同時に、認知症の中核症状の1つである「見当識障害」により今いる場所が分からず、余計に不安を感じているかもしれません。今いる場所がわからないと、自宅にいる利用者さんが「家に帰りたい」という場合もあります。
●対応手順2:帰りたい理由に応じて具体的な方法を考える
「食事の支度をしないと」という理由であれば、食事の支度を手伝ってもらう。
「戸締りが不安」であれば、施設の窓などの戸締りを一緒に確認してもらう。
のように、それぞれの理由にあわせた対応策が必要です。
また、何かをお願いしてみるなど役割があると、不安な気持ちも少し軽減されるかもしれません。
■2.何度もトイレに行きたがる方への対応
「さっきも行きましたよ」と言いたくなるのをぐっとこらえて、トイレ以外のことに意識を向けるコミュニケーションを心がけましょう。
●対応手順1:トイレ以外のことに意識を向ける
パズルゲームや脳トレなど、好きそうなことや熱中しそうなことが結び付けられるといいですね。
●対応手順2:医療的なケアが必要な可能性も視野に入れる
前述した内容に当てはまりそうな場合は、医療的なケアも検討し、多職種連携を図りましょう。
■3.大声を出し、攻撃的な方への対応
周囲の利用者さんのことも加味すると、注意したくなる気持ちもありますが、認知症の症状であることを理解して、職員一丸となってチームで対応するようにしましょう。具体的な対応方法は以下の通りです。
●対応手順1:これが認知症の症状だということを理解しておきましょう
自身の意思をうまく表現できないもどかしさや、自尊心が傷つけられたり、不安や不快を感じたりしたとき、攻撃的な言動として表出する方もいます。
対応の際、ついこちらも感情的に受け止めそうになりますが、まずは認知症の症状がそうさせている、ということを念頭に置いて対応しましょう。
●対応手順2:信頼関係を築きながら、チームで対応することを意識しましょう
時間を置いたり、対応する人を変えたりと、チームで対応を検討していきましょう。
言動の背景にある思いを探りつつ、長期的な対応として、まずは信頼関係を築くことを大切にします。 信頼関係を築く具体的な方法として、ぜひ先述した「ユマニチュード」を活用してみてください。
■4.何度も同じ話をする方への対応
まず、なぜ同じ話をしているのか、その背後にある「思い」を知ろうとすることが大切です。そのうえで、認知症の症状と向き合い悩んでいる利用者さんに寄り添ってケアをしていきましょう。
具体的な対応方法は以下の通りです。
●対応手順1:利用者さん本人の「思い」を探ってみましょう
このうち、「中核症状」は記憶障害、見当識障害、理解・判断力の低下、実行機能障害、言語障害(失語)、失行・失認などの認知機能の障害です。
まずは、このことを理解したうえで、利用者さんが何度も同じ話をしているなかで、どのような「思い」を持っているのか考えてみましょう。
●対応手順2:「直前のことを忘れてしまう」ことを理解したうえで、利用者さんに寄り添う
質問のなかにある「紙に書いて分かりやすく伝える」ということも、とてもいい方法だと思います。その場合も、どんなに丁寧に説明して、そのときは納得していたとしても、説明したことを数分後には忘れているのが、認知症の症状なのです。
そのため私たちも、利用者さんの「分からなくて不安な気持ち」に寄り添った対応をする必要があります。
利用者さんは、どのようなことを、どのようなときに聞き返すことが多いですか?
日や、時間で、ご様子に変わりはありますか?
表情や、声色や、体調は、どのようなご様子ですか?
何か、小さなことでも変化や共通点がないか探ってみてください。
●対応手順3:いい意味で悩みながら、チームで取り組みましょう
とはいえ方法は無限にありますし、そのときのタイミングで、ご本人にぴったりはまったり、 全然はまらなかったりします。こうしてみたらどうだろう?と考えることこそ、介護の仕事の面白さです。このプロセスを楽しみましょう。
とはいえ、1人で考えすぎてしまうと煮詰まってしまうので、チームのメンバーもぜひ巻き込んでみてください。 とても抽象的な回答で恐縮ですが、質問者さんがいい意味で悩みながら、ケアできることを 応援しています!
認知症ケアを知ることは介護業界に携わるうえで必須事項です!
■2024年4月から認知症介護基礎研修が完全義務化
認知症介護基礎研修とは、認知症ケアの基礎的な知識やスキルを身につけてもらうための研修です。医療福祉系の定められた資格を持つものは受講不要ですが、無資格で介護職に携わる人は受講が必須です。
参考:厚生労働省(6)認知症介護基礎研修受講義務付けの効果に関する調査研究事業(速報値)
■認知症ケアはますますニーズが高まる
実際に、内閣府のデータによると、今後も認知症および軽度認知障害(MCI)の有病者数は増えていく見込みであり、認知症ケアを理解できているかどうかが介護の質を決めることになるといっても過言ではない状況が迫ってきているのです。そのため、認知症ケアについて適切な知識とスキルをもつことが、業界の未来を支えることに繋がるでしょう。
出典:内閣府 令和6年版 高齢社会白書(全文)
まとめ:認知症を理解し、不安に寄り添うことがコミュニケーションの第一歩になります!
認知症の方とコミュニケーションをとり、介護をスムーズにおこなうためには、この不安に寄り添い続けることが大切です。早く解決しようと焦りがちですが、急ぐ必要はありません。相手の気持ちを想像しながら柔軟に対応していきましょう。
■マンガで簡単まとめ「認知症の方とのコミュニケーション方法!」


マンガ監修:望月太敦(公益社団法人東京都介護福祉士会 副会長)
■あわせて読みたい記事

認知症の祖母が怒りっぽい。家族と喧嘩してしまうときどうしたら? | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/979怒りっぽい認知症の祖母と父がよくケンカします…。 認知症の家族との関わり方のお悩みに専門家が回答します。 【回答者:伊藤 浩一】
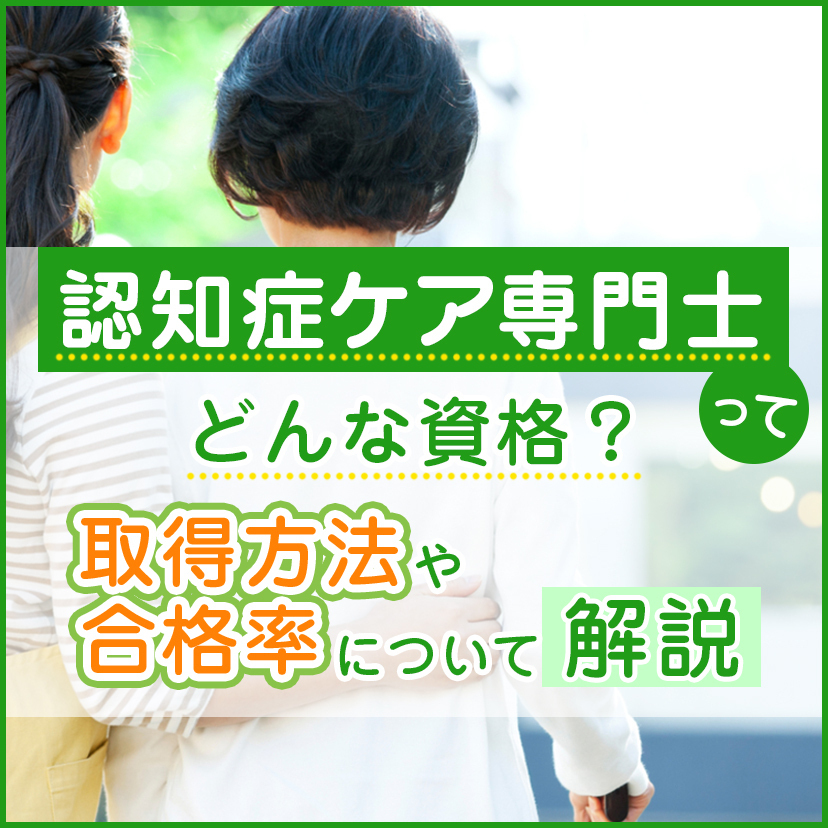
認知症ケア専門士ってどんな資格?取得方法や合格率について解説 | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/976【2024年4月更新】認知症ケア専門士は、認知症ケアの知識とスキルを備えた人を養成するための資格です。取得すると、認知症の利用者に対してより適切な対応ができるようになります。メリットや受験方法など、認知症ケア専門士に関する基礎知識を解説します。【ささえるラボ編集部】




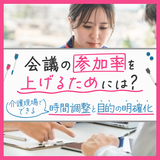

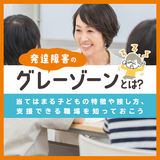









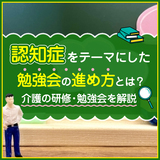















ささえるラボ編集部です。
福祉・介護の仕事にたずさわるみなさまに役立つ情報をお届けします!
「マイナビ福祉・介護のシゴト」が運営しています。