意欲が低下した高齢者の動機づけに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1.高い目標を他者が掲げると、動機づけが強まる。
2.本人が具体的に何をすべきかがわかると、動機づけが強まる。
3.本人にとって興味がある目標を掲げると、動機づけが弱まる。
4.小さな目標の達成を積み重ねていくと、動機づけが弱まる。
5.本人が自分にもできそうだと思う目標を掲げると、動機づけが弱まる。
2.本人が具体的に何をすべきかがわかると、動機づけが強まる。
動機付けには、行動要因が自身の内面から生じる興味や関心に起因する「内発的動機付け」と、行動要因が評価や賞罰などの外部的な刺激に起因する「外発的動機付け」があります。本人の内面からわき上がる「内発的動機付け」のほうが、より意欲を高めるとされています。
1.(×)高い目標を他者が掲げると、圧迫や強制を感じて意欲が低下する可能性があります。
2.(○)行動目標を本人が理解し、具体的なイメージを持つことで、動機付けが強まります。
3.(×)本人にとって興味がある目標を掲げると、動機付けが強まります。
4.(×)小さな目標の達成を積み重ねていくと、自己肯定感が高まり、動機づけが強まります。
5.(×)達成可能な目標を掲げることで、動機づけが強まります。
高齢者の便秘に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
1.大腸がん(colorectal cancer)は、器質性便秘の原因になる。
2.弛緩性便秘(しかんせいべんぴ)はまれである。
3.けいれん性便秘では、大きく柔らかい便がでる。
4.直腸性便秘は、便が直腸に送られてこないために起こる。
5.薬剤で、便秘になることはまれである。
1.大腸がん(colorectal cancer)は、器質性便秘の原因になる。
1.(○)がんにより腸管が狭窄すると、便の通過が物理的に障害されるため、器質性便秘の原因となることがあります。
2.(×)高齢者では大腸の蠕動運動が減弱するため、弛緩性便秘が多くみられます。
3.(×)けいれん性便秘では、自律神経の緊張により大腸がけいれんを生じ、便の通過が遅滞する
ため、初めに硬い便が出て、その後に軟便となります。
4.(×)直腸性便秘は、便が直腸に送られているにもかかわらず便意を感じない状態であり、便意を過剰に我慢する習慣から生じます。
5.(×)腸管の蠕動運動を抑制する作用を有し、便秘の誘因となる薬剤も多いため、薬の副作用で便秘になることはまれではありません。
高齢者の転倒に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1.介護が必要になる原因は、転倒による骨折(fracture)が最も多い。
2.服用する薬剤と転倒は、関連がある。
3.転倒による骨折の部位は、足首が最も多い。
4.転倒の場所は、屋内では浴室が最も多い。
5.過去に転倒したことがあると、再度の転倒の危険性は低くなる。
1.(×)介護が必要となった原因として最も多いのは認知症であり、次いで脳血管疾患、高齢による衰弱、骨折・転倒の順となっています。
2.(○)高齢者が処方される多くの薬にふらつきやめまい、眠気などの副作用が認められており、転倒を誘発する可能性は高いといえます。
3.(×)転倒による骨折部位は大腿部近位部が最も多く、要介護状態に至る大きな原因となっています。
4.(×)屋内において転倒した場所で多いのは、寝室や居間です。
5.(×)過去に転倒したことがある場合は、その原因となった筋力低下や環境などリスクが解消されない限り、再転倒する危険性は高いといえます。
Aさん(小学4年生、男性)は、思いやりがあり友人も多い。
図画工作や音楽が得意で落ち着いて熱心に取り組むが、苦手な科目がある。
特に国語の授業のノートを見ると、黒板を書き写そうとしているが、文字の大きさもふぞろいで、一部の漢字で左右が入れ替わっているなどの誤りが多く見られ、途中で諦めた様子である。
親子関係や家庭生活、身体機能、就学時健康診断などには問題がない。
Aさんに当てはまる状態として、最も適切なものを1つ選びなさい。
1.自閉症スペクトラム障害(autism spectrum disorder)
2.愛着障害
3.注意欠陥多動性障害
4.学習障害
5.知的障害
1.(×)自閉症スペクトラム障害には、対人関係が苦手で強いこだわりがみられるという特徴があります。思いやりがあり友人も多いAさんには該当しません。
2.(×)愛着障害とは、何らかの理由により親や養育者との間で愛情に基づく関係性が形成されず、情緒や対人関係に問題が生じる対人関係障害です。Aさんの場合、親子関係や家庭生活に問題はみられません。
3.(×)図画工作や音楽が得意で落ち着いて熱心に取り組むことができるため、注意欠陥多動性障害(ADHD)には該当しません。
4.(○)学習障害では、知的発達の遅れや視聴覚障害がないにもかかわらず、特定の領域で学習の遅れがみられます。Aさんは文字を書く能力に関して遅れがみられるため、学習障害の一つである書字表出障害(ディスグラフィア)であると考えられます。
5.(×)得意な科目があり、就学時健康診断でも問題がなかったAさんには、知的発達の遅れはないといえます。
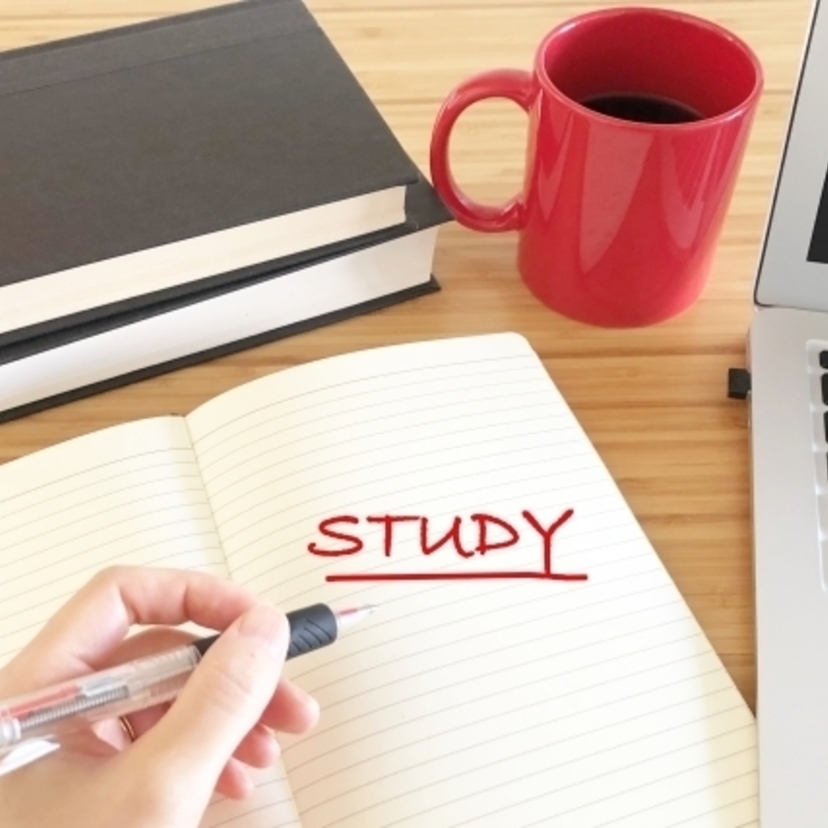



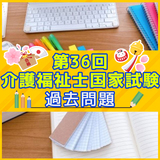
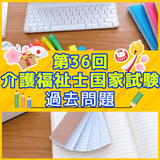
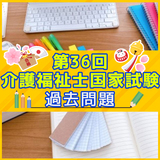
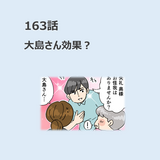


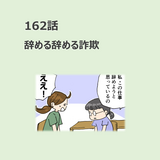

















ささえるラボ編集部です。
福祉・介護の仕事にたずさわるみなさまに役立つ情報をお届けします!
「マイナビ福祉・介護のシゴト」が運営しています。