介護業界のIT化・ICT化が進まないのはなぜ?
■介護業界でもIT化・ICT化は推奨されている
介護業界においても、IT化・ICT化を推奨する動きはあり、令和3年度の介護報酬改定では、
・PDFなどのデータを使って利用者への説明が可能に
・利用者への同意を取る際、電子署名が利用可能に
・押印欄が削除される
・オンライン服薬指導が算定されるようになる
など、デジタル化、IT化、ICT化に向けた施策が進んでいます。
さらに、令和6年度には処遇改善加算の要件として、生産性向上が求められるようになりました。
人材不足である介護業界において、介護の質をあげていくためには、IT化・ICT化で生産性の向上を図る必要があります。
しかし、実際の介護現場では、まだまだ紙文化や印鑑の文化が根強く残っています。
なぜ介護現場ではICT化が進まないのでしょうか?
その原因を解説します。
IT化・ICT化へ待ったなし!行政の動きに沿った一層の努力が必要です
■執筆者/専門家

福岡福祉向上委員会 代表 外資系コンピューター会社の営業、父親が営む会社の経営見習いを経て、2002年に35歳で福祉の世界に入り、14年間で2つの社会福祉法人の経営に携わる。 新規事業立ち上げ・組織づくり・職員育成・労働環境改善を行い、職員の労働満足度を向上させ、離職率の劇的低下を実現する。
■介護現場におけるIT・ICT化の現状とは
■そもそも日本はIT化・ICT化が進んでいない国
そして、その中でも特に介護業界はIT化・ICT化が遅い業界であるといえます。
それはなぜなのでしょうか?
出典:総務省 令和3年 情報通信白書 「第1部 特集 デジタルで支える暮らしと経済」
■ファックス、フロッピーが当たり前の介護現場も
介護現場では、いまだにファックスが大活躍。
フロッピーディスクという今の若い方などは見たこともない過去の遺物が、数年前まで介護保険の請求業務で使用されていたなんて、笑うに笑えない話もあります。
■介護業界のIT化・ICT化が遅れている4つの理由
介護業界ではいまだにファックスが大活躍していたり、フロッピーディスクという近年ではほぼ根にすることのないものが数年前まで使われていたりと、IT化が進む以前に停滞している現場も多いのです。
その理由としては、4点あります。
1.行政との兼ね合い
2.労働者側が電子機器に対して苦手意識がある
3.電子機器の導入にコストがかかる
4.情報漏洩のリスクがある
1.行政との兼ね合い
従来は、利用者との契約、重要事項説明書、ケアプランなど多くの書類に捺印が必要とされ、行政の監査や実地指導においても、それを確認されていました。
これらが、ようやく令和3年度の介護報酬改定において、電子データでの契約が認められるようになったのです。
前述したように、日本全体がIT化・ICT化がはやくはないからこそ、その影響が介護業界にもあると言えるでしょう。
2.労働者側が電子機器に対して苦手意識がある
介護業界は他業界に比べ平均年齢が高く、紙社会・印鑑社会で働いてきた人が多くいます。そのため、IT機器に対して苦手意識や抵抗を持っている人も少なくありません。
いまだに介護記録や報告書でも手書きの書類が散見されます。
国から電子データの契約が認められても、現場側が追い付いていない・取り入れていないという現状もあります。
3.電子機器の導入にコストがかかる
令和5年度の厚生労働省「介護事業経営実態調査」によると、介護サービス全体の収支差率は2.4%と、前年度より0.4ポイントも低下しています。※
このような経営状況の中で、人材を確保するためには人件費を削ることはできず、そうなるとITコストを捻りだす余裕はなくなってしまうのです。
国や行政はIT化に対する補助金なども用意していますが、その申請をするゆとりすらない事業所も多いようです。
出典:厚生労働省 令和5年度介護事業経営実態調査結果の概要
4.情報漏洩のリスクがある
私たち介護現場は、かなりセンシティブな個人情報を取り扱っています。それらの電子データを対行政や事業所間で行う際の暗号化やリスクヘッジに対する備えや知識が、まだまだ不足しているといえます。実際に電子データでの扱いを活発にするためには、それらに対するセキュリティ対策などが必要となりますが、人材不足である介護業界において着手するのが難しいのも現実です。
介護業界はこれらの理由により、介護現場ではまだまだIT化・ICT化が遅れていると言えるでしょう。
■介護業界のIT化・ICT化の先には、多くのメリットがある
■スマートフォンが使えるなら、IT化・ICT化のメリットは理解できるはず
欲しい情報にいつでもアクセスでき、相手の都合に関わらず情報を届けることができ、さまざまな検索ワードで必要な情報を拾い出すということを日常的にしています。
これらは過去に、手紙や公衆電話や固定電話、ファックスなどで行っていたことです。恐ろしいくらいの時間を掛け、非効率で、間違いも発生しやすい行為を行っていたのが、携帯電話やスマートフォンの登場、そして急速な普及により、国民のIT化・ICT化は進んだわけです。
このことから、介護業界での印鑑や紙の文化から卒業することにメリットがあるのは誰もが想像できるでしょう。
■印鑑・紙文化からの卒業の先にあるメリット
介護業界での印鑑や紙を使用する文化をなくすメリットは複数あります。
1.効率化
2.低コスト化
3.情報共有のスムーズ化
4.正確性の向上
1.効率化
しかし、印鑑の捺印をなくし電子書類で対応することによって、オンライン上でスムーズに書類のやりとりができるようになるのです。
忙しいと言われている介護業界において、この手間が省けることは業務の効率化に繋がるでしょう。
2.低コスト化
また、それは費用面だけでなく時間(タイムパフォーマンス)の意味でもです。これらを低コスト化することにより、介護業界の業務はスムーズに進みます。
また、導入に費用はかかるものの、長い面で見ると経営面にも最終的にはよい影響を与えられるでしょう。
3.情報共有のスムーズ化
電子で管理することによって、必要な情報の検索ができたり、情報を追加する際にも紙より簡単に行うことができたりします。
情報漏洩のリスクもあると思いますが、紙での管理はパスワードがかけられないのに対し、電子管理はパスワードの設定もできます。情報漏洩のリスクはいずれの場合も変わらずあると思うので、施設でいかに管理体制を整えるかが大切です。
4.正確性の向上
一方で、電子媒体を使うと数字を入力するだけで正しい表記に自動変換してくれたり、誤った表記に警告が出たりと、できる限り人によるミスを減らしてくれる仕組みができあがっています。
今後さらにニーズが高まり、利用者が増える介護業界において多くの情報を正確に管理するには、IT化・ICT化は大切なのではないでしょうか。
■介護現場におけるIT化・ICT化は、生き残るために必要なこと
■行政も、IT化・ICT化に向けて進んでいる
厚生労働省は「介護現場におけるICTの利用促進」において
「厚生労働省では、介護現場におけるICT化を進めています。
ICTの活用については、従来の紙媒体での情報のやり取りを抜本的に見直し、ICTを介護現場のインフラとして導入していく動きが求められています。介護分野のICT化は、介護職員が行政に提出する文書等の作成に要する時間を効率化し、介護サービスの提供に集中する上でも重要であると言えます。」と述べています。※
また、データ連携の方法や介護事業所でITツールを導入するための手引きなども公開し、介護事業所におけるIT化・ICT化を支援しています。
出典:厚生労働省 介護現場におけるICTの利用促進
■IT化・ICT化が進まなければ、やがて負のスパイラルに
つまり、満足な収入を上げることが困難となり、人件費に掛けるコストも削らざるを得ず、人は採用できず、辞めていくという「負のスパイラル」に陥ることとなるわけです。
よって、介護現場に於けるIT化は喫緊の課題であり、待ったなしであるというのは、以上のような理由からです。
「苦手」だからとか、「コストが掛かる」とかで、逃げるのではなく、生き残るために必要なことだという覚悟が必要だと思います。
介護現場のIT化・ICT化に伴う介護現場からのお悩み
【お悩み】
介護のICT化に伴い、見守りセンサーをつけたが、実際の忙しさは変わっていないように思います。 例えば、夜勤のように一人でたくさんの人数を見ている場合では、結局ICT化のために導入した見守りセンサーが鳴ったところで、そこへ駆けつけるのは人(介護職)です。
結局人が対応するにも関わらず、配置基準が変わり人数が減らされるのは困ってしまいます。
…とのことです。
このようにICT化を行ったが上手くいっていないというような場合、どのようなことを改善すればいいのでしょうか。
■まずは導入の目的が明確だったかを確認しましょう。
ICT化による効率化が上手く行かない事業所はたくさんありますが、原因は大きく分けて2つに分けられます。
1.ICT導入の目的が明確になっていない
このような場合は、ICT導入の成果が何なのか?もおのずと不明確となり、効果測定が難しくなってしまいます。
もう1度原点に立ち返り、現状の現場における課題点を洗い出したうえで、課題の解消にそのICT機器がツールとして活用できるかを見直し、活用方法を再考することをおすすめします。
ICT導入時の検証が不十分だったり、または. トップダウンからの指示などで導入ありきで取り入れたり、現場の声に沿った機種選定が出来ていなかったり…このようなことはなかったでしょうか。
このような場合は【ICT導入の成果が何なのか?】もおのずと不明確となり、効果測定が難しくなってしまいます。
もう1度原点に立ち返り、現状の現場における課題点を洗い出したうえで、課題の解消にそのICT機器がツールとして活用できるかを見直し、活用方法を再考することをお勧めします。
2.運用方法を定めず、宝の持ち腐れになっている
導入目的を確認したら、次に下記を確認してみてください。
・その目的は現場のメンバーに浸透しているのか
・ICT機器の特性や現場の状況に応じた運用ルールは定められている
・運用ルールがメンバーに徹底できているか
ICT機器を導入すると、多くのことがすぐに解決すると誤解されがちです。 多くの施設で、とりあえずICTを導入し、その運用ルールを定めないまま宝の持ち腐れになっているケースがあると言えます。
■改めて目的を考えなおし、ITやICTと上手に向き合いましょう!
でも、想像してみてください。
ICT導入のない夜勤の見回りでは、利用者さんの部屋を回り、布団をはぎ、排せつ状況を確認し… 場合によっては、おむつの交換を行うなんてことを夜勤の間ずっと行っていたのです。
介護職員にとっても、利用者さんにとっても大変な状況ですよね。
それと比べると、排せつや離床を見守りセンサーが感知してくれ、それに応じて、動くだけになれば双方にとって喜ばしいことです。
利用者さんもよく眠れるでしょう。
夜勤の人数が減らされるかもという心配もあるようですね。
私はもっと前向きに考えてよいと思います。
介護報酬により収入が定められている介護業界において、職員の給与を上げていくのはとても大変です。
しかしながら、業務の効率化により全体の介護職員数を減らせれば、一人ずつの給料を上げていくことが可能となります。
介護職員の確保が大変な現在、多くの介護経営者はいかにして質の高い介護職員を採用し、辞めさせないようにできるかを常に考えています。ICT機器の導入もその一環だと思います。
現場の方にとっては、なかなか経営者の気持ちは理解しにくいかもしれませんが、ICT機器の導入を機会に、「導入目的の確認」も含め情報共有すると、考え方も変わるような気がします。
少しだけ視点を変えてみて、考えてみてはいかがでしょうか。
最後に:IT化・ICT化は慣れてしまえば介護業界の強い味方です
しかし、IT化・ICT化は国も推奨する介護業界において欠かせないものなのです。導入に際して懸念すべき事項も多くありますが、ここでしっかり向き合うことで10年後、20年後まで事業所が生き延びる手段となります。
今一度、自身の事業所でIT化・ICT化できる箇所はないか向き合ってみてください。
■あわせて読みたい記事

介護記録を電子化すべき?デメリットは?導入後の不満の解決法も紹介します | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/584導入後に発生する不満の解決法を、職員目線と管理者目線で解説します。電子化という言葉の恐怖、そのイメージに囚われすぎてはいませんか?【回答者:伊藤 浩一】

介護施設がICT導入前に必ず考えておくべきこととは?専門家が解説します。 | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/751【回答者:大庭 欣二】ツールを導入しただけでは、何の効果も発揮しない。ICTの導入は「目的」でなく、「手段」であることを忘れずに!

介護業界の生産性向上って?生産性向上の定義や意義をわかりやすく解説!~導入編~ | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1164介護職員等処遇改善加算の加算要件にもなった生産性向上。事業所は取り組まなきゃと思いつつ「そもそも生産性向上って何?」と思っている方もまだ多いはず…。ささえるラボでは「導入編」「実践編」「実践事例編」の3回に分けて専門家が生産性向上について解説します![執筆者/専門家:伊藤 浩一]








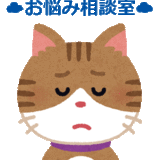










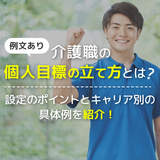












福岡福祉向上委員会 代表