本日のお悩み
私の施設ではまだ介護記録が手書きです。
連絡帳や日誌もあり、時間がかかって大変です。
知り合いのところではiPadにするなど電子化しているようなのですが、施設自体もそんなに大きくないし、職員も若くないので提案するのをためらっています。
専門家の方はどうしていますか?
小さい施設でも電子化するべきだと思いますか?
電子化という言葉の恐怖、そのイメージに囚われすぎてはいませんか?
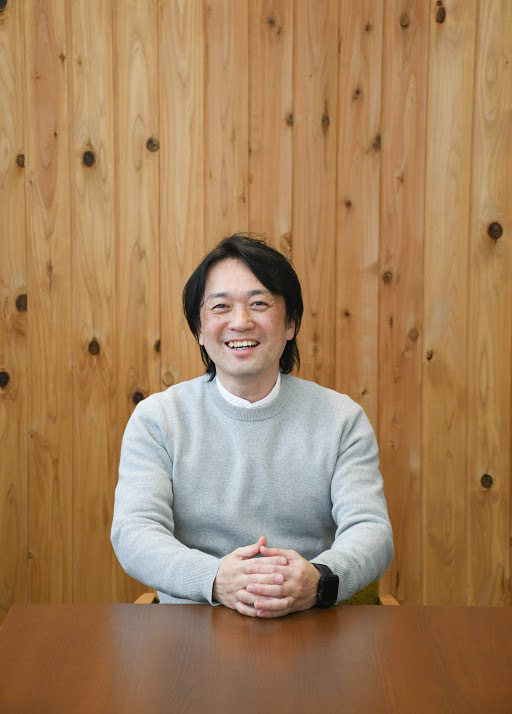
茨城県介護福祉士会副会長 特別養護老人ホームもみじ館施設長 いばらき中央福祉専門学校学校長代行 介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員
ご質問ありがとうございます。
私の施設では電子記録に変更して約10年になるでしょうか。
ipadの第1世代の時からでしたので気がついたら10年も経っていた。
と言った方がしっくりくるかもしれませんね。
■介護記録を電子化する上で、考慮すべきこと3つ
①導入時、②電子化のメリット・デメリット、③これからの背景
この三点でご質問にお答えしたいと思います。
①導入時
遡ること10年前(2012年頃)、私の施設でも同じ悩みがありました。
手書きでの記録時間はもちろん、膨大な紙と記録漏れのチェック・・・。
ケアの仕事というよりも書類を書きにきてるんじゃないか?と極端な表現ですが
思うこともありました。
そんな中、既に電子化している施設があるとの情報が。
藁をも掴む思いで見学に行った記憶があります。
幸運なことに上司がとても理解があり、また、ipadが話題だったこと、世の中がペーパーレスやICT化に動いていたも追い風で導入の決定は速かったと思います。
また、見学に行った施設さんが本当に丁寧に教えてくださいました(何度も足を運ばせていいただきました)。感謝ですね。
そして、質問者さんが気にされている現場に導入、浸透させていくお話です。
これは私も不安でした。
やはり年配の職員も多く、反発するのではと考えたためです。
しかし、結果は驚くほどスムーズでした。ipadが物珍しく、みんなはじめてだったので、どちらかというと興味津々、そして、当時から排泄表や食事表はエクセルで作っていたので、さほどPCに抵抗感がなかったんですね。
それよりも膨大な書類の管理に一石を投じられるという期待が大きかった気がします。
そもそもipadって感覚でシンプルに操作できるようになってますよね。
②電子化のメリット・デメリット
電子記録の最大のメリットはデータの抽出です。
例えば、毎日、食事、排泄、バイタルを記録することで、1週間(期間は決められる)の変化がグラフとして瞬時に見える化することもできます。
これによりいつから状態が変化したか?等一目瞭然で、医療との連携、情報共有、ケアプランへの反映、ご家族への説明などがスムーズになりました。
また、記録はデータ保存されていますのでipadやPCを持参し、wifi環境等があれば、病院でも記録の閲覧や入力が可能となりました。
昔は、個人ファイルを持ち歩いていましたね。
では、デメリットです。これは強いて言うならですが、手書きからPCやipadでの打ち込みで作業が楽になると思いましたが、時に手書きの方が速いこともわかりました。
例えば、食事量や排泄の記録は一時的に紙に手書きでチェックし、後ほど端末に打ち込む具合です。
完全なペーパーレスはできませんでしたが、むしろ手書きの良さを残しつつのハイブリッド型が有効なのかもしれませんね。
③これからの背景
まず、電子記録導入において、若いか若くないか?はあまり関係ないと考えます。
今やシニア世代(60〜79歳2020年調べ、n=10,000)の92.9%がモバイル端末を所持し、内77%がスマホ利用者だそうです。
このコロナ禍により、非接触が求められるようになりました。
役所への申請など含め、むしろスマホを使えないと生活できなくなっています。
それに、シニア世代の皆様もしっかり順応されてるんですね。
また、厚生労働省が令和3年度の介護報酬改正によって科学的介護に大きく舵をきったことは質問者さんもご存知だと思います。
科学的介護とは、客観的な情報に基づいた分析結果を活用し、実践していく介護のことです。
つまり、施設の大小ではなく、日本の介護全体が科学的介護を推進しなければならなくなったということです。
情報分析は、手書きでは難しいですよね。
また、施設の大小による資金の差については、導入補助金が拡充されています。
詳しくは都道府県のHPなどをご参照ください。
■電子化は、する前提で議論を
ということで小さい施設での電子化は、
「するべきかどうか?」ではなく、「しなければならない」と考えてください。
10年前は、電子記録システムも選択肢が少なかったですが、いまや様々なシステムが日進月歩で世に出ています。
つくり手もより使い勝手が良いものを研究しています。
でなければ売れませんから・・・。
自分の施設に合い、尚且つ、ご利用者へのサービス向上につながる電子記録は?なんてみんなで話し合いながら導入検討するプロセスは、チームビルディングとしても有効かもしれませんね。
記録の電子化をしたけれど、不満が続出…解決策は?
介護記録の電子化について私の施設での成功事例をお伝えしました。
「成功!」という表現よりは、「思ってたよりスムーズにいった!」という事例でした。
つまりは「心配しすぎだったかな・・。」という内容です。
しかしながら、実際導入してみたら
「やはりうまく活用できない」
「PCやタブレットだと入力に時間がかかる。」
「使いにくく、これなら手書きのほうがよかった」
などの不満の声も届いているとのことですので職員目線と管理者目線でその解決策を探っていきたいと思います。
■1. 職員目線で、電子化を成功させるポイント
何事も、慣れるまでは時間がかかる
介護記録の電子化に対する感想は、以前の手書き作業との比較ですよね。
つまり、「手書きの方が早かった、タブレットは時間がかかる」との感想は、そのスピードに対しての不満なのだと思います。これは単純に慣れていないから時間がかかっているということはないでしょうか?
また、通常であれば考えられるはずの「慣れるまでは時間がかかっても仕方がない」が考えられないのは、その根拠としての「何のために電子記録を導入したのか?」という目的が職員さんに明確になっていない状態が考えられます。
最初から不満の状態でスタートしているので、悪いところばかり探してしまって、いいところを見ない状態とも言えるでしょう。
電子記録の導入は誰のため?
電子記録導入は利用者さんのためです。
データ分析や情報共有ツールは確実にサービスの質向上につながっています。
目的を明確に良いところに視点を当てましょう。そして、極端に移行するのではなく組織風土に応じたアナログとのハイブリッド型を模索するのも手です。
利用者さんのために導入したんだという目的に立ち帰れば、電子記録をどのように活用するか?の視点に切り替わるはずです。
■2. 管理者目線で、電子化を成功させるポイント
「せっかく大金を出して電子記録を導入したのになんで職員は文句ばかり言ってるんだ!」
というのが概ね管理者さんの悩みだと思います。
お恥ずかしい話、私は介護ロボットやICT機器を導入する際、何度も経験しました。
専門家・伊藤さんの失敗談
まず、第一の失敗は、移乗ロボットです。
職員が腰痛に悩んでるな、何とかしてあげたい。よし、福祉機器展でこの前見てきた、移乗ロボットを導入しようと自分で決めて、利用を促しました・・・。結果、最初だけ使用してくれたもののしばらくしたら倉庫行きとなっていました。
第二の失敗は、前回の失敗を活かし、職員とともに福祉機器展に行って、使いやすいと職員が感じた同じく移乗ロボットを導入した事例です。
要は職員に判断させれば、自分達が決めたものだったから使ってくれると思ったんです。しかし、しばらくするとまた倉庫行きでした。
「なぜ!みんなのため(腰痛予防)、しかもあの時みんながいいっていったじゃん!」
失敗の共通点と、そこから学んだことは?
そしてやっと気がつきました。
これら失敗の共通点は「職員のため」が目的だったこと。
違ったんです。職員は「利用者さんのために」働いていたんです。
つまり、電子記録も同じで、現場が不満を漏らすのは、管理者さんがみんなのために入れてやったんだ目線になっていませんか?ということです。
■電子化成功の秘訣は、うまくいっている施設へ見学に行くこと
ということで、職員、管理者それぞれの目線で介護記録の電子化がうまくいかない理由を探ってきました。みなさんに心当たりはあるでしょうか?
思い返せば、なぜ私たちの事業所の導入がうまくいったか?
それは、導入している事業所さんをみんなで見学に行ったからだと思います。その施設さんは、記録を電子化することで利用者さんのケアの質が向上したと自信満々に語っていました。
そして、客観的に見ても利用者さんも、職員さんもイキイキとされていたんですね。
つまり、電子化により利用者さんの生活が豊かになるビジョンが職員に描けていた状態で導入できたということだったんです。
■立ち返るのは「利用者さんのため」という目的
今もなお、導入に悩んでいる、または、導入したけど進まない事業所さんは、再度「利用者さんのため」という目的に立ち戻ってください。
また、コロナ禍により難しいかもしれませんが、上手く行っている事業所さんの見学をお勧めします。
今は、オンラインでも対応してくれる熱心な事業所さんもありそうですね。ご参考になれば幸いです。































茨城県介護福祉士会副会長
特別養護老人ホームもくせい施設長
いばらき中央福祉専門学校学校長代行
NPO法人 ちいきの学校 理事
介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント
介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員 MBA(経営学修士)