本日のお悩み:利用者さんへの声かけが上手くいかず悩んでいます
自分なりに努力をして感情などが出ないように落ち着いて声かけをしているのですが…
上手にコミュニケーションをとるためのポイントがあれば教えてください。
■執筆者/専門家
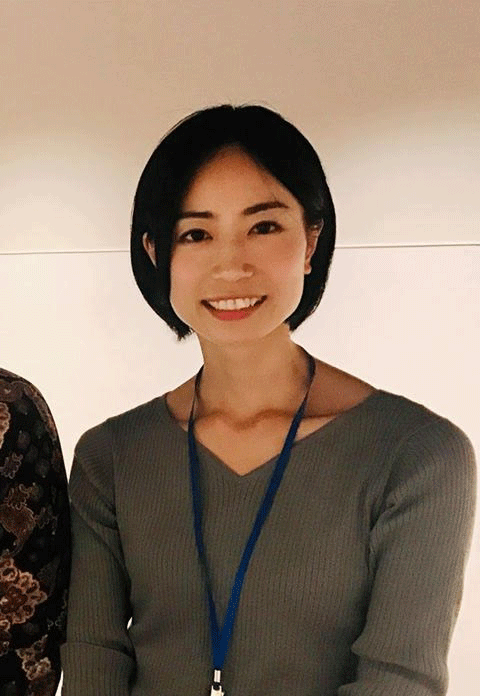
社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員 特別養護ホーム生活相談員、訪問介護事業を経験し、介護業界に9年携わる。 地域でのネットワーク活動では事務局として「死について語る会」や「3大宗教シンポジウム」など幅広いテーマの勉強会やイベントを企画・運営。
努力していても怒られてしまうと、お辛いですね…。
質問者さんが上司やリーダーから意見をもらうとき、具体的にどういったところが課題なのか、などのフィードバックはありますか?
質問内容にある、「感情が出てしまう」ということなのでしょうか?
「声かけ」というのは、とても難しいです。
私も日々、頭を悩ませています。いまだに「あ、しまった…。もっと違う声をかければよかった。」と反省することもしばしばです。
まずコミュニケーションの基本を再確認しましょう!
まずはコミュニケーションにおける基本のポイントを再確認していきましょう。
2.利用者さんには敬語を使うようにしましょう
3.利用者さんと目線を合わせ、口調や声の大きさに注意しましょう
4.利用者さんの様子を日ごろからよく観察しましょう
■1.アセスメントをしっかり行いましょう
声かけに正解はなく、声をかける相手の状況や、そのときの環境によって適した声かけは異なってきます。
私は以前、100歳の誕生日を迎えられた方に対して「お誕生日おめでとうございます!!」と声をかけたら、ものすごく怒られた経験があります。その方は年齢のことを言われるのが嫌で、誕生日はおめでたいものではなかったのです。
これは極端な例ですが、その人がどんな人なのか、入所までの状況はどのような感じであったか、今どのような状況なのかなどというアセスメントを丁寧に行い、相手のニーズを把握することが重要になってきます。
■2.利用者さんには敬語を使うようにしましょう
お客様であるから敬語を使わなければならないというわけではなく、敬語を外してしまうと、線引きが難しくなり、言葉が乱れていってしまいます。その結果、ケアにも乱れが影響してしまうのです。
最初は丁寧に話していたはずでも、気づいたら慣れなどから敬語が曖昧になっていませんか。今一度、立ち止まり振り返ってみてください。
■3.利用者さんと目線を合わせ、口調や声の大きさに注意しましょう
たとえば、車いすの利用者さんとお話しをする際、忙しいと立ったまま会話をしてしまうことはありませんか。
こちらにとっては、忙しい中の1シーンであっても利用者さんからすると上から話しかけられ、威圧的に感じてしまう場合もあります。利用者さんとコミュニケーションをとる際は、必ず目線をあわせて話しかけるようにしましょう。
また、口調や声の大きさも重要です。年齢と共に、聴力の低下がある利用者さんもいると思います。その方に普段より大きな声で声をかけることはよいのですが、それが過剰になると周囲の利用者さんから見て口調が強く感じてしまったり、威圧的に感じてしまったりします。
声をかける際は、相手のことはもちろん、周囲の状況も考慮するようにしましょう。
■4.利用者さんの様子を日ごろからよく観察しましょう
たとえば、頭が痛いとき。ゆっくり休みたいのにずっと声をかけられると正直「しんどい」と感じてしまうと思います。一方で、「体調が悪いのですか?」などと声をかけられて嬉しいと感じる場合もあると思います。これは利用者さんも同じです。
利用者さんの気持ちを100%汲み取ることは難しいと思いますが、利用者さんの様子を観察し、その状況に適切な声かけを推測することはできると思います。
●時には、行動の背景事情を考える必要がある場合もある
転倒の危険性を防ぐためには「なぜその人は立ち上がりたいのか?」を探る必要があります。
たとえば、トイレに行きたいのか、散歩がしたいのか、はたまた座りっぱなしでお尻が痛いのか…など何かしらの背景事情があるはずです。
ご本人に、「どうされましたか?」と聞いてみて、求めていることが分かれば、すぐ対応できるのですが、言葉で返ってこないこともあるでしょうし、適切な言葉が見つからない方もいらっしゃるでしょう。
だからこそ私たちが観察し、推測をして、そのときに適するであろう声かけを考える必要があるのです。
ただ、ここで一生懸命考えた声かけでも、相手が求めていることではない場合も多々あります。状況によっては少し時間を置いたり、対応者を変えたりすることが必要な場面もありますね。
タイミング別!声のかけ方を見直そう!
■ケア前の声かけ:不安を取り除く言い回しを
「○○さん、車椅子に移る準備をしますね。」
2.利用者さんに寄り添った声かけをする
「何か心配なことがあればいつでも教えてください。」
「私がそばにいるので安心してください。」
これらのような声かけを行うことで、利用者さんは安心し、ケアを受け入れやすくなります。
■ケア中の声かけ:作業ではなく対話を意識して
「今から体を拭きますね。冷たくないですか?」
「不安なことがあればいつでも言ってください。」
2.日常の話題をいれる
「今日はどのようなことをしましたか?」「さっきのレクは楽しかったですか?」
3.ケアに関連する身近な話題を取り入れる
「このタオルは柔らかくて気持ちいいですね。」
これらの声かけを行うことで、利用者さんは安心してケアを受けることができます。ただし、利用者さんによっては声をかけられたくない場合もあるので、事前に要望を確認しておけるとよいでしょう。
■ケア後の声かけ:感謝や労いを伝える
「今日も協力してくださりありがとうございます!」
2.ケアの感想を聞いてみる
「今日の入浴はいかがでしたか。気になることがあれば教えてくださいね。」
3.継続的な関係性を築く姿勢を示す
「(笑顔で)次回もよろしくお願いします!」
最後の言葉のかけ方次第で、利用者さんの満足度も変わってきます。その日のケアがどんなに大変でも、最後は笑顔で声かけをおこなうと、次のケアにも繋がります。
利用者さんの状況別!声かけのOK例とNG例
ここからは状況に応じて適切な声かけの例(OK例)と避けた方がよい声かけの例(NG例)を紹介していきます。
■認知症の利用者さんへの声かけ
■ポイントと注意点
また、見当識障害により時間の感覚が薄れてしまう方も多いので、挨拶の際は時間がイメージできるように「おはようございます」「こんばんは」を意識的にお伝えしたり、施設等だと、生活の場所なので職員同士の「お疲れさまです」は利用者さんの前では使わないなどをルールにしているところもあります。
ー適切な声かけの例(OK例)
と提案する形での言葉かけを行うことで、相手の意思を確認することができますし、たとえ言葉で意思を表現するのが難しい方であっても、表情や仕草から読み取れるものもあります。
ー避けた方がよい声かけの例(NG例)
といった否定的な声をかけてしまうと、不快な感情が残ってしまいます。
また、「○○した方がいいですよ」など指示を出すような言い方や「早くして」といった急かすような声かけは一方的に介助者の決めたことに従ってもらうような印象を与えることがあります。
■視覚障害のある利用者さんへの声かけ
■ポイントと注意点
一緒に歩いているときに「これから上りの坂道です」と、いちいち言わなくても感覚で分かるから不要という方もいれば、言ってもらった方が安心、という方もいます。何をどこまで説明するかは介助者の考えではなく利用者さんの考えに沿うことが大切です。
また、高齢期になってから視覚に障害をもった場合、見えないことに対しての不安が大きい方もいらっしゃるため、こまめに「来ましたよ」「これから○○しますね」と声をかけたり、細かいことを説明したほうが安心される方が多いと思います。
ー適切な声かけの例(OK例)
食事の際に「○時の方向に○○があります」とお伝えしたり、「右手の近くに○○があります」「トイレの流すレバーは座って左手を伸ばした壁側についています」といったように、誰が聞いてもわかりやすいことがポイントです。
ー避けた方がよい声かけの例(NG例)
■拒否のある利用者さんへの声かけ
■ポイントと注意点
とにかく目をみて、天気でも、ニュースの話でもいいので話しかけ、好きなことを探る。そして好きなことの話をする。「気にかけてますよ」というメッセージを態度で示す。そのような工夫の繰り返しでプラスのイメージを持ってもらう必要があります。
どうしても介助者側が苦手意識を持つことも多いですが、そういった感情はなぜか相手に伝わってしまいます。利用者さんの立場から考えれば、いきなり自分よりもはるかに若い人にあれしましょう、これしましょうと言われたら、それだけでうんざりしてしまう気持ちもわかりますよね。
ー適切な声かけの例(OK例)
といったようにプラスのイメージの言葉に言い換えることができ、これをリフレーミングと言います。 あくまでも拒否というのは介助者側からみた現象であって、利用者さんからみたら当然の防御。リフレーミングを活用して、声のかけ方を考えてみるのも策かと思います。
ー避けた方がよい声かけの例(NG例)
場面別!排泄・食事・移乗などに応じた声かけの例
■排泄の羞恥心をやわらげる声かけ
「今からトイレにいきましょうか。お腹の調子はいかがですか。」
2.安心感を与える声かけを行う
「そばにいるので、安心してください。」「寒くないですか?」
このように、羞恥心を持ちやすいケアであるからこそ、いつも以上に利用者さんの気持ちに寄り添った声かけが重要です。
■食事を拒否する方への声かけ
「今日は食欲がないのですね。」
2.興味をひくような声かけをしてみる
「今日のメニュー、とても美味しそうですよ。少しだけ食べてみませんか。」
このように無理強いはせず、利用者さんに寄り添ったうえで、少しずつ声かけを行っていきましょう。
■移乗をスムーズにおこなう声かけ
「○○さんお手伝いしますね。」
2.具体的に説明する
「これからベッドから車椅子に移ります。ゆっくりで大丈夫ですよ。」
このように安心感と信頼を持つことで、利用者さんも移乗介助に協力的になってくれるためサポートが行いやすくなります。
声かけで重要な3つのポイント
2.表情・身だしなみ
3.ジェスチャーの活用
■1.言葉遣い・抑揚
基本的なマナーとしては、利用者さんに対しては敬語を使うことが大切です。また、早口ではなく落ち着いて口調とテンポで話すようにしましょう。
■2.表情・身だしなみ
利用者さんに声かけを行う際は、口角をあげ明るい表情で、清潔感のある身だしなみを心がけましょう。
■3.ジェスチャーの活用
しかし、あまりにオーバーなジェスチャーは誤解や威圧感に繋がってしまうため、利用者さんの目線を考慮したうえで行うようにしましょう。
最後に:相手が求めている声かけを考えてみましょう!
無意識にできているものもあれば、長く働くなかで忘れてしまっているものもあったはずです。しかし、繰り返しにはなりますが、ここで紹介したものが全て正解とは限りません。
では、私たち介護職ができることは何でしょうか。それは「考えること」です。利用者さんが求める声かけや対応が何なのか、日々思考し、想像していくことが大切です。
ぜひ、声をかける前に「利用者さんが求めている声かけを考える」という習慣をつけてみてください。
■マンガでまとめ:利用者さんへの声かけのポイント


マンガ監修:望月太敦(公益社団法人東京都介護福祉士会 副会長)
■あわせて読みたい記事

【事例あり】認知症の方とのコミュニケーション方法のポイントを解説!悩みがちな事例についても解説します | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/438【2024年4月更新】認知症の方を理解することは、スムーズなコミュニケーションに繋がります。この記事では認知症の方とのコミュニケーション方法やよくある事例への対応方法を紹介します!

デイサービスで盛り上がる話とは?高齢者に喜んでもらう会話のきっかけ7選を専門家がご紹介! | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/747[2025年3月19日更新]「何を話せば良いか」ではなく、「何を聞けばいいか」で考えてみましょう/ひとり一人の個別性を大切にしましょう/オンラインやVRの活用で幅が広がります!/具体的にどんなことを話せばいい?高齢者に喜んでもらう会話のきっかけとは【回答者:伊藤浩一 羽吹さゆり 古畑佑奈 脇 健仁】

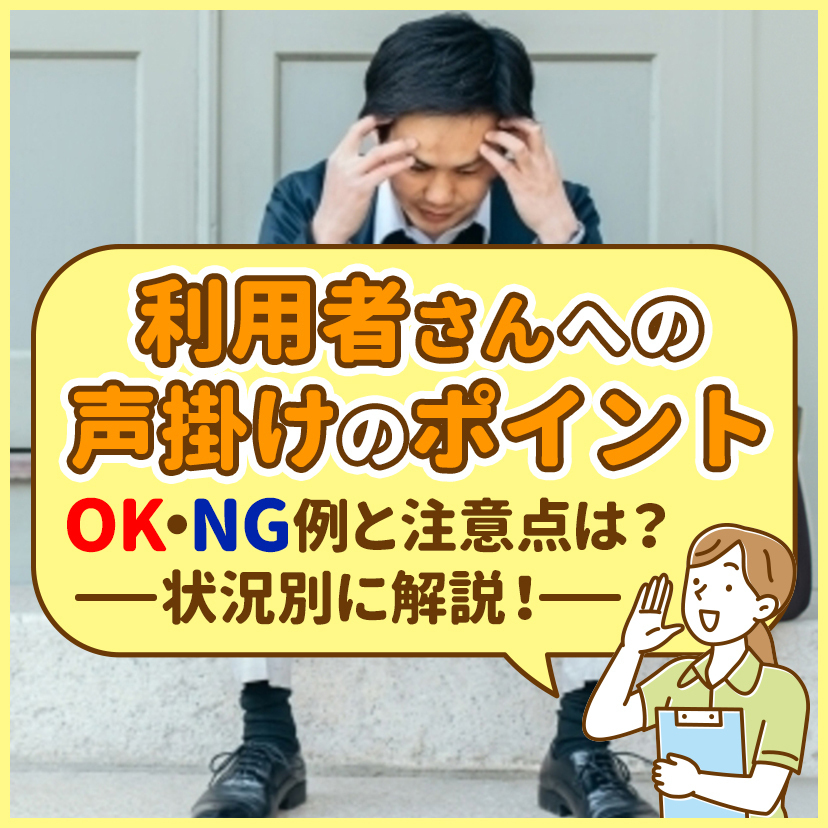





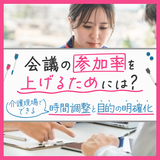









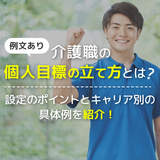












社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員