本日のお悩み
高齢者レクリエーションの担当をすることになりました。盛り上げたりするのが苦手なこともあり不安です。
どのような意識でどういったことを考えて企画・実行していけばいいでしょうか。
また、コロナ禍を意識してできる限りで密にならないようどのくらいの頻度で開催したらよいでしょうか。レクリエーション実施の目的なども教えてください。
初めて高齢者レクリエーションを企画・実行するために必要なことは?


ご質問ありがとうございます。
レクリエーション担当になられたのですね!ご担当はおひとりでしょうか?
ご利用者の前に立って、率先して盛り上げることに苦手意識があると、うまくできるか不安だと思います。
私も初めてレクリエーションの担当になった時は、プレッシャーと不安だらけだったことを思い出します。お一人で抱え込まず、周囲の仲間や経験のある先輩スタッフと相談されながら進めてみてください。
少しでも不安を払拭できるように、私からもアドバイスをさせていただきます。
■レクリエーションを行う際に必要な意識とは?
まず初めに、レクリエーションの意味について考えてみたいと思います。
どのようなことに意識すればよいのかイメージしやすくなると思います。
広く一般的な意味としてレクリエーションとは、自由時間に行われる創造的活動のことです。
よってレクを行う際は、その創造的活動がご本人にとって楽しみを伴った活動であるかをしっかりと意識することが重要です。
■レクリエーションの目的は?
目的は、「趣味活動支援」「楽しみづくり」「関係作り支援」「心身機能の維持向上」「生活のメリハリ作り」をはじめ、「認知症の予防」「症状進行の緩和」等です。
集団で実施できるものから、個人で楽しめるものなど、その手段は様々なものがありますね。
■レクリエーションの種類は?開催頻度や時間設定はどうするべきか?
①種類
多くの高齢者施設では、・体を動かすゲーム・カラオケ・手芸・工芸・文芸・自然探求・演劇・舞踊・社交的行事・脳トレーニングなどさまざまな創造活動を用意されているかと思います。
それらを総じてレクリエーションと呼びます。
②開催時間
午前中は入浴や業務が集中し、忙しい時間帯でしょうから個別の個人活動が良いかもしれません。
集団の活動は、私の施設では13時から15時までの時間の間で提供しています。
準備も含めて40分から1時間程度実施しています。
③開催頻度
開催頻度については、日曜日を除いて毎日提供しています。
日曜日は、ゆっくりお散歩などの外出の時間としていますよ。
また一人で行うのではなく、複数人や機能訓練指導員等の専門職にも協力してもらっています。
日々の業務の組み立てもありますので、職員の業務量としての負担も考慮しながら、どの時間で開催できるのか?誰が担えるのか(補助は入れるか?)等も考え、時間を設定すると開催できる日時が見えてくると思います。
■どのような事を考えて企画するのか?
レクリエーションの企画を考えるうえで大切になるのは、その方の嗜好に合ったレクリエーションなのかということです。
お一人でレクを楽しみたいのに、わざわざ集団レクにお誘いしても、その方にとっての楽しい時間とはなりません。
ただし、ケアプラン上の目標に沿ったレクリエーションは、ご本人の想いと一致していない場合もあるかと思います。
身体機能を維持していくためには、体を動かす活動も必要です。
その為、心身機能向上のためにご参加いただきたい際には、その目的を十分にご説明し、ご納得いただいた上で、参加していただきましょう。
その結果、楽しんで参加することができ、より目的の達成に近づけるかと思います。
■実施の注意点や配慮は?
なんといってもその場を盛り上げられるか、目的をしっかりと説明できるか、音楽などの環境も含めて楽しい雰囲気が作れるかにあると思います。
実施することで得られるメリットを丁寧にお伝えするといいでしょう。
実施については、転倒や車いすからのずり落ち等、安全に開催するために事故発生のリスクについては十分に検討してください。
職員が付き添うことで安全を確保できる場合もありますので、自分ひとりではなく、複数人のスタッフで開催できるとより良い時間が創造できるかと思います。
■コロナ禍を踏まえての開催頻度は?
令和5年5月8日より新型コロナの感染症法での位置づけは、2類から5類へ引き下げがされました。
※厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について」より(厚生労働省のサイトに遷移します)
こちらについては、個人の担当者判断では決められない内容でもあると思います。
どのような感染対策を履行したうえで、実施していくのかについて、事業所内で検討されてみるのが良いかと思います。
私の施設では検討の結果、マイクの消毒を行った上で毎日レクリエーションを開催しています。
レクのネタの参考になる!おすすめの記事はこちら
レクリエーションを開催するにあたり、どのような内容のレクリエーションを実施すればよいのかお悩みの方も多いと思います。そんなときはぜひ、下記の記事も参考にしていただければうれしいです。

高齢者向け、レクで使えるおすすめ脳トレ4選! | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/940毎日のレクリエーション、ネタが尽きた…とお困りの方は多いのではないでしょうか?この記事では、高齢者向け介護レクリエーションにおすすめな脳トレを4つご紹介します!

冬のおすすめレク4選 コロナ禍でもOK&寒くても大丈夫なものを紹介 | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/937寒くて外出するのをためらいがちな冬、屋内でできるおススメレクを紹介します!(後藤 晴紀)

高齢者・介護レクリエーション30選!座ったままできる簡単な脳トレ・テーブルゲーム・体操を紹介 | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/750介護施設で実施されるレクリエーションには、利用者を楽しませ、身体機能を維持するという目的があります。レクリエーションの目的や種類、注意点といった基礎知識とともに、簡単にできる脳トレ・ゲーム・体操の具体例を紹介します。(コラム:後藤晴紀)
最後に
新型コロナ感染症との共存の生活がスタートする中で、私たち専門職もどのようにご利用者の楽しみや笑顔を増やしていけるのか、社会課題に対しての挑戦が求められていると感じています。
介護福祉専門職として社会から期待されていると感じると同時に、その期待にしっかりと応えていきましょう!
制限が多い生活では、感染症や事故のリスクと共に楽しみを奪われることがあります。
私たち以上にご利用者は、その影響を受けてしまいます。
ご利用者の状態低下のリスクも踏まえながら、笑顔での生活を支えられるように支援していきたいですね。















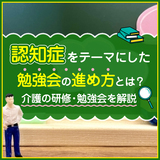















・けあぷろかれっじ 代表
・NPO法人JINZEM 監事
介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士