本日のお悩み
デイサービスに勤務しています。1週間ほど前、ある利用者様が亡くなられました。
その利用者様と仲が良かった、別の利用者様から後日、「その情報をなぜ教えてくれなかったのか?」と聞かれ
「個人情報なので…」とお伝えしましたが、仲良くしていた方のお悔やみが出来なかったことを後悔される気持ちも分かります。
こういった場合はどう対応したらよいのでしょうか?
亡くなられたことを公表するのは個人情報保護に違反することなのでしょうか?
隠さない、ごまかさない、嘘をつかない事が原則!

ご質問ありがとうございます。
介護職なら一度は経験したことがある、判断に困ることの一つではないでしょうか?
とても多くの介護職員が同様の事案について悩んでいると思います。
私も仕事を始めたころは「よくわかりません」「知らなかった」などと、言葉を濁してその場を切り抜けるように回答していたこともあります。
大好きなご利用者に嘘をつくって、しんどいですよね。
そんな経験からも、今回の質問は、よくぞ聞いて下さいました!!ありがとうございます!!という気持ちです。
ただし、ここでの回答は、あくまでも私個人としての意見です。
ほかの意見を持っている方もいらっしゃるでしょう。
介護職員としての死生観やご利用者の尊厳について考えながら、共に考えていける学びの場としていただければ幸いです。
■伝えても良いが、両者のご家族の確認は取っておくべき
まず初めに、確実なことから回答いたします。
亡くなったことを、ご友人に伝える行為自体は、個人情報保護違反とはなりません。
また、すでに亡くなっていることからも、法律上の保護対象とする権利者本人が存在しないため、プライバシーの侵害にも該当しないと考えられます。
ただし、ここで注意しなければいけないことがあります。
介護事業者としては、伝えられた側のご利用者の状態が変化する可能性や、ご遺族の心情に配慮する必要があります。
よって、ご家族の確認と同意を取っておくべき、配慮的事項であると考えます。
その理由については後述させていただきますね。
■仲の良かったご利用者には、亡くなったことを伝える
それでは、本題です。
ご利用者から「なぜ亡くなったことを教えてくれなかったのか」と聞かれてしまった事について、今後どのように対応していくか?
これに対する私個人の結論は、「仲の良かったご利用者については、お伝えする」です。
他のご利用者に必要以上に伝える必要はないと思いますが、ご友人であれば伝えることが望ましいと考えています。
■「亡くなったことは伝える」理由 1つめ
質問者さんをはじめとした介護職員は、ご利用者さんから信頼を得ていますよね。
にもかかわらず、その職員から隠しごとをされたり嘘をつかれた場合、信頼関係を壊してしまうリスクがあります。
今回もそうだったように、ご利用者は、その友人が亡くなったことをどこかで知り得る可能性が高いです。
その場合、ご利用者としての心情として「仲が良かったことを知っていたのに、信頼していた職員さんが教えてくれなかった。」という想いを抱いてしまいます。
また、今回のように「個人情報だからお伝えできない」という理由でも、恐らくそのご利用者は納得されなかったと思います。
ご友人からすれば、「知っているのに教えてくれない人」という感情を抱いてしまう状況になる事からも、双方にとって良い対応ではないと考えています。
実際に質問者さん自身も、事実を伝えられないことは辛かったことと思います。
■「亡くなったことは伝える」理由 2つ目
また、亡くなった方にとって、ご自分の死を友人に隠されたらどんなに悲しい事であるかという点も大切です。
自分ごとに置き換えてみると、自分が死んだことを友人に隠されたり、教えてもらえなかったら、悲しい気持ちになりませんか?
落ち込まないようにと周りの人が心配していることが理由だったとしても、大きなお世話だと思ってしまうのではないでしょうか。
私たち介護職員にとって重要は仕事の一つは、ご利用者の尊厳の維持ですよね。
亡くなったことを伝えないという行為は、生きてこられたご利用者の歴史や想い、尊厳が無視されてしまっている状態だと感じてしまいます。
亡くなられた後は、その方のの思い出話をしながら、故人を偲ぶことが大切なのではないでしょうか。
それが、ご利用者の尊厳を守るために私たちができる最後の行為であると感じています。
■では、今後はどう対応するか
私たちは介護職員ですし、私は介護福祉士です。
亡くなったことをご友人にただお伝えして終わり。ということでは、専門職としては不十分ですので、具体的にどのように対応していくのかお伝えしますね。
故人のご家族に対して
故人のご家族にとって、身内を失うのは辛いことです。
ご家族の中には、亡くなったことを事業所で伝えないでほしいと思うご家族もいらっしゃいます。
この確認を怠ってしまったことで「どうして勝手に伝えるんですか!?」とお叱りを受ける場合もありますので、ご友人にお伝えしても良いかを確認しておきましょう。
友人だったご利用者に対して
亡くなったことを伝た後の状態を予測する・ご家族とのトラブルを避けるためにも、病歴から精神疾患の既往歴の有無の確認をしておきましょう。
これまで喪失体験を経験してきたであろうご利用者であっても、新たな喪失体験は精神的に大きな負担となる可能性が高いです。
ご利用者に気分の落ち込みがみられた際には、その原因を考察し、友人が亡くなった事と関係があるのかを評価する必要があります。
仮に友人が亡くなった事との関係が認められるような場合、他の職員やご家族とも共有し、そのご利用者が友人の死を受け入れてまた笑顔になれるようにサポートします。
私たちは故人についての思い出話を避けてしまいがちですが、そのご利用者にとって安心して今を生きることに繋がる可能性がある場合もありますので、ご利用者が抱えている不安と、とことん向き合いましょう。
友人だったご利用者の、ご家族に対して
多くのご家族が同意(許可)していただけると思います。
注意すべきなのは、ご家族に同意を得ずに、友人が亡くなられたことを伝えてしまうことです。
その後もし精神心理状態が悪化したり、別件で入院してしまったりした場合「勝手にあんなことを伝えるから、こうなった」と責めを受ける可能性があります。
特に精神疾患が認められる方については、キーパーソンへ「ご友人が亡くなった事実を伝えても良いか」という確認と同意を得ておきましょう。
その後、家庭での睡眠状態や食欲、事業所や家庭での様子など、生活全般への観察が必要になることからも、キーパーソンとの連携が必要になります。
必ずご家族への説明と同意を得ることを忘れないでくださいね。
事業所内で、対応について話し合う
質問者さんが伝えることを決めたとしても、事業所としての判断や、上司や同僚の考え方はそれぞれだと思います。
一度この事案について事業所内で話し合いましょう。
今後の事業所の対応として、他のスタッフとも意識合わせは必要です。
冒頭でもお伝えしましたが、正解は一つではありません。
様々な死生観や考え方を知る良い機会ににもなります。
死生観を考える時間は、介護職員としてとても貴重な学びの時間になります。
ぜひ話し合ってみてくださいね。
■死に向き合って、安心できる環境をつくりましょう
「死」に対してしっかり介護職員がサポートできる体制は、ご利用者さん・ご家族の双方にとって安心なのではないかと考えています。
友達が死んだり自分が死んだことをきちんと伝えてくれる環境や、落ち込んでも支えてくれる存在がいることは、子供でも、大人でも、高齢者でも、認知症でも当たり前のことですよね。
隠したり嘘をついたりするよりも、よっぽど安心して暮らせる素敵な社会だと思っています。
そんな社会を一緒に創っていきましょう!!
ご質問ありがとうございました!















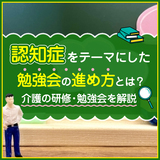















・けあぷろかれっじ 代表
・NPO法人JINZEM 監事
介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士