「同性介助」について改めて考えてみよう

・(有)⽻吹デザイン事務所介護事業部アモールファティ代表 ・アモールファティスクール⻑ 介護福祉⼠/介護⽀援専⾨員/介護技術指導員/⽇本語教員/社会科教員 介護職員実務者教員/社会福祉主事任⽤
■そもそも「同性介助が基本」はどんな場面でも通用する考え方なのか?
「同性介助が基本」と言われることがありますが、はたして本当にそうでしょうか?
例えばですが、身体の大きな女性のご利用者の移乗介護は? ご利用者の方でも女性より男性の介護職員の方が安心できるとういうケースもあります。
「同性が良い」又は「当たり前」という考え方は、少し進歩性がないのではないでしょうか。
■重視すべきは性差ではない
ご利用者の方々の中には、自分ごととして、一つ一つのケアを真剣に観察している方もいます。自分にどのようにケアをしているか、自分の羞恥心に対してどのような配慮をしてくれるか、そのような気持ちを常に張り巡らせているかもしれません。
例えば、女性のご利用者を女性職員が入浴介助をしたとします。それでも、ご利用者の「自分だけ裸になって恥ずかしい」という気持ちに配慮していなければ、ご利用者の方は満足できないかもしれません。
反対に、男性職員が「自分が男だから恥ずかしいだろうな」と気を遣いながら入浴介助をしたことで、「あの職員さんはとても優しい人」という印象を持つことになり、その後の排泄の介助等もスムーズにいったというケースもあります。
■同性であることに甘えないことも大切
同性介助の方が職員を受け入れやすいのは確かだと思いますが、それに甘んじてケアをしてしまうと、ご利用者から信頼してもらえない可能性もあることを意識していただきたいです。
ケアのシーンでは常に、「どのような気持ちで介護されているのだろうか」ということに関心を持つことが大切です。元気であれば自分でやりたいだろうなと、ご利用者さんの気持ちに寄り添うことができれば、自然と職員の態度、言葉遣い等にも配慮が現れてくるのではないかと思います。
■性差を感じさせない対応ができるのがプロ
性差を感じさせない対応こそが、ケアの専門性が問われるポイントです。
なので、男性のご利用者は女性職員に対して恥ずかしくないという概念もおかしいのです。男性こそ、今まで第一線のなかで働いていた方です。プライドもあります。プライドが高ければ高いほど羞恥心も高いのではないでしょうか。
確かに、いつもは同性介助を受けている方が、例外的に異性の介助を受けることになった場合は、身構えもするかもしれません。しかし、逆に自分の「腕の見せどころ」と捉えて臨んでみてはいかがでしょうか。
さまざまな事象も自分のスキルアップのチャンスと考えていただけたらと思います。
関連するお悩み
女性の介護士が介助するとうまくいかない(とくに入浴介助)利用者さんがいて、苦戦しています。
いろいろと試してみたのですが、男性の職員だとスムーズでした。
人員の配置の問題もあり、毎回男性職員に、というわけにもいかず、みんなでいろいろ考えながら取り組んでいますが、こういうとき専門家の方はどのように対処されますか?
ぜひヒントをください。
トライ&エラーを繰り返し、成功したケースを分析して確率を上げていく
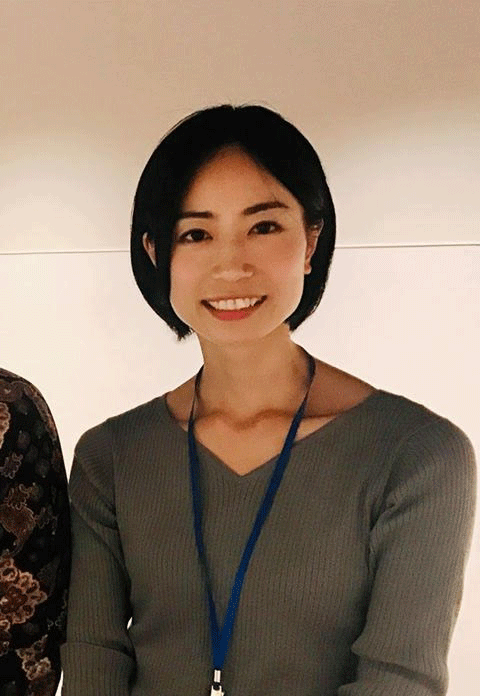
ご質問、非常によくわかります!
苦戦しますよね……それで、時々スムーズに入浴出来たりすると心の中でガッツポーズですよね。
同じようなケースで悩んでいらっしゃる方も、とても多いのではないかと思います。
個別性が高いので「これ!」といった万能の解決法がなく、また同じ方でも、職員の対応は同じなのに日によって気分が全然乗らない、ということも多いですよね。
いろいろと試している中で、「男性なら比較的スムーズ」という傾向がわかった時点で、素晴らしいと思います!
■入浴介助だけでも男性職員手伝ってもらうのがベストですが…
みなさんで考えていらっしゃるということだったので、その方の生活歴や過去にあったことなどは把握されているのかな、と思います。
きっと、出来る限りその方の意向に合わせた対応をとれるよう、すでに考慮されているのだと思いますが、職員が複数いる施設であれば、他のユニットやフロアにも相談し、最善策は入浴介助だけでも男性職員が対応できるように調整するのがよいのではないかと思います。
ただ、ご質問にあるようにどうしてもシフト上難しい日もありますよね……
確率を上げるために、出来そうなことを2つ考えてみました。
■解決策①スムーズなときのデータを取って傾向を把握する
1つは、スムーズにいったときの記録を細かく分析し、傾向を探ることです。
その際、利用者の方の様子や職員の言動だけではなく、天気や室温といった気候状況や、時間、フロアの状況など、出来るだけ細かい視点でデータに出来ると、傾向が把握しやすいかと思います。
ただこれは、もう既にされていることかもしれませんね。
個人的には、スムーズに介助できる場面にどのような傾向があるのかは興味があるところです。
(単に男性なら誰でも大丈夫なのか、女性の介助でスムーズにいった場合はどんな時かなど)
■解決策②男性職員を「演じる」
また2つ目に、男性ならスムーズ、ということで、女性職員が男性を演じることです。
演じる、と言われても困るかなと思いましたが、わかりやすく変化が出せるのが、声のトーンと、服装です。
(介護と演劇は、親和性が高いと思っています。「老いと演劇」、ぜひ調べてみてください)
高齢になると高い音が聞きづらくなりますので、もしかしたら、男性の低めの声やトーンが聞きやすいのかもしれません。
また、服装については男性職員だからみなさん暗い色を着ている、というわけではないと思いますが、色彩が与える影響も要素の1つにはなるのではないか?と考えました。
■最後に
正直なところ、全然納得のいくお答えが出来なくて、へこんでいます。笑
でも、こんな感じであれこれいろいろと考えるのが、ケアの醍醐味ですよね。
質問者さんは、チームでその考える作業が出来ていますし、その経験が他の方のケアにも生かせると思います。
結論としては、トライ&エラーをひたすら繰り返して、成功したケースを分析して確率を上げていく、ということです。
上手くいったケースあったら、ぜひとも教えてください!































社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員