クロイツフェルト・ヤコブ病(Creutzfeldt-Jakob disease)に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
1.有病率は1万人に1人である。
2.プリオン病である。
3.認知症(dementia)の症状は緩やかに進行する場合が多い。
4.致死率は低い。
5.不随意運動は伴わない。
1.(×)日本での有病率は、100万人に1人といわれています。
2.(○)プリオン蛋白が変化した異常プリオンが脳に沈着することが原因であり、動物に感染する牛海綿状脳症(狂牛病:BSE)などの類似疾患とともにプリオン病と総称されます。
3.(×)クロイツフェルト・ヤコブ病は認知症の原因疾患の一つであり、認知症の症状は発症して数か月のうちに急速に進行します。
4.(×)認知症の症状だけではなく、筋固縮などの運動失調や、意識障害などの神経症状が初期から出現し、寝たきり状態になった後は全身衰弱や呼吸器系疾患などが原因となり、多くは発症から1~2年で死に至ります。
5.(×)歩行障害や行動異常に加え、しばしばミオクローヌスと呼ばれる不随意運動を伴います。
レビー小体型認知症(dementia with Lewy bodies)に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
1.脳梗塞(cerebral infarction)が原因である。
2.初発症状は記憶障害である。
3.けいれんがみられる。
4.人格変化がみられる。
5.誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)(aspiration pneumonia)の合併が多い。
5.誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)(aspiration pneumonia)の合併が多い。
1.(×)脳梗塞が原因となるのは、脳血管性認知症です。レビー小体型認知症は、脳の広範囲にレビー小体という異常蛋白質が蓄積し、脳細胞が変性をきたしたり、減少したりすることが原因となります。
2.(×)初発症状としては、幻視やパーキンソン症状が現れます。
3.(×)けいれんはてんかんの症状であり、レビー小体型認知症ではみられません。
4.(×)人格変化は、前頭側頭型認知症でみられる症状です。
5.(○)レビー小体型認知症ではパーキンソン症状が出現するため、姿勢の傾きや嚥下機能低下などにより、誤嚥性肺炎を合併するリスクが高まります。
Bさん(80歳、女性、要介護2)は、1年前にアルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimerʼs type)の診断を受け、服薬を継続している。同居の息子は日中不在のため、週に3回、訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用し、訪問介護員(ホームヘルパー)と共に活発に会話や家事をしていた。不眠を強く訴えることが増えたため、1週間前に病院を受診したときに息子が主治医に相談した。その後、午前中うとうとしていることが多くなり、飲水時にむせることがあった。歩くとき、ふらつくようになったが、麻痺(まひ)はみられない。バイタルサイン(vital signs)に変化はなく、食欲・水分摂取量も保たれている。
訪問介護員のBさんと息子への言葉かけとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
1.「日中は横になって過ごしたほうがよいでしょう」
2.「歩行機能を保つためにリハビリを始めませんか」
3.「嚥下障害(えんげしょうがい)が起きてますね」
4.「処方薬が変更されていませんか」
5.「認知症(dementia)が進行したのでしょう」
1.(×)日中横になって過ごしてしまうと、活動性が低下し、昼夜逆転が生じるなど、認知症が進行する原因となります。
2.(×)受診後に突然それまではみられなかったふらつきが生じているため、原因は歩行機能の低下ではないと考えられます。
3.(×)嚥下障害が生じている可能性があったとしても、介護福祉職が病名や障害名を断定することは不適切です。
4.(○)受診をきっかけとして、午前中の傾眠や飲水時のむせ、歩行時のふらつきが生じています。不眠症状を訴えたことで、改善を目的とした睡眠導入薬が処方されている可能性が高く、処方薬を確認することが適切です。
5.(×)受診後の変化は、認知症の進行を示すものではありません。また、介護福祉職が疾患の進行に関して断定することは不適切です。
認知症(dementia)の原因疾患を鑑別するときに、慢性硬膜下血腫(chronic subdural hematoma)の診断に有用な検査として、最も適切なものを1つ選びなさい。
1.血液検査
2.脳血流検査
3.頭部CT検査
4.脳波検査
5.認知機能検査
1.(×)血液検査で炎症所見などを調べることはできますが、血腫の有無を確認することはできません。
2.(×)脳血流の異常を検出する脳血流検査は、認知症や変性疾患の鑑別診断に有用な検査です。硬膜下血腫は、脳を包む硬膜と脳表面との間に血腫が存在するため、脳血流検査では検出できませ
ん。
3.(○)慢性硬膜下血腫では、頭部外傷などを原因として、脳に血腫ができることで器質的に認知症症状を引き起こします。血腫の診断には頭部CT検査やMRI検査が有用であり、検査で確認した血腫を外科的手術で取り除くことで、認知症症状が改善する可能性があります。
4.(×)脳波検査は、てんかんや意識障害などの診断時に有用な検査です。
5.(×)認知機能検査は、記憶力や判断力の低下など、認知機能を評価するための検査です。
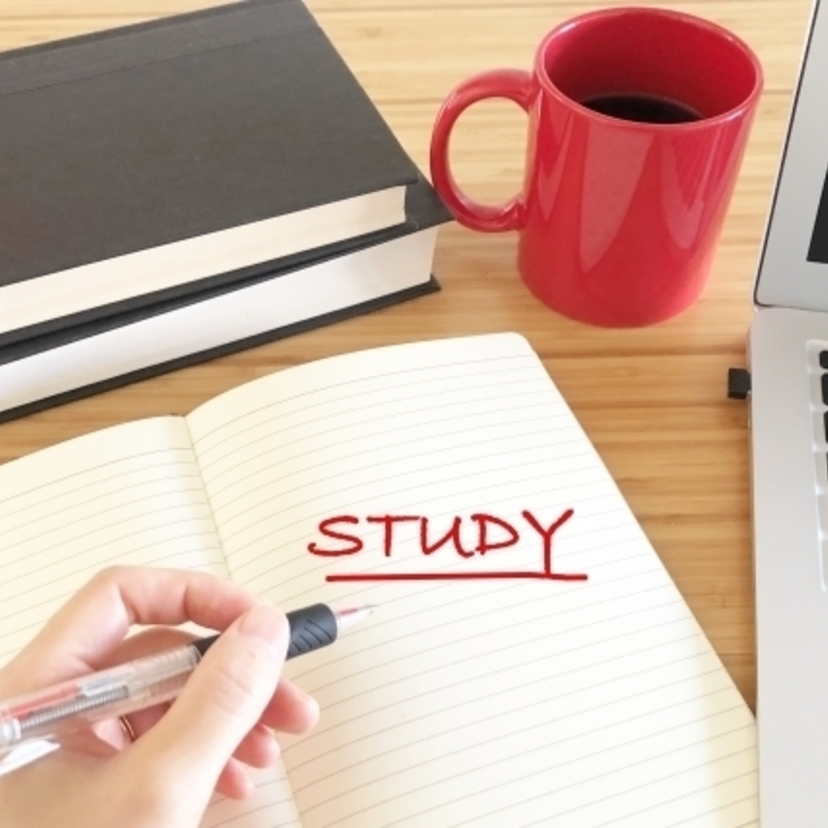



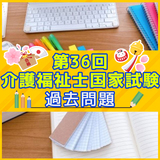
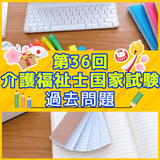
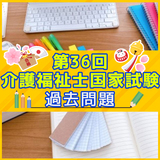







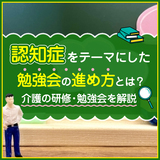













ささえるラボ編集部です。
福祉・介護の仕事にたずさわるみなさまに役立つ情報をお届けします!
「マイナビ福祉・介護のシゴト」が運営しています。