次の事例を読んで答えなさい。
〔事 例〕
Aさん(10歳、男性)は、自閉症スペクトラム障害(autism spectrum disorder)であり、多動で発語は少ない。毎日のように道路に飛び出してしまったり、高い所に登ったりするなど、危険の判断ができない。また、感情の起伏が激しく、パニックになると止めても壁に頭を打ちつけ、気持ちが高ぶると騒ぎ出す。お金の使い方がわからないため好きなものをたくさん買おうとする。
現在は、特別支援学校に通っており、普段の介護は母親が一人で担っている。
Aさんの将来を考え、家族以外の支援者と行動できるようにすることを目標に障害福祉サービスを利用することになった。介護福祉職と一緒に散歩に行き、外出時のルールを覚えたり、移動中の危険回避などの支援を受けている。
Aさんが利用しているサービスとして、適切なものを1つ選びなさい。
1.同行援護
2.自立生活援助
3.自立訓練
4.生活介護
5.行動援護
1.(×)同行援護は外出支援ではありますが、対象は視覚障害により移動に著しい困難を有する障害児・障害者に限定されます。
2.(×)自立生活援助は、単身で居宅生活を営む障害者が対象となります。
3.(×)自立訓練は、自立した社会生活を送るための身体機能や生活能力向上を目的とした訓練であり、障害児が利用することはできません。
4.(×)生活介護は、日中に障害者支援施設などで行われる介護や創作的活動であり、障害児は対象外となります。
5.(○)行動援護は、知的障害や精神障害により行動に著しい困難を有する障害児・障害者に対して行われる外出支援です。
次の事例を読んで答えなさい。
〔事 例〕
Aさん(10歳、男性)は、自閉症スペクトラム障害(autism spectrum disorder)であり、多動で発語は少ない。毎日のように道路に飛び出してしまったり、高い所に登ったりするなど、危険の判断ができない。また、感情の起伏が激しく、パニックになると止めても壁に頭を打ちつけ、気持ちが高ぶると騒ぎ出す。お金の使い方がわからないため好きなものをたくさん買おうとする。
現在は、特別支援学校に通っており、普段の介護は母親が一人で担っている。
Aさんのサービス利用開始から6か月が経ち、支援の見直しをすることになった。Aさんの現状は、散歩では周囲を気にせず走り出すなど、まだ危険認知ができていない。介護福祉職はルールを守ることや周りに注意するように声かけをするが、注意されるとイライラし、パニックになることがある。
一方で、スーパーではお菓子のパッケージを見て、硬貨を出し、長時間その場から動こうとしない。介護福祉職は、Aさんがお菓子とお金に注目している様子から、その力を引き出す支援を特別支援学校に提案した。
介護福祉職が特別支援学校に提案した支援の背景となる考え方として、最も適切なものを1つ選びなさい。
1.エンパワメント(empowerment)
2.アドボカシー(advocacy)
3.ピアサポート(peer support)
4.ノーマライゼーション(normalization)
5.インクルージョン(inclusion)
1.(○)エンパワメントは、その人が本来持っている能力を最大限に引き出し、自身で問題解決することで生活や環境をよりコントロールできるようにしていくことです。
2.(×)アドボカシー(権利擁護)は、意思表示が困難な人の利益やQOL向上のために、援助者が主張や要望を代弁することです。
3.(×)ピアサポートは、同じような立場や境遇にある人たちが、感情を共有することで安心感や自己肯定感を得ることです。
4.(×)ノーマライゼーションは、障害の有無や年齢、性別などに関係なく、すべての人が尊重され、地域社会の中で普通に生活することができる社会の実現をめざす理念です。
5.(×)インクルージョン(社会的包摂)は、社会から排除されている貧困者や失業者、ホームレスなど、すべての人々を社会的摩擦などから援護し、社会の構成員として包み支え合うことです。
次の事例を読んで答えなさい。
〔事 例〕
Bさん(45歳、女性)はアパートで一人暮らしをしていた。家族や親戚との付き合いはなかったが、趣味も多く、充実した生活を送っていた。
ある日、車で買物に行く途中、交通事故を起こし、U病院に救急搬送され手術を受けた。
手術の数日後、医師から、頸髄損傷(けいずいそんしょう)(cervical cord injury)があり、第5頸髄節(けいずいせつ)まで機能残存するための手術をしたこと、今後の治療方針、リハビリテーションによって今後の生活がどこまで可能になるかについて、丁寧に説明を受けた。
Bさんの今後の生活に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1.自力歩行ができる。
2.自走式標準型車いすを自分で操作して、一人で外出することができる。
3.自発呼吸が困難になり、人工呼吸器が必要な生活になる。
4.電動車いすを自分で操作することが可能になる。
5.指を使った細かい作業が可能になる。
脊髄が損傷されたレベルにより、運動麻痺や感覚障害の分布は異なります。Bさんは第5頸髄節まで機能残存するための手術を受けていることから、力は強くないものの肘を曲げることができる状態であると考えられます。
1.(×)脊髄が損傷されると、障害部位より下は脳からの指令が伝達されなくなるため、Bさんは自力歩行が困難となります。
2.(×)自走式標準型車いすの操作や、一人での外出は難しいと考えられます。
3.(×)自発呼吸に影響を及ぼすような障害はありません。
4.(○)電動車いすは簡単なレバー操作で移動可能であり、Bさんの残存機能を生かして自力で操作することができます。
5.(×)指を使った細かい作業は難しいと考えられます。
次の事例を読んで答えなさい。
〔事 例〕
Bさん(45歳、女性)はアパートで一人暮らしをしていた。家族や親戚との付き合いはなかったが、趣味も多く、充実した生活を送っていた。
ある日、車で買物に行く途中、交通事故を起こし、U病院に救急搬送され手術を受けた。
手術の数日後、医師から、頸髄損傷(けいずいそんしょう)(cervical cord injury)があり、第5頸髄節(けいずいせつ)まで機能残存するための手術をしたこと、今後の治療方針、リハビリテーションによって今後の生活がどこまで可能になるかについて、丁寧に説明を受けた。
Bさんは、入院当初は落ち込んでいたが、徐々に表情が明るくなり、U病院でのリハビリテーションにも積極的に取り組むようになった。現在はVリハビリテーション病院に転院して、退院後の生活に向けて身体障害者手帳を取得し、準備を進めている。Bさんは、以前のようなアパートでの一人暮らしはすぐには難しいと考え、障害者支援施設への入所を考えている。
障害者支援施設に入所するために、Bさんがこの時期に行う手続きとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
1.居宅サービス計画を作成するために、介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談する。
2.要介護認定を受けるために、市町村の窓口に申請する。
3.施設サービス計画を作成するために、介護支援専門員に相談する。
4.サービス等利用計画を作成するために、相談支援専門員に相談する。
5.障害支援区分の認定を受けるために、市町村の窓口に申請する。
5.障害支援区分の認定を受けるために、市町村の窓口に申請する。
1.(×)介護支援専門員が居宅サービス計画を作成するのは、要介護認定者が介護保険サービスを利用する場合です。
2.(×)要介護認定を受ける必要があるのは、介護保険サービスの利用を考えている場合です。
3.(×)介護支援専門員が施設サービス計画を作成するのは、要介護認定者が介護保険サービスを利用する場合です。
4.(×)相談支援専門員がサービス等利用計画を作成するためには、Bさんが障害支援区分の認定を受けている必要があります。
5.(○)Bさんは障害者支援施設への入所を考えているため、障害福祉サービスを利用するために必要な障害支援区分認定の申請を行うことが適切です。
次の事例を読んで答えなさい。
〔事 例〕
Bさん(45歳、女性)はアパートで一人暮らしをしていた。家族や親戚との付き合いはなかったが、趣味も多く、充実した生活を送っていた。
ある日、車で買物に行く途中、交通事故を起こし、U病院に救急搬送され手術を受けた。
手術の数日後、医師から、頸髄損傷(けいずいそんしょう)(cervical cord injury)があり、第5頸髄節(けいずいせつ)まで機能残存するための手術をしたこと、今後の治療方針、リハビリテーションによって今後の生活がどこまで可能になるかについて、丁寧に説明を受けた。
その後、Bさんは希望どおり障害者支援施設に入所した。入所した施設では、C介護福祉職がBさんの担当になった。C介護福祉職は、Bさんから、「日常生活で、もっと自分でできることを増やし、いずれは地域で生活したい」と言われた。そこでC介護福祉職は、施設内の他職種と連携して支援を行う必要があると考えた。
C介護福祉職が連携する他職種とその業務内容に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1.工作などの作業を行いながら身体機能の回復を図るために、看護師と連携する。
2.運動機能の維持・改善を図るために、理学療法士と連携する。
3.趣味活動を増やすことを目的に、管理栄養士と連携する。
4.活用できる地域のインフォーマルサービスを検討するために、義肢装具士と連携する。
5.栄養状態の面から健康増進を図るために、社会福祉士と連携する。
2.運動機能の維持・改善を図るために、理学療法士と連携する。
1.(×)工作などの作業を行いながら身体機能の回復を図るためには、作業療法士と連携することが適切です。
2.(○)理学療法士は、運動機能の維持・改善を図るスペシャリストであり、Bさんの「もっと自分でできることを増やしたい」という希望にこたえることが可能です。
3.(×)趣味活動に関する支援を行うのは、介護福祉職です。
4.(×)活用できる地域のインフォーマルサービスを検討するのは、社会福祉士や介護支援専門員(ケアマネジャー)です。
5.(×)栄養状態の面から健康増進を図るためには、管理栄養士と連携することが適切です。
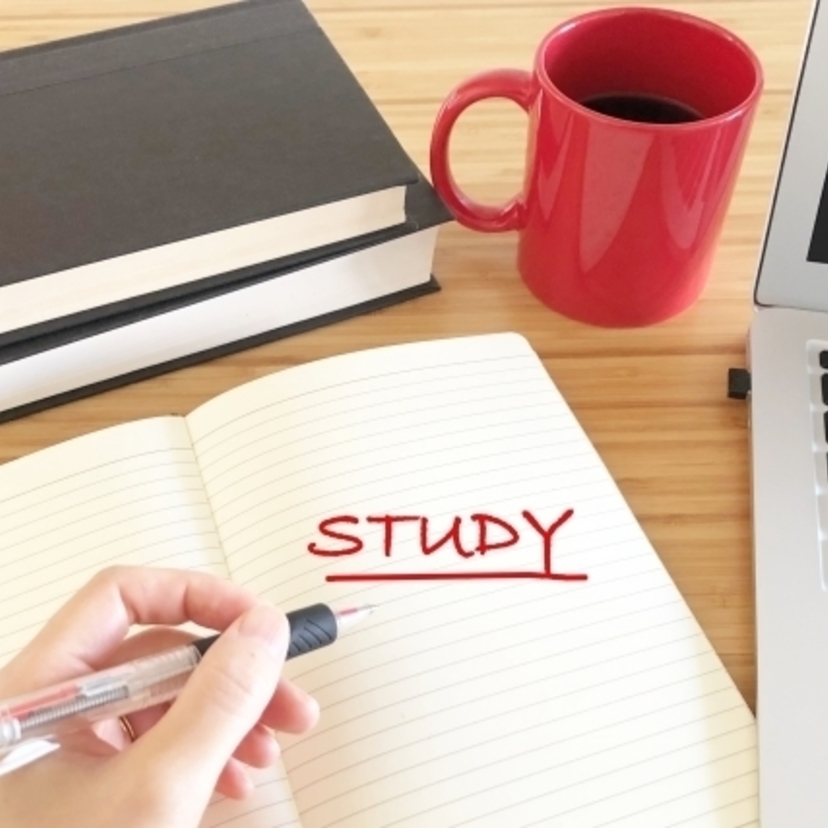



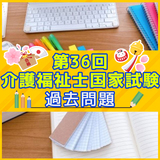
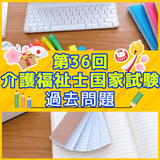
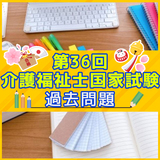









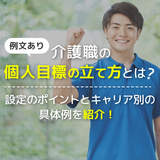











ささえるラボ編集部です。
福祉・介護の仕事にたずさわるみなさまに役立つ情報をお届けします!
「マイナビ福祉・介護のシゴト」が運営しています。