本日のお悩み:うつ病で休職中、このまま退職したらずるいと思われる?
復職と退職で迷っていましたが、退職を選ぼうと思っています。ただ、このまま辞めると周囲の人から「ずるい」「逃げた」などと言われないか不安です。
なぜ、他の病気では「ずるい」と言われないのにうつ病での休職は「ずるい」と言われてしまうのでしょうか。また、円満に退職できる方法も教えてください。
うつ病で休職・退職するのはずるいと思われる理由
主な理由は以下の通りです。
2.休職・退職者が出ることによって同僚の業務量が増えてしまう
3.休職中に傷病手当をもらっていることに対して不満を感じている
■1.うつ病に対する理解が足りない
また、症状によっては気分の高揚などを伴う場合もあるため、外見から判断してもらえないというのも大きな要因でしょう。 これらのことから、うつ病への理解がないと「気持ちや気分」で休めていて「ずるい」といった考えに繋がることがあります。
■2.休職・退職者が出ることによって同僚の業務量が増えてしまう
その結果、より「ずるい」といった気持ちが強まり、休職者の体調を心配する余裕がなくなってしまうのです。
■3.休職中に傷病手当をもらっていることに対して不満を感じている
そうなると、周囲からは働いていないのにお金をもらっていると勘違いをされ「ずるい」と言われることがあるでしょう。
うつ病で休職・退職する際の当事者・同僚・施設それぞれの視点で、対応方法を考えてみましょう!
ここからは、休職をする当事者・同僚・施設といったそれぞれの視点でうつ病での休職や退職に円満に対応する方法を紹介します。
当事者ができること|うつで休職。円満に退職する方法とは?
■解説者/専門家

資格▶介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士/ 経歴▶けあぷろかれっじ 代表、NPO法人JINZEM 監事/ プロフィール▶ 『介護福祉は究極のサービス業』 私たちは、障がいや疾患を持ちながらも、その身を委ねてくださっているご利用者やご家族の想いに対し、人生の総仕上げの瞬間に介入するという、責任と覚悟をもって向き合うことが必要だと感じています。
■関係法令をしっかり押さえて、ストレスなく退職する方法
鬱病を患い休職中とのこと。ご質問者さんの一日も早い回復を願うばかりです。
今はゆっくりと体と心を休めてくださいね。
では早速、当事者が円満に退職できる方法から考えていきましょう。退職の手続きをスムーズに行うためには、雇用契約等に関する関係法令をしっかり確認することが大切です。
以下で詳しく説明していきます。
■1.まずは自分の雇用形態を確認しましょう
まず、ご質問者さんが、正社員等の無期雇用職員かパートやアルバイトなどの有期雇用職員なのかで、退職の流れが変わってきますので、ご自身がどちらの雇用形態なのかを労働条件通知書や雇用契約書等の事業所との契約内容をご確認ください。
簡単に無期雇用職員・有期雇用職員をご説明すると、雇用の条件に期間の定めがあるかどうかということになります。
正社員や無期雇用職員であれば、期間の定めなく雇用が継続されていく雇用形態となり、パートやアルバイトなど、有期雇用の場合は、何月何日から何月何日までといったように、期間に定めがある雇用形態となり、期間満了日を迎えるにあたり、契約更新の取り交わしが行われることになります。
ここから関係法令とともに、それぞれの退職のルールや流れについてご説明させていただきます。
ー無期雇用契約(正社員など)の場合
その内容は、労働時間や休日、懲戒に関する事項や退職に関する事項など、様々なルールが記載されています。その内容は事業者によって異なります。例えば、退職についても『1か月前に申し出なければならない』や『3か月前に申し出なければならない』など、事業者によってそのルールが異なってくるということです。
では、この就業規則を遵守しなければならないのかというと、そうでもないのです。 退職のルールは民法でも定められており、就業規則のルールよりも民法のルールが優先されることになります。
では、民法において退職のルールはどのように規定されているのかということですが、『期間の定めのない契約は、いつでも解約の申入れをすることができ、雇用は解約申入の後2週間を経過したるに因りて終了する。』となっています。※
よって、退職の意思表示をきちんとすれば、民法上2週間後には退職ができるということになります。
就業規則で退職の申し入れを1か月後や、3か月後に定めている理由についてですが、 新たな従業員を補填するための猶予期間と考えられますね。 会社側と円満に退職を望むのであれば、就業規則に基づいた退職の申し入れをおすすめします。
出典:厚生労働省 退職の申出は2週間前までに
ー有期雇用契約(パート・アルバイト)の場合
ただし、結婚や出産等、『やむを得ない事由』がある場合はこの限りではありません。
また、会社と労働者が協議の上、合意が得られた場合も退職が可能となります。 さらには、契約期間の初日から1年が経過していれば、認められることもありますので押さえておいてください。
■2.退職の意思表示をしましょう
こちらには退職についての詳しい内容を記載する必要はありませんので、『一身上の都合により』と、簡潔に記載される内容で問題ありません。 また、『退職願』の場合は、『退職をしてもよろしいか伺います』といった、承認を得る意味合いになりますので、承認を受けて初めて退職となります。
つまりは、会社が承認するまでの期間は、退職を撤回することもできます。 また、承認されないといったケースもありますので、ご注意ください。
ー退職が承認されない場合は?
こちらの『退職届』には、会社の承認を得ずに一方的に退職の効力が発生します。 先述した2週間後には退職できるということです。 退職届を提出した後には撤回は原則できませんのでご注意ください。
いずれにせよ、退職の意向を伝えた時点で、特定の事由に該当しない場合は、事業者は退職させないということはできませんので、まずは上司に退職の意向を伝えるのが、よろしいかと思います。
ー内容証明郵便の活用も視野に
もちろん、対面で退職届の提出をおこなうことができれば理想的ですが、難しい場合は内容証明郵便などを活用する選択肢もあるでしょう。何より体調を最優先に選択していくことが大切です。
当事者ができること|うつ病で休職中・退職後にもらえるお金は?
■解説者/専門家

資格▶社会保険労務士・主任介護支援専門員・社会福祉士・介護福祉経営士1級・ファイナンシャルプランナー2級/ 経歴▶おかげさま社労士事務所 代表、地域包括支援センター センター長/プロフィール▶ 大学(福祉学)卒業後、大手教育会社を経て、介護業界へ転身。 介護業界に関わる人の優しさに触れると共に、低待遇と慢性的な人手不足の課題解決のため社会保険労務士の資格を取得し、2021年に開業。 地域包括支援センターでセンター長として長年勤務した経験を活かして、介護現場の最前線で活躍する事業所と人をサポートしている。 また、介護関連の執筆・監修者としての活動や介護事業書向けの採用・定着・育成・組織マネジメントなど、介護経営コンサルタントとしても幅広く活動中。
■お金の不安を解決!うつ病等で体調不良になった介護職が安心して休むためには
一方で退職をしたあとも次の仕事などを決めていないと、お金の不安は続きます。
これから、介護職の皆さんが治療に専念して安心して休むことができるようにお金の不安を解決していきます。
■在職〜休職中に受け取れるお金とは
まずは、以下の3点を確認・申請しましょう。
2.会社の休暇制度を確認しましょう
3.傷病手当金(健康保険)の申請をしましょう
■1.労災保険の対象か確認をしましょう
体調不良の原因が長時間労働による場合や業務上過度な負担が原因であった場合、労災保険の対象になる場合があります。労災認定が下りた場合は治癒するまでの医療費やその間の月々の生活費(約6割〜8割)、また障害認定が認められれば、障害補償年金などの所得補償がされます。
ただしこれは明らかに業務に起因するものでないと労災認定がおりません。
■2.会社の休暇制度を確認しましょう
勤務している事業所の就業規則または休職規定の確認しましょう。
会社に休職制度がある場合はそのルールに従って休職することになります。 休職制度は法律で義務づけられているものではありません。 休職期間や休職時の給与支給の有無は会社によって異なりますが、一般的には無給の会社が多いです。
また休職期間中も、社会保険料の支払いは免除されませんのでご注意ください。
■ 3.傷病手当金(健康保険)の申請をしましょう
以下の要件を満たせば給与(標準報酬月額)の3分の2が支給されます。※
・療養のため労務不良であること
・4日以上仕事を休んでいること
・給与の支払いがないこと
期間は通算1年6ヶ月となります。
この間に復職をされる方もいますし、復職されて再度体調を崩され休職をしても、所得が補償されるため安心して治療に専念できると思います。詳細は、会社の人事労務担当者に確認してください。
※標準報酬月額とは、4月~6月の3か月間の給与を平均したものです。
ー扶養内でパート・バイトをしている場合
逆に、パートなどの雇用形態であっても、自分自身が健康保険の「被保険者」の場合は受け取ることができます。 詳しくは、自分の保険証を確認してみましょう。
■退職後に受け取れるお金とは
もらえる可能性があるお金として、以下のものが挙げられます。
2.障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)
3.退職金
4.失業給付金
■1.傷病手当金(資格喪失後の継続給付)
・資格喪失時に傷病手当金を受けている、または受ける条件を満たしていること
■2.障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)
障害等級や世帯構成や月々の収入によっても異なりますが、平均7万円〜15万円ほどの受給が可能となります。
■3.退職金
ただし、支給の条件や金額は事業所によって異なるため、就業規則や上司に確認をとるようにしましょう。
■4.失業給付金
受け取れる条件は、以下の通りです。
・前職で雇用保険に加入していた人
・離職の日までの2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間がある人(※特定受給資格者等の場合は離職の日までの1年間に6カ月以上)
上記条件を満たしたうえで、もらえる金額や期間は以下の通りです。
※年齢によって異なります
・もらえる期間
被保険者期間10年未満:90日
10年以上20年未満:120日
20年以上:150日
※受給期間(お金を受け取れる期間)は離職日の翌日から1年以内です。まだ給付日数が残っていても、この期間を過ぎると給付金は受け取れません。早めに申請しましょう。
※離職理由、年齢、雇用保険の被保険者だった期間によって異なります。
■退職後も支払い続けなくてはいけないお金とは
■住民税
また、退職した翌年も住民税の支払いは生じますので、前もって住民税のお金は用意しておけると安心でしょう。
■健康保険
■国民年金
まとめて前払いをすると、割引が適用されるのでまとめて支払いができる場合は、一括で支払えるとよいでしょう。
当事者ができること|うつ病による休職・退職を「ずるい」と思われないためには?
とはいえ、周囲から「ずるい」と思われることを気にしてしまうと、それがさらに症状の悪化などに繋がることもあります。
ここからは、周囲の人にできる限り「ずるい」と言われないために、当事者ができる対策方法を紹介します。
円満に休職・退職をするために、当事者ができる主な対策は以下の通りです。
2.休職中に旅行や遊びに行ったことが会社の人に伝わらないようにする
3.休職を繰り返さないように療養に専念する
4.復職時には感謝の気持ちを伝える
■1.休職・退職の前に業務の引き継ぎを適切に実施する
また、利用者さんの情報等については、正確に引き継がないと事故に繋がる可能性があります。利用者さんの基本的な情報はもちろん、気になる点などがあればそこもしっかりと引き継ぐようにしましょう。
病状から、対面での引継ぎが難しい場合、データでの引継ぎを行う場合もあります。この場合は、個人情報の扱い等に十分留意するようにしましょう。
■2.休職中に旅行や遊びに行ったことが会社の人に伝わらないようにする
気分転換で旅行や外出をすることはよいですが、SNSなどへの投稿は周囲の人の気持ちも考慮するようにしましょう。
■3.休職を繰り返さないように療養に専念する
そのため、療養期間中は仕事のことを考えず、通院や食事、睡眠など回復にむけて専念するようにしましょう。
■4.復職時には感謝の気持ちを伝える
感謝を伝える際は、できる限り直接伝えることが好ましいですが、どうしても会うことができないなど事情がある場合は、電話やメールで伝えても問題ありません。
うつ病を理由に休職や退職を検討中の人の相談窓口7選
■1.ハローワーク
うつ病を抱えた状態や、治療を終えた状態での転職活動は負担もあるため、ハローワークなどを活用できるとよいでしょう。
また、全国に500か所以上設置されているため、自宅からアクセスしやすい相談所を確認していけるとよいでしょう。
参考:厚生労働省 ハローワークの相談支援
■2.労働基準監督署
労働環境が要因で体調を崩した場合、1人で抱え込まず相談をするようにしましょう。
参考:厚生労働省 全国労働基準監督署の所在案内
■3.障害者就業・生活支援センター
うつ病を抱える方に対しては、就業に関する相談やアドバイスなどを行ったり、生活のサポートを行ったりしています。体調を崩し、1人での生活や転職活動に不安を抱えている場合は相談ができるとよいでしょう。
参考:厚生労働省 障害者就業・生活支援センターについて
■4.地域障害者職業センター
休職などで、復帰に不安がある方は活用できるとよいでしょう。
参考:厚生労働省 障害者職業センターの概要
■5.就労移行支援事業所
無理なく少しずつ社会復帰を目指したい方は活用していけるとよいでしょう。
参考:厚生労働省 就労移行支援事業
■6.こころの耳
精神面に完全に特化しているので、相談をすることに抵抗などがあっても、比較的相談しやすい機関です。
参考:厚生労働省 こころの耳
■7.退職代行サービス
ただし、退職代行サービスを活用した退職を好まない事業所も多くあります。円満な退職を希望する場合は、自身で対応できるとよいでしょう。
同僚ができること|うつ病で休職する同僚のことを「ずるい」と思ってしまう…その対処法とは?
■解説者/専門家

ワ☆ノベーション代表 グロービス経営大学院経営研究科経営専攻修了(MBA) MBA(経営学修士)、公認心理師、社会保険労務士有資格者、社会福祉士。 総合心理教育研究所学術客員研究員。
なかには、「休めてずるい」と思ってしまうことも…。ここからは、同僚の視点でできる対処法や切り替え方法を解説します。
■対処法1:うつ病を理解する
うつ病を落ち着かせるには、治療方法を考える前に、心身の休養がしっかりとれるように環境を整えることが大事です。職場や学校から離れ自宅で過ごす、場合によっては、入院環境へ身を委ねることにより、大きく症状が軽減することもあります。精神的ストレスや身体的ストレスから離れた環境で過ごすことは、その後の再発予防にも重要です。
うつ病の治療には、医薬品による治療(薬物療法)と、専門家との対話を通して進める治療(精神療法)があります。また、散歩などの軽い有酸素運動(運動療法)がうつ症状を軽減させることが知られています。
これらを把握できているかどうかで、うつ病の同僚に対する接し方や考えを変えていくことができると思います。
参照:厚生労働省 こころの病気について知る
ーうつ病とは?
精神的ストレスや身体的ストレスなどが原因となり、脳がうまく働かなくなるとこれらの症状が出てきます。また、うつ病になると、ものの見方や考え方が否定的になります。
日本では、現在約15人に1人が一生のうちにかかっているため、決して珍しい病気ではないのです。そのため、うつ病と診断されるのが怖いと思われる方も多いですが、早めに受診し、適切な治療を受けることが大切です。
■対処法2:「セルフモニタリング」をしてみる
■「セルフモニタリング」とは?
つまり、今回の場合は「ずるい」と思った瞬間にリアルタイムで気づくことを指します。
「自分はこの人をずるいと思っているんだな」と、客観的視点で、もう一人の自分が自分を眺める感覚です。眺めていると自分の思考や気分・感情に巻き込まれずに距離をとれるようになっていきます。客観的に眺められるようになると、その気持ちを手放せるようになってきます。
自分の思考や気分・感情に評価・判断・分析せずにそのまま受け止めることをマインドフルネスと言います。ストレスに対処するうえでも、ずるいと思っていることに気づかなければ対処できません。まず、このトレーニングをしてみてください。このセルフモニタリングだけでもかなり効果があります。
ー1.「ずるい」と思った瞬間を客観的に見つめてみよう
・どこで:スタッフルームで
・誰に:上司の○○さんからの共有
・ずるいと思ったきっかけ:○○の理由で
次にその時の自分の体験を書き出します。
・感情:イライラ、モヤモヤ
・行動:舌打ち
・身体反応:少し重い感じ
※ネガティブな態度や行動は、自分も相手も傷つきますので建設的な行動をしていきましょう。同じような状況になった時は、ゆっくり深呼吸してみましょう。
このように書き出して整理しておくことでデーターベースができてきます。同じような状況になったときに対処しやすくなります。
ー2.自分の「ずるい」という気持ちと向き合ってみる
たとえば、「私だって本当は休みたいよ…。羨ましいなあ」「今も人員不足なのに、もっと大変になる…。」「もう限界なのに、もっと私が頑張るしかないのか…。」などです。
自分の体験と深く向き合うことで、気持ちが落ち着いてきます。落ち着いて少し冷静になったらずるいと思われた相手はどんな気持ちなのか、反対に自分がずるいと思われたらどんな気持ちなのかイメージしてみてください。
■その他知っておくと活用できるマインドコントロール方法
→深呼吸をしながら、マイナスな気持ちを吐き出す呼吸法です。
・自身に労りの声かけ(プローブ)をする
→日々頑張っている自分に労りの言葉をかけてみましょう
・心の整理術(クリアリングスペース)
→ずるい・きついなどといった気持ちの置き場所を考えてみましょう
事業所や施設ができること|うつ病による休職・退職に施設側がやるべき対処法とは?
事業所側が行うとよい対応は主に以下の通りです。
2.うつ病で休職・退職する従業員に就業規則を理解してもらう
3.メンタルヘルスに関する研修を実施する
4.増員や業務の負担調整を実施する
■1.「うつ病」など特定の病名を公表しない
また業務上、必要があって伝える場合でも、本人の同意は必要です。トラブルにならないよう同意をもらう際は書面などで証跡を残せるとよいでしょう。
■2.うつ病で休職・退職する従業員に就業規則を理解してもらう
口頭での説明だけでなく、内容を確認したことを証明できるよう書面などで証跡を残せると後々のトラブルにも繋がらず安心でしょう。
■3.メンタルヘルスに関する研修を実施する
研修では、そもそも精神疾患がどのようなものなのかであったり、どのような対応や声かけがよいのかなどの知識を確認していきます。厚生労働省が運営する「こころの耳」にはメンタルヘルスに関するeラーニングや研修に活用できる情報などが掲載されています。これらを活用して研修を行うのもよいでしょう。
参考:厚生労働省 こころの耳
■4.増員や業務の負担調整を実施する
休職をした人に不満がある状態のまま進めてしまうと、休職者の職場復帰が上手くいかなくなってしまう可能性もあります。そのため、事業所側としては人員補充や業務の再分担を行う必要があります。慢性的な人員不足の事業所にとっては、なかなか対応が難しいと思いますが、どこかで業務負担を軽減する工夫策がないか模索していくだけでも、現場の従業員のモチベーションは変わります。
最後に:うつ病などへの理解を深め働きやすい環境づくりをしましょう!
すべてに共通して、うつ病などの精神疾患に対する理解があるかどうかが大きなポイントであるとわかったかと思います。うつ病はいつ誰が発症してもおかしくない精神的な病です。休職ができることを羨ましいと感じる方もいらっしゃると思いますが、当事者は大きな苦しみや不安を抱えています。
うつ病に関する知識を深め、職場全体でサポートしていけるようになるとよいでしょう。
■あわせて読みたい記事
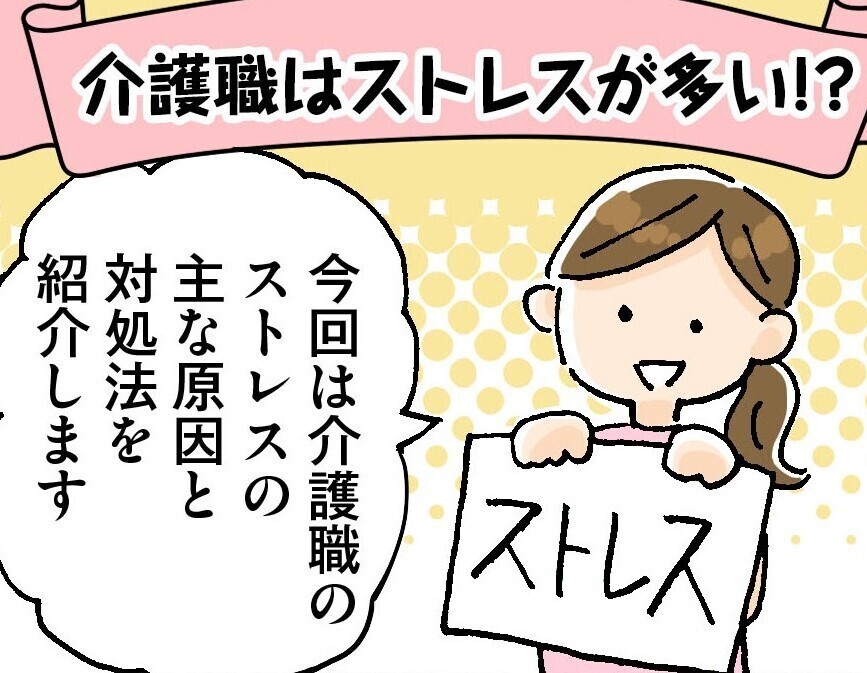
介護職はストレスが多い!? 主な原因と限界になる前に対処する方法 | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/648介護職は重労働でストレスを感じやすい仕事です。なかにはストレスで心身の調子を崩して離職する人も。ストレスをためない工夫をしつつ、つらいときには早めに対処することが大切です。介護職のストレスの主な原因と対処法を紹介します。【コラム:島田 友和 伊藤 浩一 古畑 佑奈】
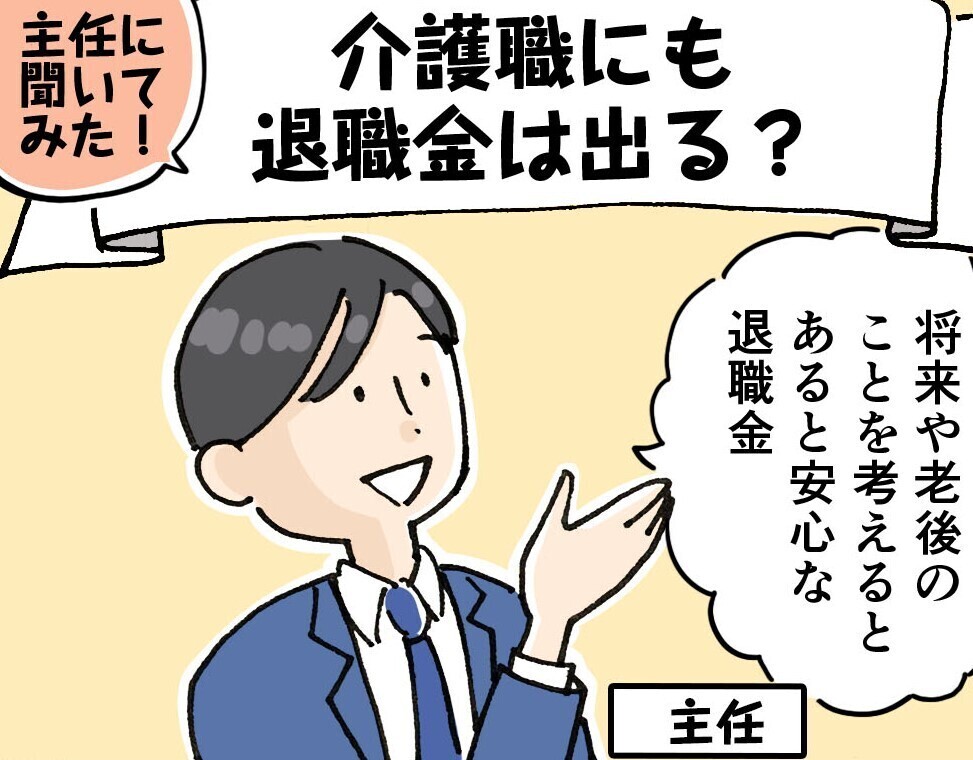
介護職にも退職金は出る?制度の仕組みや金額の目安を知っておこう | ささえるラボ
https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/567将来や老後のことを考えると、あると安心な退職金。介護職も、勤務する事業所によっては退職金をもらえる可能性があります。退職金制度の種類や仕組み、介護業界の退職金事情、退職金の有無をチェックする方法を解説します。【執筆/マイナビ編集部、専門家:大庭欣二】

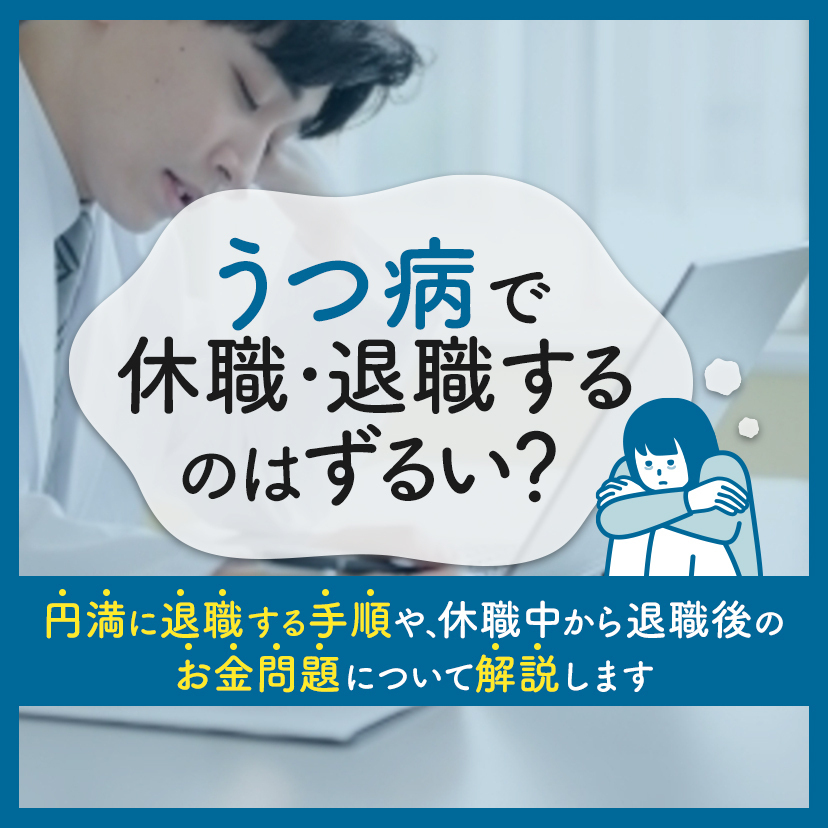





























・けあぷろかれっじ 代表
・NPO法人JINZEM 監事
介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士